まず、文化関係団体の育成に関していえば、従来その意義が認識されながらも、そのための活動が活発になされてきたとは必ずしもいい難いものであった。たとえば、昭和四十五年版『港区の社会教育』(東京都港区教育委員会社会教育課編)は、その問題について、次のようにのべているのである。
本区における文化活動としては、「文化財調査委員会」の設置や、社会教育法第十条にいう社会教育関係団体としての自主グループの育成等をおこなっているがそれほどめだった活動とはいえない。しかし情報化時代を迎え、さかんに『生きがい論』が話題になる今日、人々の精神的なものへの要求が高まりつつあるとき、文化活動への期待も大きい。そのために文化財保護への市民運動を組織化し、住民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成する努力が必要である。
右に明らかなように、区教育行政における文化普及活動は、従来停滞しがちであったのであるが、しかし、近年の週休二日制の普及にともなう余暇の増大は、区民の文化活動への要求を高め、それに対する区の後援・育成を活発化させることになった。
とくに、港区俳句連盟、港区茶華道連盟、港区珠算振興会などは、近年、展覧会や大会を恒例化して開催しており、社会教育行政の大きな成果といいうるのである。また、最近では、教育委員会が主催した成人学級や婦人学級の参加者が学級終了後に自主グループを結成し、継続的活動を活発に展開しており、本区では、こうしたグループの自主的活動を積極的に後援しているのである。たとえば、昭和四十八年度からは、「グループづくり研修会」を開催し、社会教育の概念、今後の社会教育の方向、自主グループの必要性、自主グループの組織方法などについて講師を招いて指導を行なっており、自主グループや連盟の活動をできる限り援助し、育成せねばならないことを確認している。
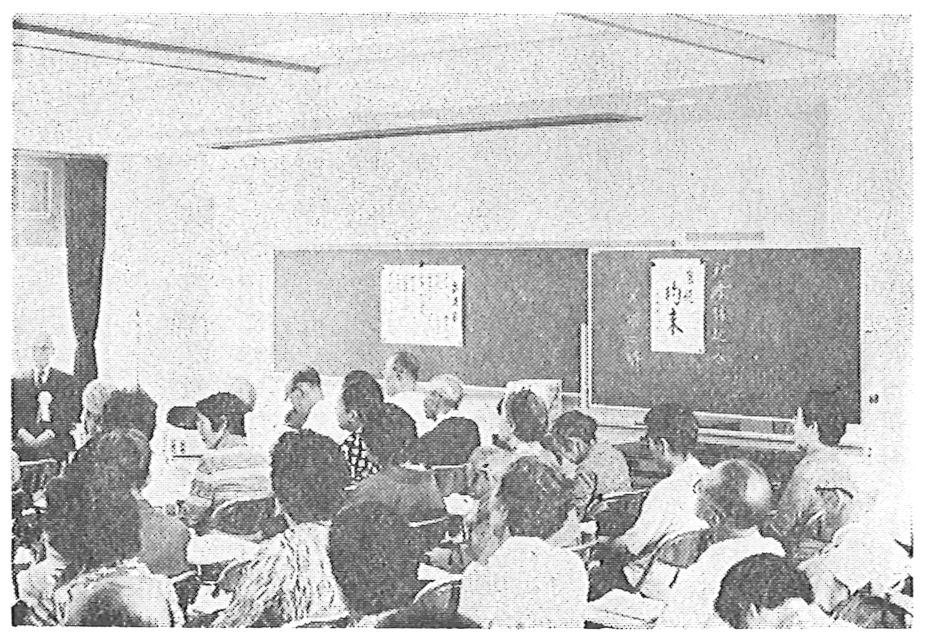
港区俳句大会風景
なお、各文化団体連盟関係の活動状況は、表46のとおりである。
表46 各文化団体の連盟関係活動状況
昭和四十六年度
| 行 事 名 | 期 日 | 会 場 | 参加者 |
| 港区茶華道展 港区俳句大会 港区珠算競技大会 | 六月一三日(土)・六月一四日(日) 一一月八日(日) 一一月一五日(日) | 港区青年館 港区青年館 港区芝公会堂 | 延五六六名 八〇名 二〇〇名 |
昭和四十七年度
| 行 事 名 | 期 日 | 会 場 | 参加者 |
| 港区茶華道展 創立一〇周年港区俳句大会 港区珠算競技大会 PTAコーラスのつどい | 五月二九日(日)・五月三〇日 一〇月二四日(日) 一二月五日(日) 一二月四日(土) | 港区青年館 港区青年館 港区芝公会堂 港区青年館 | 延九八八名 八八名 二二〇名 三二〇名 |
昭和四十八年度
| 行 事 名 | 期 日 | 会 場 | 参加者 |
| 港区茶華道連盟二五周年記念式典ならびに華道展 茶会 港区俳句大会 港区珠算競技大会 | 五月二六日(土)、五月二七日(日) 四月七日、四月八日 一〇月七日 一一月二三日(祝日) | 高輪プリンスホテル 高輪プリンスホテル 港区青年館 港区芝公会堂 | 延二〇〇名 延五〇〇名 八一名 二五八名 |
昭和四十九年度
| 行 事 名 | 期 日 | 会 場 | 参加者 |
| 港区俳句大会 港区茶華道連盟秋季大会 港区珠算競技大会 | 一〇月六日(日) 一〇月一二日(土) 一二月一日(土) | 港区青年館 港区青年館 港区青年館 | 七四名 三四〇名 一八七名 |
昭和五十年度
| 行 事 名 | 期 日 | 会 場 | 参加者 |
| 港区俳句大会 港区珠算競技大会 港区茶華道連盟いけばな展 | 八月三一日 一一月一六日 一一月二九日、一一月三〇日 | 港区青年館 港区青年館 港区青年館 | 六四名 一八七名 延六七〇名 |
昭和五十一年度
| 行 事 名 | 期 日 | 会 場 | 参加者 |
| 港区俳句大会 港区珠算競技大会 港区茶華道連盟秋季大会 | 九月五日(日) 一一月七日(日) 一一月二七日(土) | 港区青山社会教育会館 港区立赤羽小学校 港区青年館 | 六五名 二三六名 一二八名 |
【新生活運動】 せまく文化活動に限定されたものではないが、しかし区民の自主的・主体的活動をその本質としなければならないものに、新生活運動がある。
港区では、昭和三十七年度に、港区新生活運動推進協議会が結成され、活動目標を、「①清掃実践活動、②ゴミの減量運動、③蚊とハエの駆除、④花いっぱい運動」の四つに設定したのである。この新生活運動は、とくに高度経済成長政策が推進されるなかで、日ごとに生活環境が悪化していった昭和四十年代以降その重要性をいっそう増したのである。
近年の港区における新生活運動は、生活学校運動を中心としており、昭和五十一年度は、七つの生活学校が開設されている。この生活学校は、新生活運動の展開のなかから主婦主体の運動として生みだされたものであり、くらしのなかで具体的に困っていること、不安なこと、迷っていること、望んでいることなどを具体的に出しあって、解決をはかる糸口をみつけ出し、問題の具体化をはかることを目的とするものである。
生活学校運動の昭和五十一年度の活動状況は表47に示すとおりであるが、港区では、生活学校運動とともに課題活動を推進している。すなわち、ここ数年の例をあげれば、昭和五十年度から全国および都レベルと共同歩調をとって「資源を大切にする運動」を展開し、港区独自の活動として、水資源の汚濁防止運動を中心に取り組み、調査・実践活動を各生活学校が実施し、啓発活動として節水の呼びかけなどを行なっている。
表47 生活学校の概要と活動内容
| 学校名 | 地 域 | 生徒数 | 活 動 内 容 |
| 三 田 | 商・住街 | 五〇 | 健康管理、食品の安全性、合成洗剤・プラスチック製品等の安全性、資源再利用等の学習活動、啓発活動、改善活動。日常生活における生活改善活動、啓発活動。不用品交換会、料理講習会、諸工場見学会、講演会、宿泊研修会など。 |
| 高 輪 | 〃 | 六〇 | |
| 六本木 | 〃 | 五〇 | |
| 青 山 | 〃 | 五〇 | |
| 麻 布 | 〃 | 五〇 | |
| 日の出 | 〃 | 二五 | |
| 御成門 | 〃 | 五〇 |
【東京みなと音頭】 そこでとくに新生活運動の領域にくみ入れられるものではないが、区民の文化生活と深い関連をもつものとして「東京みなと音頭」の制作をあげることができる。
すなわち、「東京みなと音頭」は、「いままであった音頭は、昭和二十四年に制作したもので、急速な時代の移り変わりにより、歌詞、リズムなどが現代にマッチしなくなり区民の多くの方々から、いまの時代にふさわしい音頭を作ってもらいたい」との要望が強まったのを背景に、昭和五十年十月に制作・発表されたものである。同音頭の歌詞は、次のとおりであるが、その特徴は、制作にあたって、区内の現状を国際色の豊かさや、緑の多いことで表わす反面、昔なつかしいイメージをも忘れないように、近代的ななかにも歴史的な感覚をとり入れ、老若男女を問わず、広く各年齢層に親しまれ、愛され、容易に歌え、かついつまでも忘れられないものとなるように配慮されていることである。
「東京みなと音頭」
作詩 吉川 静夫
作曲・編曲 小沢 直与志
一 花の日本は ここから開く
夜の新橋 六本木
あなたと私は 一本気 ソレ
あなたと私は 一本気
二 若さいっぱい 青山通り
緑いっぱい 街づくり
粋な世界の 飾り窓 ソレ
粋な世界の 飾り窓
三 出船入船 高輪沖に
恋の積み荷は なぜできぬ
想い出消えない いつまでも
ソレ
想い出消えない いつまでも
四 灯りなつかし 赤坂あたり
風にほつれる 日本髪
浮世絵みたいな 情け街 ソレ
浮世絵みたいな 情け街
五 みなと音頭は 世界の音頭
青い眼をした ひともいる
おどれば心も 円くなる ソレ
おどれば心も 円くなる
六 ここはどこでも 幸福の町
名さえ港区 みんなとく
東京タワーより 名は高い
ソレ
東京タワーより 名は高い
七 東京みやげは 音頭にきめた
唄と踊りと この笑顔
手拍子鳴らせば 月がでる
ソレ
手拍子鳴らせば 月がでる
この「東京みなと音頭」の初披露は、昭和五十年十月十三日に区立青山中学校で、港区体育祭の開会式の第二部として行なわれ、また、そのレコードも製作され、町会、自治会、婦人会、母の会、PTA、老人クラブ、商店会等の団体に無料で配布し、その普及を図っている。さらに、昭和五十年からは、個人にもこのレコードを一枚二百十円で頒布するとともに、同年七月にはこの音頭の踊り方の講習会を、港区スポーツセンターで開催している。

「東京みなと音頭」唄と踊りの講習会
【文化財保護活動】 次に文化財保護活動についてのべれば、その活動が正式に発足したのは、昭和三十九年であった。すなわち、港区では、昭和三十九年に文化財調査委員会を設置し、区内に埋もれている文化財の調査、資料の収集を開始したのであるが、それは、日本の高度経済成長政策のもとで推進された急速な都市開発によって、貴重な文化財や資料が破壊・消失の危機にさらされたからである。とくに、港区は、海岸に接していて、幕末からの日本の歩みがここから始まったということもあり、二三区のなかでも文化財が豊富に残されているところであり、したがって、この文化財調査委員会の活動は、単に港区レベルにとどまらない、歴史学的にも重要な意味をもつのである。
同委員会の活動は多岐にわたっており、右にのべたような文化財の調査、資料の収集をふまえて、その結果を毎年、『港区の文化財』という一冊の本にまとめて発表し、また、国や都の指定以外の文化財や資料のなかでとくに港区において重要な意味をもち区民に周知させたいものに「文化財標示版」を設置することを、昭和四十七年度から毎年行なっている。このほか、文化財に関心をもっている人々のハンドブックとして『港区文化財のしおり』(昭和四十六年初版発行、同四十七年、四十八年、五十年にそれぞれ改訂あるいは増補改訂、――港区独自の文化財標示についてはこの『しおり』を参照)を発行したり、「港区の文化財スライド」を作成したり、文化財めぐり(昭和五十一年度は二回)を行なうことによって、区内の文化財の紹介につとめている。
このほか、文化財調査委員会から成人学校などに講師を派遣し、文化財の今日的意義、保護思想の普及につとめている。
なお、『港区の文化財』は、昭和五十二年度までに合計一四冊発行されているが、その内容は表48のとおりである。
表48 『港区の文化財』既刊一覧
| 号 数 | 題 名 | 発行年月日 |
| 第 一集 二 三 四 五 六 七 八 九 一〇 一一 一二 一三 一四 | 幕末の外交史跡 海岸の歴史と風俗 増上寺とその周辺 麻布―その南西部 赤坂・青山―その1 高輪・白金―その1 三田と芝―その1 新橋・愛宕山付近 麻布―その北東部 高輪・白金―その2 三田と芝―その2 赤坂・青山―その2 港区の文化財第13集 港区の文化財第14集 | 昭和 三九年一〇月一〇日 四一 三 三〇日 四二 三 一五日 四三 三 三〇日 四四 三 三一日 四五 三 三一日 四六 三 三一日 四七 三 三一日 四八 三 三一日 四九 三 三一日 五〇 三 三一日 五一 三 三一日 五二 二 二一日 五三 三 三一日 |