【労使協調めざした戦前の協調会】 この機関が本区内に設けられた要因は、何よりも協調会が存在していた点にある。第一次大戦後の労働運動の活発化、とくに米騒動に驚いた政府・財界が、労働問題、社会政策に関する調査研究と労資協調の立場からする社会政策を進めるために大正八年(一九一九)設立したのが協調会であった。資金は主に財界からの寄付金でまかなわれ、政府からの一部補助金があったが、いちおうは純然たる民間機関であった。この点、第二次大戦後の中央労働委員会が公的政府機関であるのとは基本的に異なるが、労働争議の仲裁・調停・斡旋を目的とした点は、共通性をもっていた。協調会は、中労委発足後もしばらく存続し、昭和二十一年八月、GHQによって解散させられた。解散命令の理由は戦時中、協調会の内部から産報運動を提唱、協調会をその母体たらしめようとの意図にもとづき、産業報国連盟がつくられたためである。実際の産報運動は、政府の手による産業報国会によって本格的になり、産報を主張する人びとは協調会を出て、留まったものだけで調査・教育活動を続けていた。中労委の発足とは別に、新たな研究・教育機関として中央労働学園が発足したが、これは明らかに協調会の後身とみてよいだろう。
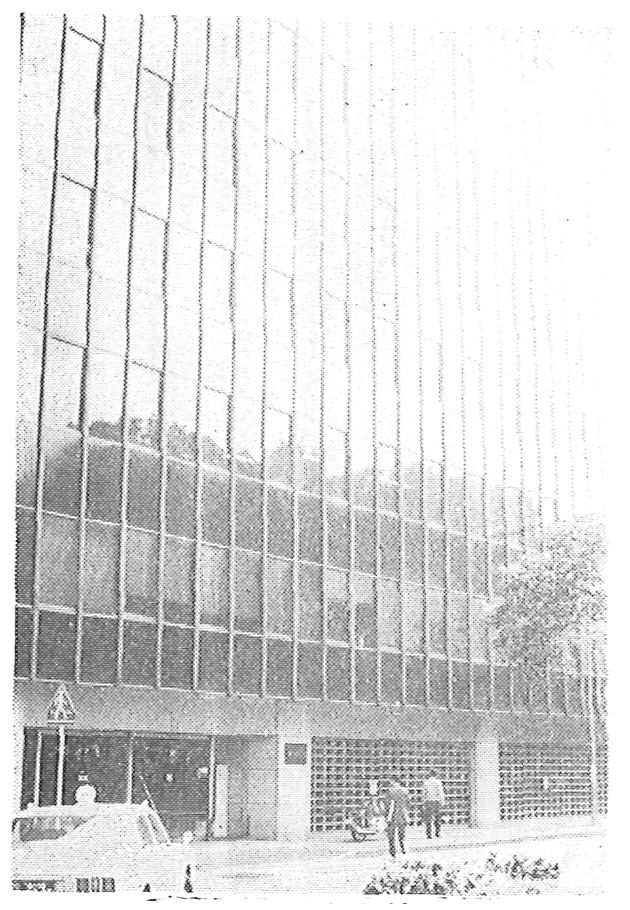
労働委員会会館
【労働組合法制定・公布】 昭和二十年十月四日のGHQ覚書と、同月十一日マッカーサー司令官が幣原首相に「労働組合の結成を促進すべき」旨の指示を与えたこともあって、政府は同月二十七日、労務法制審議会に労働組合法案の立案を諮問した。同審議会は第一・二回委員会を芝白金台の伝研(現 国立公衆衛生院)で、第三回以降は駿河台の東亜研究所で行なわれた。そして末弘厳太郎による原案をとりまとめ十一月二十四日答申をだした。政府は十二月の第八九議会に労働組合法案を提出、同月二十一日法律第五一号として制定・公布したのである。戦前の歴史と比べれば、まことに手際よくことを運んだのである。
【中労委創設される】 労働組合法が翌昭和二十一年三月一日施行と同時に、法の定めるところに従って厚生大臣の所管下に、中央労働委員会が創設され、同日事務局を芝公園六号地(現 芝公園一丁目五番)に開設したのである。当初の原案では名称が「中央労務委員会」となっていた。そのいきさつを委員の一人であった山中篤太郎は、次のようにのべている。
「『労働』とすべきかどうかということについては初めから議論があった。ぼくが記憶しておるのは、京都から出た社会党の水谷さん(長三郎氏)が『勤労』という字を、非常に軍国調である、断じて『労働』にしなければいかぬということを盛んに議論していました。ところが『労務』という言葉が、これは末弘さんの原案で、末弘さんが自分で書いたものだから出てきたが、諸君『労務』は困る。『務』は困る……という結論だった。……」(中労委編『中労委十年の歩みを語る』二三頁)。