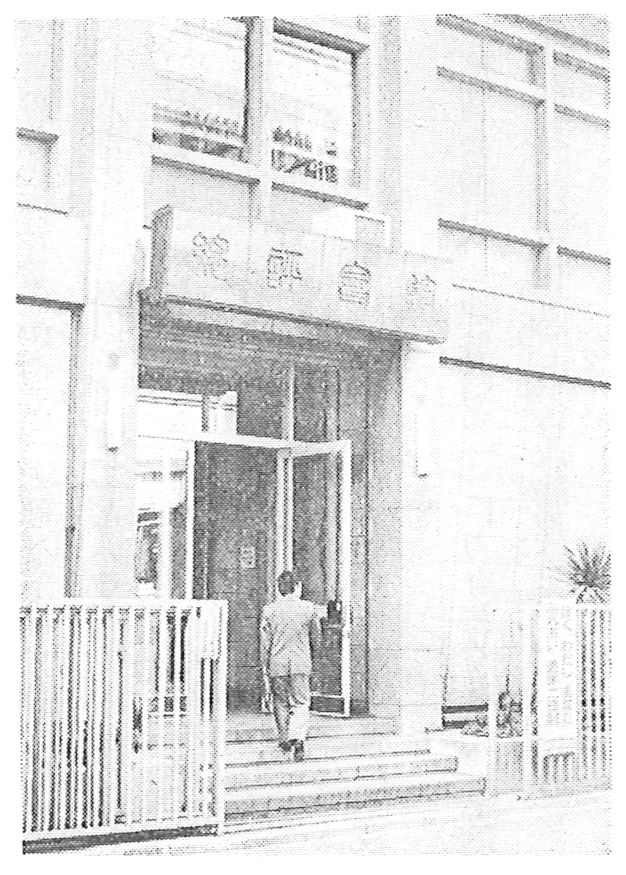
現在の総評会館
【「全労会議」へ走った総評の四単産】 翌二十六年総評は、単独講和反対闘争に乗りだすとともに、民同左派の高野実らが指導権を握り、二十七年二月の賃金綱領発表(マーケット・バスケット方式)で労働者の異常な関心と支持を集めた。同時に、講和条約発効にともなう労働組合規制に反対する「労闘スト」を展開することによって、階級的立場を確立し、名実ともに日本の労働運動の全国的・指導的存在となった。この転換は、戦前から合法左翼の線を歩んできた高野実が事務局長になったことや、炭労・電産・全港湾の労働者がストライキを闘って、下からの力で左旋回を支えたこと、さらには総評に結集したかなりの部分が、産別会議の側における政党を労働組合より一段高い存在とみる思想にたいする正しい批判の側面をもっていたし、労働者組織の「統一が重要であるという立場から」総評に参加した組合もかなりあった(芳賀民重氏談)ことなども、その要因をなしていたといえよう。この成長の過程で総評の行き方に反対の全繊同盟・海員組合・全映演・日放労の四単産は脱退し、二十九年(一九五四)四月全労会議を結成し、本部を麻布市兵衛町二の四(現 六本木一丁目二七番)に置いて、反共・生産性向上の方針で労働運動右派の結集体としての登場した。
【総同盟刷新強化運動協議会 総同盟と全労会議が合同】 また、これより先、総評結成にともない二十五年十一月の大会で総同盟解散の決議にさいして、全繊同盟ほかはこれに反対して退場し、総同盟刷新強化運動協議会をつくり、翌二十六年六月に総同盟を再建し芝三田四国町二(現 芝二丁目二〇番)に事務所を置いた。ただし、この段階では中心となるべき全繊同盟が加わらなかったため弱勢となったが、その後における総評脱退の四単産とともに総同盟も加わって全労会議を盛りたててきた。やがて昭和三十九年(一九六四)十一月十一・十二日、全労会議と総同盟は合同して現在の全日本労働総同盟(同盟)となったのである。
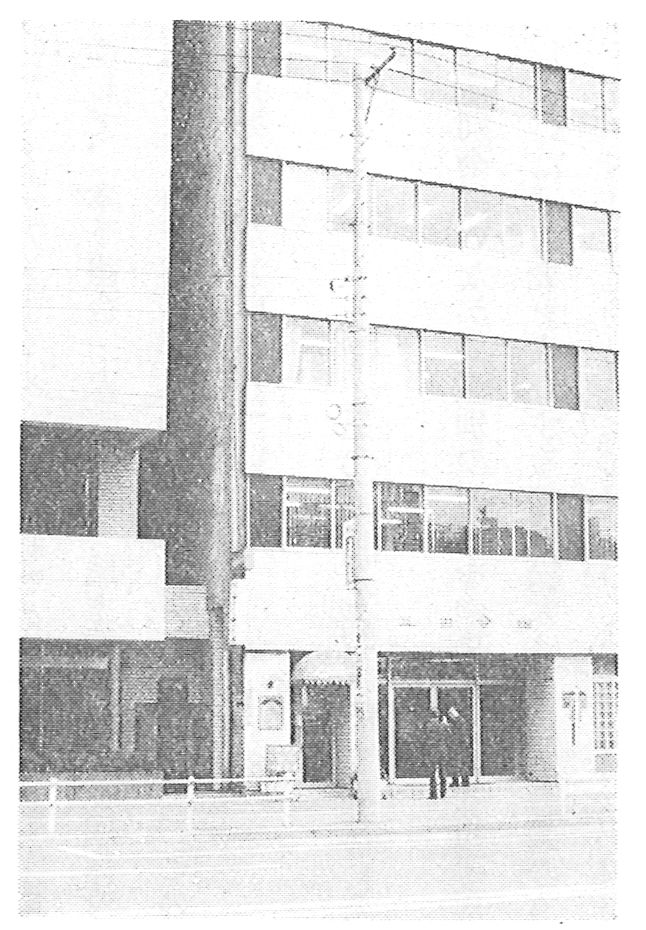
同盟本部のある三田友愛会館