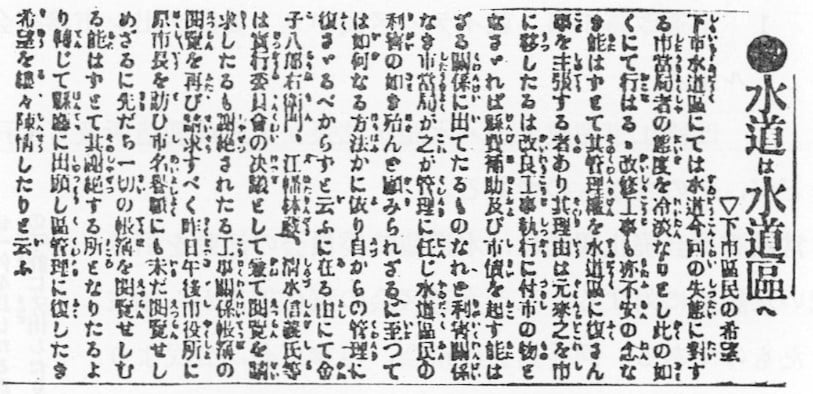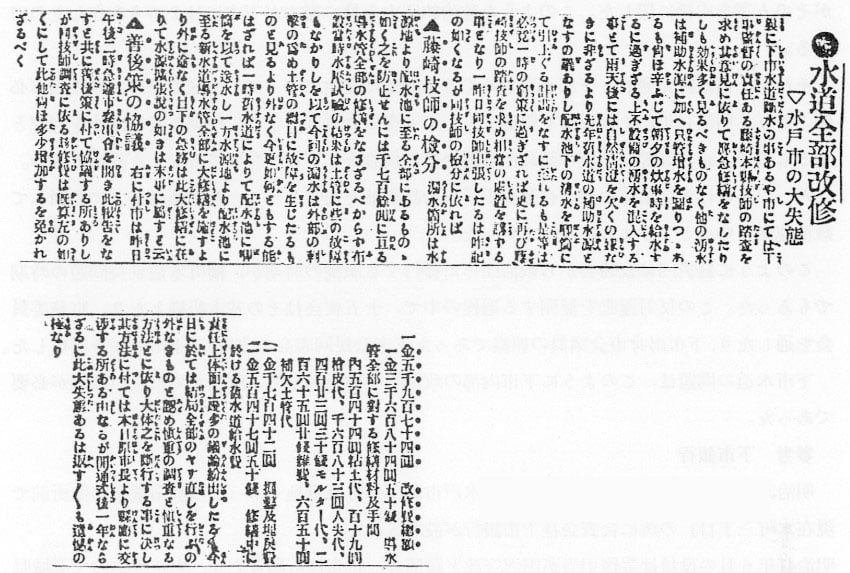5つの要求の1つである給水時間の延長について,市参事会は水量試験のためと称して5月18日より3日間不断(ふだん)給水をした。不断とは,いつもとか絶えずということで,24時間断水することもなく給水するということである。このために必要なる経費が,これまでとそれほど変わらなければ,不断給水を続けたいとある。
この時の揚水機関の運転1時間での揚水量は配水池の水嵩を4寸高くする,そして用水量は5寸程度であるため,毎日10時間の運転をしていた。不断給水となれば,この揚水機関の運転時間では配水池の貯水量が不足するから,現在より2,3時間の運転延長が必要となる。その試験を,水道区民の要請を受けて,市参事会が始めたのである。
ところが,7月1日午前7時ごろ,配水池下に設置してあった揚水ポンプのエンジンが不調となり,運転を一時ストップした。そのため給水が止まり,朝の食事などの用意ができず下市一帯は大騒ぎとなった。まもなく故障は修理され,10時には全配水管に水が充満し,正常になったが,このような問題が保守点検の技術能力が低かったため,ときどきあった。
これらの問題も含めて,44年早々の断水や減水などの失態は,市当局の水道に対する態度が冷淡であるからだと下市水道区民は考えた。
5つの要求のなかに,水道改修工事には下市区民より立会人を出すことも記してあったが,なかにはそれでも不安であるから,その管理権を水道区に取り返すことを主張する強硬な意見もでてきた。もともと水道事業はその水道区で運営していた。それが発展的改良工事をするため,県費の補助を受けたり,市債を発行して資金を入手する手段として,便宜的に市に移管したにすぎない。利害関係のない市当局が管理することになったため,水道区民の利害は無視され,各種の失態が多くなった。それを解決するには,水道区が直接に水道事業を管理する以外に方法がないという。
そのために下市区民で実行委員会を組織し,その決議として金子八郎右衛門・江幡林蔵・清水信義などが,水道工事関係帳簿類の閲覧を市当局に請求した。5月25日にも市役所に原市長を訪問し,再び閲覧を請求した。このときも市名誉職にも閲覧させていない帳簿類を,一般区民に提示することはできないと拒絶された。下市区民は,この閲覧によって水道事業の水道区管理に一歩でも近づくことができる段階と考えてもいた。そこで県当局に,帳簿類の区民への公開と水道の区管理移管を,市に指令されるよう陳情した。しかし,それは認められなかった。