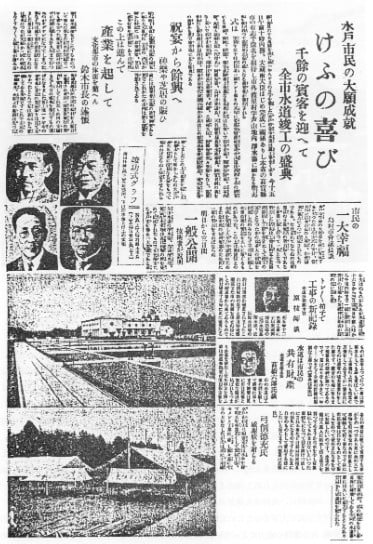昭和7年7月15日の竣功式当時,鈴木市長は「いはらき新聞」紙上に,「この上は進んで,産業を起して,文化都市の体面を整へん」と題して,つぎのように語っている。
施工前水源地をどこにするかについて悩んだ事,また給水料問題で一年ももみ合った事,本省に認可申請中に内閣が変り9分9厘まで行った事がオジャンになってしまった事など今は総て昔の思出話になりました。着工後一番心配になったのは増水だったが,天祐か1回の増水もなく,すらすらと難工事が済み市会議員諸氏が市民の福利を大眼目に努力され,吏員一同昼夜兼行の努力を実行してくれたため,何の支障もなく今日の盛典を興行する運びになりました。着工後1ケ年半の短期間に吏員の緊張振りは且て見なかったところで,私は専心から感謝してゐる次第です。これで市民の保健衛生,火防上の施設は先づ完成しました。この上は産業を起し,文化都市として恥かしからぬ大水戸市たる様に清新なる気をもって努めねばならぬと痛感させられる。
また,同誌面に,島村市会議長が,「市民の一大幸福」と題して語っている。
水戸市空前の大事業をここに完成するに至ったのは,全市民の支持,当局者に鈴木市長の大英断,市会議員の協力によって結成されたものである。なお,忘れてならぬのは従業員の日夜兼行の努力振りである。大事業に対して打って一丸となって努力した結果は,工費約50万円程節約し,工期を半分にして竣工の運びとなった。市の為多大の利益を招集したのみならず不況時に際し,失業救済の実績を大いに挙ぐるものがあった。この上は常磐村との合併を実現し,大水戸市建設のため,また全市民の福利増進のため更に一層の努力をせねばならぬ。
これらに対して,臨時水道部庶務主任の高橋六郎は,「水道は市民の共有財産」と題して,使用の問題について語っている。
市の水道は工事の体を脱して経営に移ります。経営は更に市住民達と緊密な関係が結ばれる。つまり水道を使用し使用料金を払う事は,水道布設費の償却確定額を各自の受益に応じて負担する事がその一つであり,更に此の大工事物を市民各位の共有財産として維持して行く事なのです。故に市民各位は自分のものとして親しみを持って使用される事を切にお願したいのです。水道の設備は8万人に給水し得る能力を持っていますから,水を少し位無駄にしてもかまはないといった気持ちになって栓を開けっ放しにされる事などは,結局市民相互の損失になるのですから,お互に自分のものとして愛用する様にしたいと存じます。