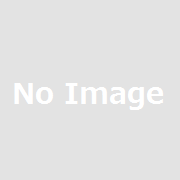笠原水道の調査・設計にあたった平賀保秀は、『水戸市史』中巻①によると、元は下総(千葉県)佐倉の堀田家に仕えており、数理・天文・地理などに通じた人物であった。江戸時代後期の文政九年(一八二六)に笠原水道の記念碑として建てられた「浴(よく)徳(とく)泉(せん)」の碑には、平賀は初代藩主徳川頼房の時に水戸藩に召し抱えられたむね記されている。これに対して『水戸の水道史』は、平賀について、水戸藩士の系譜を集めた『水府系纂(すいふけいさん)』を引いて、堀田家の臣であったが堀田家とりつぶしののため浪人となり、寛文二年(一六六二)十一月、二代藩主・光圀の時に五百石・大番組の士という破格の待遇で召し抱えられたと紹介している。平賀は寛文九年には郡奉行となり、延宝五年(一六七七)に隠居して舟翁と号し、天和三年(一六八三)に没した。
設計者平賀保秀について
14 ~ 15
平賀が仕えた佐倉の堀田家は万治三年(一六六〇)、堀田正信が幕政を批判し無断で佐倉に帰ったため改易されており、平賀の水戸藩招聘(しょうへい)をその二年後の寛文二年とするほうが理屈に合う。しかし寛文二年は笠原水道の工事が始まった年で、一年半後の寛文三年七月には完工したとされるから、寛文二年十一月に平賀が水戸藩に迎えられて調査・設計にあたったのでは、計算が合わなくなる。正式に藩士となる前、外部の技術者として水戸藩の委嘱を受け、すでに調査・設計にあたり、それに基づく工事が順調に進んだため、寛文二年十一月の時点で正式採用になった、と考えれば、破格の待遇も説明がつく。しかし、工事の詳しい記録が残っておらず、確かなことはわかっていない。