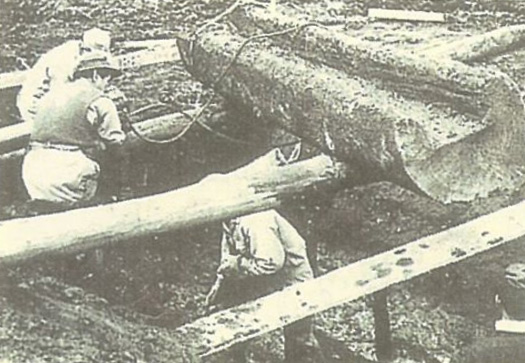その笠原水道は江戸時代前期の寛文三年(一六六三)に完成した後、江戸時代を通じて使われ、明治時代に入ると、竹樋の引き込み線によって各戸給水となり、いっそう利用されるようになる。しかし、需要の増大や施設の老朽化、衛生上の問題もあって、改良が迫られた。そして明治四十三年(一九一〇)、水戸市は、下市全地区を給水地域とし笠原水道の水源地近くとその他を水源とする、鋳鉄管による自然流下方式の水道を完成させ、さらに昭和七年(一九三二)、那珂川を水源とし水戸市街地全体を給水区域とする近代水道を完成させる。こうして、笠原水道は住民生活を支える上水道としての長い歴史の幕を閉じたのである。
三百年の長い歴史―江戸から昭和へ
19