戦後の混乱期も脱した昭和三十年以降、合併後の諸事務処理を行うとともに、町では新町建設審議会を設置し、新市町村建設促進法に基づいて、埼玉県の新市町村建設計画の一般的調整基準等により、昭和三十六年一月に宮代町新町建設計画基本計画書(昭和三十五年度~昭和四十四年度)が埼玉県知事あて提出された。また、同年実施計画書も作成されている。
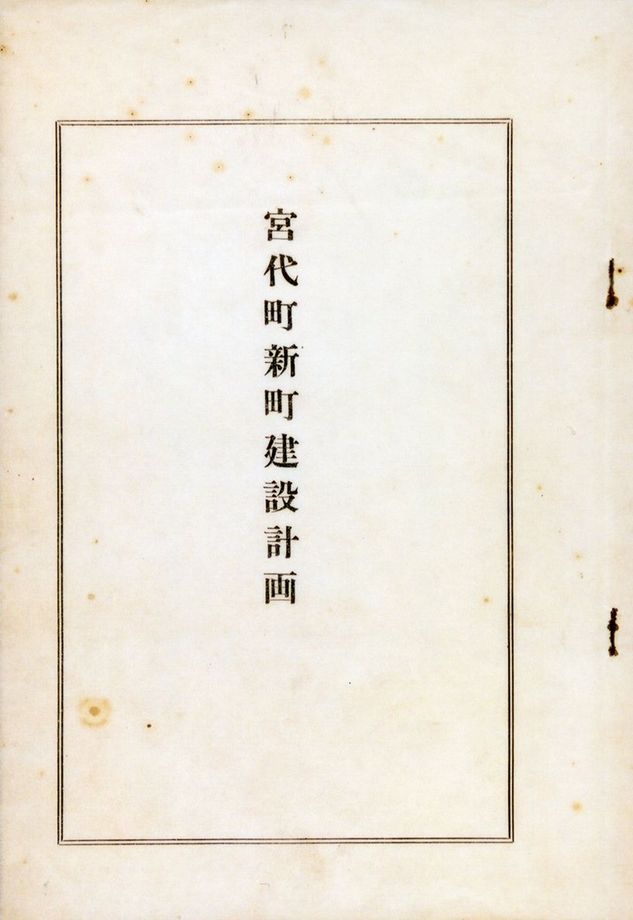
4-116 宮代町新町建設計画
これによると、基本的構想として、
一、人口・所得及び生活水準の向上に関する構想
二、立地条件の整備及び産業振興に関する構想
三、道路その他土木、交通輸送及び通信施設の整備に関する構想
四、教育文化及び厚生に関する構想
五、財政運営の合理化に関する構想
の五つを柱として、生産及び所得計画、農業計画、畜産計画、商工計画、道路、橋梁計画、教育、文化計画、厚生計画、行財政機構の合理化計画の八項目の重点施策を掲げ、新たな町づくりへの取り組みが始まった。
合併当初、旧百間村役場(現西原保育園)を町役場として使用し、旧須賀村役場(現和戸公民館)を支所として使っていたが、昭和三十五年鉄筋コンクリート二階建てによる待望の宮代町役場が現在の地に完成した。
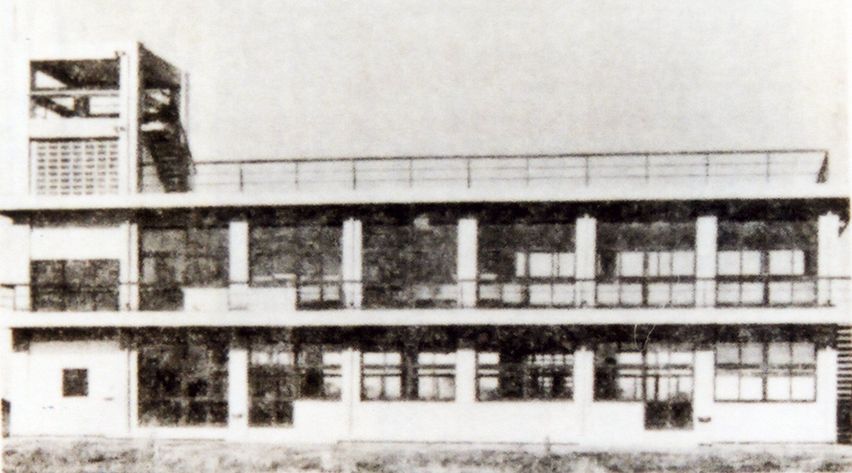
4-117 新設された宮代町役場
また、昭和三十六年六月には上水道が完成し、給水が開始された。「水は天からのもらい水」というように豊富な地下水に恵まれた当地では素掘りによる井戸を用いており、当時一七二八か所の井戸があった。しかし、都市化により井戸の枯渇、水質環境の悪化などの状況から上水道が設置された。当初給水戸数約一五〇〇戸で全戸数の七八パーセントを数えた。その後、人口の増加に伴ない浄水場等の施設が次第に整備され、昭和五十六年には県営水道の受水が始まった。さらに、昭和三十七年には久喜、宮代両町による久喜・宮代衛生組合が発足し、し尿処理場が完成し、昭和三十九年にはごみ焼却施設も稼動し、本格的な衛生施設として完成を見たのであった。また、昭和三十八年には町内の放送施設として有線放送が開通した。加入戸数約一二〇〇戸で、当時通話料は一通話三円の呼び出し電話であった。昭和四十九年に自動化されたが、一般電話の普及により昭和六十年に廃止された。
一方、教育施設では昭和三十六年百間中学校体育館完成、三十七年須賀小学校改築、三十八年東小学校増築、百間小学校改築、昭和三十九年百間中学校、須賀中学校増築など子供の増加による学校施設の整備が図られた。
こうして、町民の生活により密着したところからまちづくりが始められた。