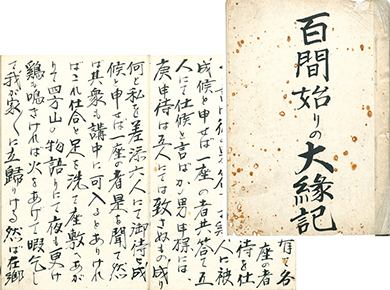1
1(昭和十四年写本)
百間始まりの大縁記
 2
2一.抑百間の始まりのいはれを詳しく
たづぬるに、其頃浪人五.六人着たり
て寺村東神外より西神外の間に
百姓五.六軒立居ける。或時五人
集まりて庚申待を致し居ければ明
方たれ共知らず四拾ばかりの男一人
立寄て申様には、是は何故有て各
 3
3々様方集りたもうやと云う。一座の者
共答て申には今夜は庚申待を仕
ると言えば彼の男答てお幾人に被
成候と申せば一座の者共答えて五
人にて仕候と言ばかの男申様には、
庚申待は五人にて致さぬもの成り
何と私を差添え六人にて御待に成
候とへと申せば一座の者是を聞て然
ば其衆も講中に可入るとありけれ
ばこれ仕合と足を洗て座敷へあが
りて四方山の物語りにて夜も更け
鶏も鳴きければ火をあげて暇乞いし
て我が家々に立帰りける。然ば在郷
の事なれば廻り宿に致しければ彼
 4
4の男の當番にあたりければ其日暮
方に講中の者を迎に来りければ
所の者申様には其衆は何国の
者なると申せば彼の男答へて私は
龍宮の者と言ふ それより彼方此方
を呼び集めて行きける下の谷より逆
井まで続き入ると思ひ五人の者共
彼の男に問い入りける あれは何様
なりと申せばあれは私の屋敷に御
座候と言えばさてさて扨々良き御林なりと
言うて其れより二、三丁あがりて長屋
門有り門より内へ入りければ御地の老
人七八人袴羽織にて下座平らに禮
をのべて玄関に入りそれより屋敷
 5
5案内致され扨座に付煙草盆
を出し茶菓子を出し茶を出して
亭主言ふ様は各々様方は
始てお出で被成候へば座敷を御覧な
されと言ふて先ず大廣き御座敷
に入りにける満々たる座敷なるゆえ
五人の者問ひけるは畳何畳敷
に御座候と言ふ 亭主答へて是
は千畳敷なりと云ふ 次の間を御
覧なされと言ふ 次の間へ入り是は
何畳敷に御座候と申せば是は五
百畳敷きなりと云う 其他間敷余程
多く茶の間料理の間台所なり 然に
一人勝手へ行きけるに何やら十二三の
 6
6娘のようなるものを菰に包み料理の間へ持
参して云ふ様は、先づ此れを料るべし
と云ふ 右の男これを見て座敷へ
立かへり此の由を右五人の者へ話
し確に十二三の娘なり 必ず食べ申
間敷と相談いたし 扨それよ
り吸肴にてあいのおさいのと云ふて数
盃頂きそれより膳を出し二の膳に
て扣る者も有り 其中に一人是は国
へ帰りて話の種にいただき申と言い
ければ鼻紙の間に入れそれより御膳を
さげければ又四方山の物語りて夜も
更け鶏も鳴きければ火をあけて帰
ると言ふ 亭主聞て今夜暇乞して
 7
7亭主又尼沼道まで見送りて
暇乞して立分れ 我が家々にたち
かへる。明朝八兵衛が妻に向て
言ふやうは鼻紙に入たるものは知らぬ
かと言へば女房我ぞんじたかと言
ふ 其頃は八兵衛が娘三才になる
八兵衛言ふ様は此の子たべたかも知
れず 然るに此娘鼻紙に入置人魚
食べる頃は人皇四拾六代孝謙天皇
の御代天平十三年秋の末方行基
菩薩此所に修行に来りければ道
辻にて八十ばかりの老人に出合かの老
人行基菩薩に向いて頼みけるは
御僧見掛けて頼度事あり 此所
 8
8は都に遠し 志ゆけんほふづの所なり
何卒弥陀を刻みて御堂を建立
頼入候 とう出来候はば御苦労
ながら薬師を五社権現に勧請し
て賜れば我此所の守神にたつべし
かえすがえすも頼入るとかき消ように風
吹きたもふ 依て行基菩薩が弥陀
を刻始め然るに八兵衛が娘五六才
になりける 毎日此所へ来て邪魔に
なる 行基菩薩此娘に向かひて言うや
ふは 如何に娘我が来ては此佛成就
せぬ程に明日より来るべからず我は此
方の言うことを聞かば我を明は辯財天
と勧請して得さずべしと言いければ
 9
9此娘聞き分けて不来 然るに逆井
原若狭の船着にて船頭共が原へ
井戸を掘て置と云う 昔は此所を
若狭井戸とす 其後は人々逆井
逆井といいならし明て此所へ大船
着ければ子供二三人来りて遊び
けるが八兵衛が娘六七才に成けれ共
船の舳先へ行とばをかむりて伏けれ
共船頭共知らずして船を出しければ
帆をあげ乗出し暫時が間に三四拾里
乗ければ彼の娘起きて出る 船頭共
是を見てやれ娘が居ると言共出船成
しは止る事を得ず 先若狭国小濱町
に着ければ近所に子持たずの者是を
 10
10聞いて養子に貰い度由様々に所望す
故養子に遣しける然るに此娘だけ長
じて八百年の齢を保っと云う 若狭国
小濱町に八百姫と祭るなり 竜宮より
持来せし人魚を食したる故なり
然るに行基菩薩弥陀を刻て老
人を五社大権現と勧請致し八兵
衛が娘を弁才天と勧請して所
の者を集めて行基菩薩言う様
は村名は何と言ふを問へば百姓共
村名は未だ無くと云う 行基菩
薩又問へば然ば村境より村境ま
でさほを入れて見よふと言いければ畏
い候と百姓共立合東神外の祓より
 11
11西神外の祓まで百間あり 此由を行
基菩薩へ話しければ行基菩薩
聞届け 然ば今日より村名を百間村
と御申候と言ふ 扨行基菩薩弥陀
は成就致けれ共堂建立難成と言ふ
故常陸国へ立かへり其頃は常陸国
は安部の仲丸殿の御知行にて行基
菩薩は元仲丸殿の菩提寺なる故
に菩薩は仲丸殿へ合て言ふ様は私
修行の先にて老人に頼まれ弥陀を刻
置候が堂建立難成に付何卒堂
建立頼入と言いければ仲丸殿きき届
如何にも建立可致と御普請奉行と
して鈴木日向守忠勝 島村出羽
 12
12守直政両人百間に到着す 其頃は
天平十五年になり弥陀堂出来其年
仲丸殿は禁帝より勅上にて遣唐使
をも仰付る 同勢数多召連て唐へ出
船して唐に着ければ旅宿して明日大
王の御前に出ければ碁将棋双六金
玉の石にて廻り一番を付て仲丸殿の前
に出しけれ共日本に無き事なれば知らず 依て
碁将棋にてせめ殺さる故御家絶断
依て鈴木島村帰らずして百間に住居
す 其後亦きびの大臣へ遣唐使も仰
付数多召連れて唐へ出船して無
事唐に着きければ旅宿致して休みける
然るに其夜仲丸殿の亡魂現れ出る
 13
13そして申様には某仲丸なり 我も碁将
棋双六を以て征め殺されしなり 貴殿
も明日は碁将ギ双六を以て征められる由
今夜はけいこ可被成と碁将棋双六を
教へける 明る日大王の御前に出ければ
案の定碁将棋双六を出しけれ共
きびの大臣は夜中稽古致し
ければ少しも怯へることなく大王あ
きれて言ふようは名僧を呼び出
し何卒六ヶ敷書を作りて可差出
と申付る 其夜又仲丸殿の亡魂現
れ出て言様は碁将棋はおしえたが
明日は唐で二人となき名僧の作り
たる詩を書くと言ふ 是は我が力
 14
14も不及 其許の常々念づる神佛を頼
べしと云いて消にける さればきびの
大臣は日々に大和の国初瀬寺
の観音いのる誓をかけ頼にける其夜
お告げあり 明日其書差出候共
日の出を待つべし 我等雲に変化
落つべし 雲の落たる所より讀始
めとかく雲歩きに委せとの御告なり
きびの大臣雲歩きにまかせ讀たり
依而きびの大臣日本へ帰り碁将棋
双六を始めけり 然に弥陀堂は金谷
原の西の方を海老の嶋の浦に弥陀
が原と言ふ所に建たせたもハ実に
大同元年に西光院建立す 同
 15
15彌陀堂を前に引て西光院の
本堂とす 弥陀堂の跡を出堂
が原と云ふ 寛永元年に西光
院焼ける其灰を山崎へ埋めて
これを經塚と言ふ 同三年に建立す
弥陀堂の浦(裏)に雷電あり 百間
始りの惣社なり實に岩槻城主
太田道灌なり 然るに北條相模
守氏直 岩槻を征めんとて 大手の
大将は宮の下に陣を敷 搦手の大
将は花泉台に陣を敷 然るに岩
槻の用から浦は新川扣 其の内に
うたり沼有て裏より入る事難成
故大手ばかり強く固め大手の口より
 16
16強く征めけれ共かまはず 然るに雜
兵共沼へ身を投ける 體にして水
底の橋を渡る北條方は華泉台
に矢倉を建て遠眼鏡にて城の要
害を見る目の下に見えるに依て水
底の引橋有る事を見出し一騎当
千の者共騎馬にて荒川を我先にと
乘り抜け抜け打渡り実に鎌倉おう
ぎがやつ上杉彈正定政方より加
勢に来る由を聞ければ是にては叶ふ
間敷と思ひ百間雷電へ祈誓を
なしければのふ志ゆ落て東海道は雷
電にて二日大雨降ると云ふ満水に留
られて遂に二三日逗留する内に北條
 17
17方は裏より乱入底橋を渡りて暫
時加間に討ち落す 道灌叶はすし
て江戸へ逃け行く 北條相模守
殿恐悦あって諸願成就なれはとて
百間雷電へ五拾石の殊印を付
三尺四方の鰐口を納める今は西光
院の宝物なり 其後代々殊印
御書替の時 寺の殊印になほす
其の後に十二坊を立る故にあざ名
を寺村と言なり 昔諸役重く廻
状を数度参らし 名主相談の上
村名を百間村と後宿へ譲りしなり。
明治六癸酉年二月写せしを
 18
18昭和十四巳卯年七月再写す
天平十三年より明治六年
まで凡千百三十三年なりと
本年迄千百九十九年なり