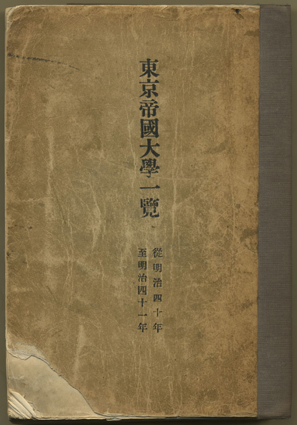これまでご紹介してきたとおり、島村家は江戸時代の初期から百間中村の名主を勤めた家でした。
島村家に遺された古文書の中には、名主をしていた当主が苗字帯刀を許された文書の「苗字帯刀免許状」や「苗字帯刀下知書」などがあり、また、「中小姓格仰付状」や「取締徒士格仰付状」などがあります。また、「明十一日九ツ半麻上下着用御役所江罷出候」と書かれた古文書もあります。麻上下とは、武士が出勤する際の定番の服装です。
これらのことから、当主の身分が武士として扱われていたことがわかります。
このような島村家の長男として盛助が生まれたのは、明治十七年八月九日のことでした。盛助の母は津ねといい、越谷の能楽師の家系の出身だそうです。
盛助には弟が二人、妹が四人いました。末の妹は、盛助が山形に赴任した後を追いかけるようにして山形へ行き、教師として英語を教えていたそうです。
盛助は地元の小学校を卒業すると、旧制浦和中学校、第一高等学校、東京帝国大学へと進みます。その過程のなかで、英語とのかかわりを深めていくようですが、そのきっかけが何であったのかはわかっていません。
中学から高等学校、帝国大学へと進む中で、腰に弁当を下げての中学通学は「裕福な家の長男が何故?自分で働くことを考える必要もないだろうに。」と、言う人もいたそうです。晩年の盛助が語ったところによると、世の中が新しく変わっていく中で、生家のように持っている土地から小作料が納められるなど、自らの手で稼ぐことの無いままに生活を送る世の中はいつか終わるだろう。いつかは自分の手で働いて稼ぐ時代がやってくるだろうから、学問を修めたのだといっていたそうです。
その後の社会の変貌を考えると、盛助には先見の明があったといえるかもしれませんね。
盛助が旧制浦和中学校に入学したのは、開校まもない明治三十年のことで、第三回生としてでした。
学生時代の盛助がどのようであったのか、知ることのできる資料はなかなかありません。百年近くも前の話ですから、本人が書いたものなどが見つからない限り、詳しく知ることは大変難しいことです。幸いなことに、現在のところ唯一といえる貴重な資料が、埼玉県立浦和図書館が所蔵する地域史料の中にありました。旧制浦和中学校の関係資料の中にあるそれは、「昔の話」という題で、盛助が中学校時代の思い出を記しているものです。その一文をご紹介します。(原文の旧漢字や旧かなづかいは、読みやすく改めました。)
「浦和中学時代の昔話を書いてくれという御依賴ですが何か思い出して書いてみようと思います。私が入学したのは明治三十年です。(中略)鹿島台の旧校舍もまだ開校して間もないことなので渋塗りの色も新らしく堂々と聳(そび)えていました。すくなくも当時の少年の私の眼にはそう映じたのでした。(中略)入学するとすぐ寄宿舍にはいりました。当時の寄宿舍は万事軍隊式になっていました。私は開校二年目に入学したのですから寄宿舍に、前年入学した三年生と二年生の先輩がいるわけです。(中略)部屋の掃除や何かは皆新入生がやるのですし、少しでも旧入生の御機嫌を損ずると恐ろしい顏を見せられたものでした。尤(もっと)も今から考えてもこんな事は当然の事のようにも思われるのですが、それにしてもなかなか猛烈なものではありました。
当時すでに野球はやりました。然しその頃の事ですから、クラブやミットなどは殆んど無いのです。今日の皮革の統制なぞあの時分だったら平気だったでしょう。プレーヤーは主として寄宿舍でした。水兵のシャツのように頭からかぶる白小倉の半袖のシャツの胸のところにDの字を黒羅紗(くろらしゃ)で切りぬいてぬいつけてあるのが、今日でいうユニフォームなのです。Dというのはdormitoryの頭文字で、この英語が寄宿舍という意味になっていたのです。ゴロを取りそこねるとシャツの中へ球がころげ込むほど胸のところが大きく開いていました。そして紺の脚袢に足袋跣足(たびせんそく)で神奈川あたりへ試合に出かけたのですから相当な心臟のチームであったことは確かです。但し試合に勝った記憶一つもないところを見ると技倆(ぎりょう)はさほどのものではなかったようです。(下略)」
寄宿舎での生活の様子がうかがえ、また、大変な野球好きであったその始まりが中学時代であることが、この文から推察することができますね。
明治三十六年七月に旧制浦和中学校を卒業したのち、盛助は旧制第一高等学校大学予科第一部(以下「一高」とします。)に入学します。同年九月のことでした。
当時の一高は、東京帝国大学予備門として成立した歴史から、帝国大学に入るための準備校のような位置づけでした。そのために、全国の高等学校の首位に位置し、その入学試験は最も難関とされていたそうです。
一高では、寄宿舎への全生徒入寮制が採用されていたため、盛助は現在の東京都文京区本郷にあった一高の寮で過ごしていたものと思われます。寮では「ろう城自治」と呼ばれる訓育方針がとられたことから、学生自治を尊ぶ一高独自の校風が形成されました。
そして、この一高での学生生活においては、盛助の生涯の中で考え方や生き方などへの影響を与えた恩師や友人との出会いもありました。
まずは夏目漱石です。漱石は盛助が入学する年の四月から、一高と旧制東京帝国大学(以下「東京帝大」とします。)において講師として教鞭をふるいました。漱石と盛助が教師と学生という関係でいる期間は、盛助の一高入学から、漱石が一切の教職を辞した明治四十年二月までなので、約三年間といえるでしょう。漱石とはその後もなにかと縁が続いていたようですが、その話はまた別の機会に譲りたいと思います。
一高の先輩としては、夏目漱石の門下生と呼ばれる小宮豊隆、阿部次郎、野上豊一郎のほか、岩波書店の創設者である岩波茂雄や、のちに旧制山形高等学校での同僚となる吹田順助がいました。
また、同級生として卒業をした人には、戦後の文部大臣や学習院院長を勤めた安倍能成や、俳人の富安風生(謙次)、木下杢太郎(太田政雄)、宮本和吉などがいます。
後輩には谷崎潤一郎がいますが、どのくらいの親交があったかは、いまのところわかっていません。
写真は、一高時代の集合写真です。かなりわかりづらいですが、上から二段目の一番左の人物が盛助です。同じく上から二段目の中央あたりにいる、頭一つ分抜き出ているのが安倍能成です。後の回で取り上げますが、安倍は晩年の盛助を訪ねて、何度も宮代の地に訪れていることが地元に伝わっています。
(前号引用文中の「dormiloly」は「dormitory」の誤りでした。お詫びし訂正いたします。)
盛助が東京帝国大学文科大学(以下、「帝大」とします。)に入学したのは明治三十九年九月のことでした。
残念なことに、帝大時代の盛助について知ることのできる資料もあまり見つかっていません。現在のところ、「帝国文学」及び「東京帝国大学一覧」という二種類の書籍に掲載されていることがわかっています。
「帝国文学」は、帝大の教官、卒業生、在校生によって明治二十七年に結成された、帝国文学会の機関誌として発行されました。盛助は在学中に戯曲の翻訳を発表、卒業後もいくつかの作品を発表しています。これらの作品の紹介については、後の回で取り上げます。
「東京帝国大学一覧」(以下、「一覧」とします。)は、学校総覧みたいな内容の書籍で、校則や教員一覧、在校生名簿、卒業生名簿ほかの情報が掲載され、基本的には毎年発行されています。
今回は、盛助が帝大二年生となった、明治四十年十二月に発行された一覧に掲載された在校生名簿から、盛助や同級生たちについてご紹介します。
旧制第一高等学校(以下、「一高」とします。)から一緒に卒業した同級生たちは、それぞれの専門へと分かれました。
木下杢太郎(太田政雄)は医科へ進み、皮膚科の専門医となりました。富安風生(謙次)は法科に進み、逓信次官を勤めたのち、俳人として活躍しました。
盛助が進んだのは文学科でした。一高からの同級生としては、英語学者の市河三喜がいました。また、旧制第三高等学校や第五高等学校などを卒業し、帝大で同級生となった人には、小野秀雄、田中秀央、下村湖人(内田虎六郎)、さらに学習院高等科からの同級生には、正親町公和、木下利玄、志賀直哉などがいました。
また同じ文科でも、安倍能成や宮本和吉らは哲学科に進みました。この哲学科の同学年には、学習院高等学科を卒業した武者小路実篤もいました。
在校生あるいは卒業生の名簿をみていると、さまざまな分野において近現代の日本を支えた人々の名を見つけることができます。その一人に盛助の名があることに、感動される方も少なくはないでしょう。
東京帝国大学(以下、「帝大」とします。)の文科に入学した盛助は、文学科においてイギリス文学を学びました。
この頃にはすでに、作家になりたいという希望があったのでしょうか。帝大の文科で発行していた雑誌である「帝国文学」に、『精神の眼』という喜劇の戯曲を発表しています。主人公である男女の結婚をテーマに書かれたこの戯曲は、「帝国文学」第十四巻第七・八・十号にわたって掲載されています。この戯曲を発表したとき、盛助はペンネームを「島村苳村」としています。しかし以降は、「島村苳三」となりますが、理由は不明です。
明治四十二年七月、盛助は帝大を卒業します。この卒業証書授与式は天皇陛下が臨席されたようです。「卒業証書授与人名」という名簿をみると、「英吉利文学受験」の項目に盛助の名が見られますので、卒業試験を受けた専攻がイギリス文学であったことが確認できます。
帝大を卒業してからの盛助は何をしていたのでしょうか。卒業直後からしばらくの間は、不明です。調査が至っていないせいもあるかもしれませんが、作品の掲載された雑誌が見つかっていません。明治四十三年三月刊行の「帝国文学」第十六巻第三号に、ロシアの作家であるメレジュコフスキー原作の『ジュリアンの最後』が掲載されているところをみると、翻訳に集中していたのかもしれません。
盛助はこの『ジュリアンの最後』を始めとして、小説や翻訳(メレジュコフスキー原作のもの)を発表していきます。そして、明治四十四年四月二十八日から六月六日までの四十日間にわたり、読売新聞に小説「貝殻」を連載しました。この連載小説は後日、春陽堂から「現代文藝叢書第十三編」として刊行されました。