これについて、山崎謙という人が、およそ次のようなことをいっているので、先ずそれを見ると、「将門記を記した人は、将門にゆかりのあった大木の僧侶で、この人が守谷の大木山連乗院に入山して、そこで書いたものであろう。本来ならば、将門が開山したといわれる筒戸の禅福寺で書きたかったのであるが、そこでは書けない事情があった。禅福寺は最初は真福寺といっていたが、将門敗死の後一度廃寺となり、その後名前を変えて、禅福寺と称して復興した。註(6)」と述べてある。
このことを傍証する資料はあまり残されていないが、偶然にも『将門記』の古写本というのが、名古屋市(当時の美濃国大須村)の真福寺に伝わっていることが判明した。美濃の真福寺と筒戸の真福寺(現在の禅福寺)とは、何等かの関連性があったものと考えられるが、このことは、一応、注目に値することである。将門の創建したといわれる筒戸の真福寺は、将門の敗死後廃寺となり、その後しばらくして禅福寺と名称を変えて復興したが、そのことについては、それなりの事情があったものであろう。もちろん、『将門記』は禅福寺では書けず、大木山で書かれたが、大木山には将門七人の影武者の死屍が葬ってあり、御霊山と称するところであった。
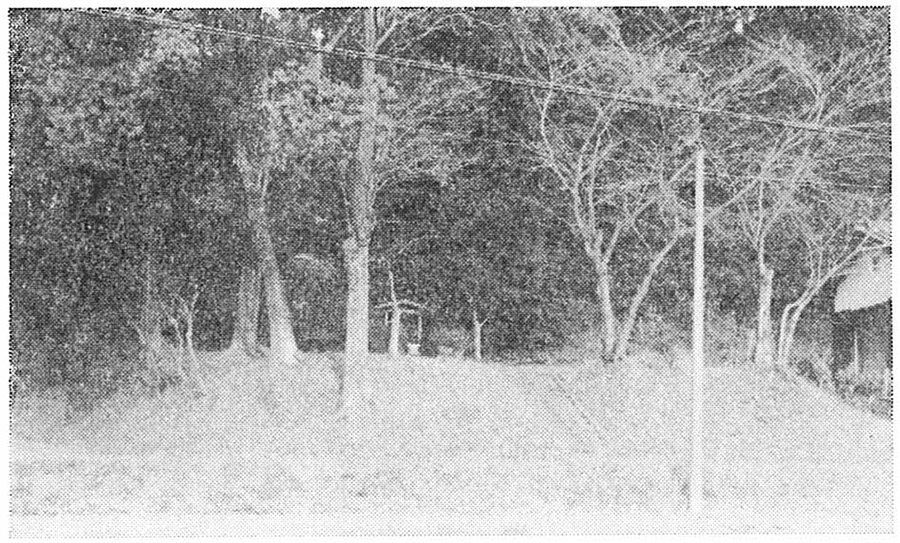
大木霊山入口
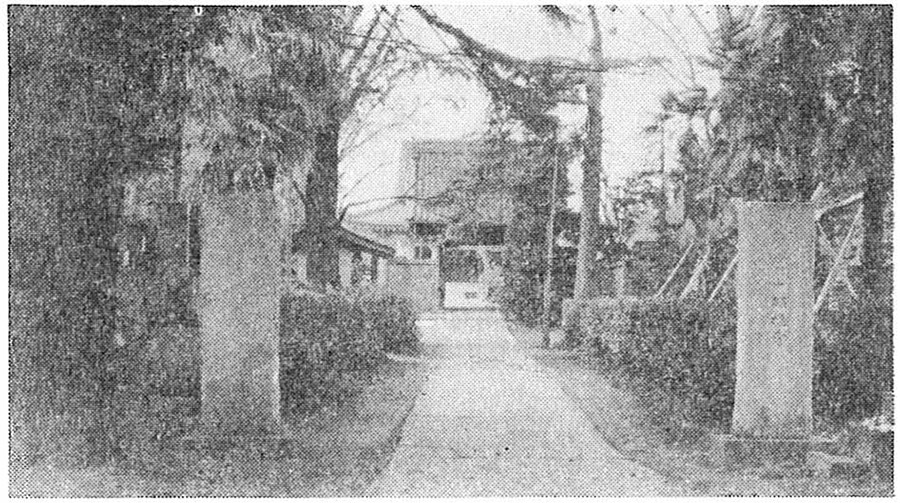
禅福寺
なお、『将門記』の前半の記述内容をみると、将門に同情的でないような場面もでてくるが、当時の情勢から判断して、そのように書かざるを得ない事情が存したものであろう。