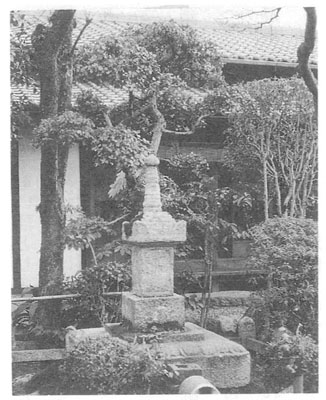横田河原の合戦で勝利を得た義仲ではあったが、史料の欠落もあって、その後は一年以上も動静が不明である。この間のできごととして、「養和の飢饉(ききん)」が全国を襲ったことが知られ、こうした深刻な事態が兵を動かすことをためらわせた理由とも考えられるが、これとは別に義仲は重大な局面に立たされていた。それは、このころ、頼朝と不和になった二人の叔父があいついで義仲を頼ってきたことに関係している。以仁(もちひと)王の令旨(りょうじ)を伝達した功労者の新宮行家と、下野(しもつけ)国(栃木県)の足利俊綱と組んで蜂起(ほうき)したあげく、頼朝に敗北した常陸(ひたち)国(茨城県)の志太(しだ)義広(本名は義憲)である。
とりわけ最初から頼朝に敵対していた志太義広を義仲がかくまったことが原因で、これまでもしっくりいっていなかった義仲と頼朝との関係はいっきょに悪化した。頼朝が新宮行家の引き渡しを求めたのにたいして、義仲がこれを拒否したことは『平家物語』諸本にみえているが、義広についても同様であったらしいことは、のちに義広が義仲とともに北陸道を進軍して入京している事実からうかがえる。このため、延慶本の『平家物語』によると、寿永二年(一一八三)三月、頼朝は義仲追討のために十万余騎の軍勢を率いて碓氷峠を越え、信濃国の「樟佐川」まですすんだとあり、覚一本などの流布本では、頼朝軍に追われた義仲軍が信濃国境の熊坂(くまさか)山(信濃町)に陣取り、頼朝軍は善光寺までいたったとある。これらの話がどこまで信頼できるか疑問もあるが、両者がこの時点で一触即発の危機にあったことは確かだろう。この危機はけっきょく、義仲が嫡子の清水冠者義重(延慶本などでは義基とする)を頼朝のもとに人質として差しだすという、義仲の譲歩によって回避されることになった。
こうして、鎌倉の頼朝との一時的な和議が成立したことにより、義仲は寿永二年(一一八三)の三月以降、北陸道から京に向かって進撃を開始し、越中(富山県)・加賀(石川)国境の倶利伽羅(くりから)峠の戦い(「砺波山(となみやま)の戦い」ともいう)などで平氏軍に大勝を重ねつつ、同年七月ついに入京を果たしている。
この間、一人の興味深い人物が義仲のもとにしたがっていた。義仲の祐筆(ゆうひつ)を勤め、倶利伽羅峠のふもとにある埴生(はにゅう)護王八幡宮(富山具小矢部(おやべ)市)や加賀・越前(福井県)・美濃(岐阜県)の三馬場(ばんば)の白山妙理権現(石川県鶴来町の白山比咩(しらやまひめ)神社、福井県勝山市の平泉寺白山神社、岐阜県郡上(ぐじょう)郡白鳥町の白山長滝神社)に捧げた、願文を執筆した大夫房覚明(かくみょう)である。『平家物語』諸本によれば、覚明は俗名を藤原道広といい、蔵人(くろうど)などを歴任したのち、奈良の興福寺で出家して最乗坊信救と名乗り、各地を遍歴したあと、新宮行家の推挙で義仲に仕えるようになって、さらに名を覚明とあらためたとある。かれはやがて義仲から離れ、その後の消息はかならずしも確かではないが、後世、京都の大谷本願寺や長野市篠ノ井塩崎にある康楽寺の縁起では、じつは海野幸親の子で、その後半生は親鸞(しんらん)の弟子となって、小県郡海野荘白鳥に康楽寺(戦国期に塩崎に移転したとされる)を創建した西仏(さいぶつ)として登場する。これは、伝承の域をでないが、唱導文芸の発展する過程を知るうえでは注目されるエピソードであろう。
こうして平氏を追い落として入京した義仲ではあったが、その栄光は長くはつづかず、以仁王の遺児北陸宮を擁立しようとした宮廷工作は失敗に終わり、配下の軍勢が乱暴狼藉(ろうぜき)を繰りかえしてひんしゅくを買うなど、むしろ最初から挫折の連続であったといってもよい。加えて、あくまでも源氏の主導権をにぎろうとした頼朝との対立がふたたび表面化し、頼朝と後白河法皇を中心とする公家社会の複雑な駆け引きのなかで、しだいに孤立化を深めていった。寿永二年十一月、法皇の御所である法住寺殿を襲撃するという挙にでた義仲は、翌元暦(げんりゃく)元年(一一八四)一月、強圧的な手段で征夷(せいい)大将軍に任ぜられたが、それもつかの間、頼朝の意をうけた義経(よしつね)・範頼(のりより)の軍勢を前に、ついに都落ちを余儀なくされ、平氏打倒の目的を達しえぬまま近江粟津(あわず)(滋賀県大津市)で敗死したのであった。ここで、以仁王の令旨発布に始まり、木曾義仲の旗揚げから没落、さらに平家滅亡と頼朝政権の樹立にいたる、いわゆる源平内乱期の全過程をとおして、長野市域を中心とする北信濃の武士たちがどのような行動をとったかを整理しておこう。
北信濃の武士の去就(きょしゅう)を、要約すればおおよそつぎのようになろう。第一に当初は旗色を鮮明にするものが少なく、村山義直や戸隠別当の栗田範覚(寛覚)の動きはむしろ異端的であり、井上氏と村上氏の主流が従軍するのは、東信の武士団の大半がしたがった横田河原の合戦からとみられること、第二に、中小武士層の全体的傾向として、当初はどちらかといえば、平氏方についたものが目立つこと、第三に、平氏方についた武士、源氏方についた武士のいずれの場合にも、一族中には敵・味方に分かれるものが出た例がしばしばみられたこと、などである。さらに付け加えれば、義仲存命中に頼朝にもよしみを通じたり、さらには義仲にそむいたりするものが多く出ており、そのことが、井上光盛のように粛正された例外を除いて、義仲敗死後も最終的には鎌倉幕府の御家人として生きのびる道につなかったと推測できる点があげられる。もっとも、この点は北信濃の武士だけに限ったことではなかったといえる。