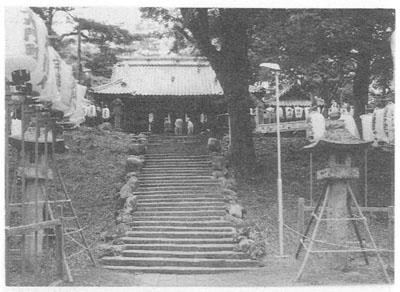地方における代表的な神社として、古代には九世紀はじめに編さんされた『延喜式(えんぎしき)』に神名が記載された官社があったが(第一編第三章第三節)、平安後期以降、史料上にほとんどみられなくなる。その理由としては、むろん文献史料の欠如にもよるが、神社そのものがさまざまな変質をとげたことも大きな要因である。
そもそも官社とは、神祇官(じんぎかん)の名簿に登録され、祈年祭(としごいのまつり)などに国家から奉幣をうけた神、いわば国家的祭祀(さいし)の対象となっていた特別の神社であったから、律令国家の衰退とともに、その性格は変化するのも当然であろう。とくに、官社に列したのは、霊験あらたかであるといったような理由が多く、その選定には郡司(ぐんじ)などの地方豪族の報告や申請にもとづくのが一般的であったから、官社の支持基盤となっていた郡司層の没落や在地状勢の変化は、それまでの官社のありかたを根本的に揺るがすこととなった。中世まで命脈を保つことのできた官社も、鎌倉時代までにはその大部分がほんらいの神(社)号が変わってしまったりするなど、性格や存在形態になんらかの変化が生じている。長野市およびその周辺の事例をもとに、こうした点を具体的にみておこう。
健御名方富命彦神別(たけみなかたとみのみことひこかみわけ)神社は、『延喜式』によれば、水内郡では唯一「大」の神(官社で大小の区別は班幣(はんぺい)のさいの幣帛(へいはく)の量の違いによる)を祀(まつ)る神社であったが、鎌倉時代にはその正確な鎮座地さえ忘れ去られていた。室町幕府の公事(くじ)奉行人を勤めていた小坂(諏訪)円忠(えんちゅう)は、延文(えんぶん)元年(一三五六)に『諏方大明神画詞(えことば)』を著したが、そのなかで、当時善光寺境内に所在し「南宮社」ともよばれていた「善光寺別社」が、当社のことではないかと考証している。この記事は『延喜式』所載の神社の現地比定としては、もっとも古い事例のひとつとして注目されるものである。当社が諏方郡の建御名方富命(彦)神社(『延喜式』では「南方刀美(みなかたとみ)神社」として所見)の分社(別社)であり、「南宮社」が南方刀美神社の略称とみられること、さらに水内郡の郡司を諏訪郡と同じ金刺氏(諏方郡の建御名方富命神社の神職でもあった)が勤めていた点から、水内郡家(ぐうけ)(長野市県町遺跡に比定される)に近い現在の善光寺周辺に、ほんらいの鎮座地を考定する見方は、こんにちからみてもかなり妥当性が高い説といえようが、これとて決定的な根拠は当時もなかったようで、あくまでも小坂円忠の憶測にすぎなかった。
現に、近世中期以降に起こる式内社顕彰運動の過程で、いくつかの神社が名乗りを上げたため、健御名方富命彦神別神社はこんにち、長野市城山、信州新町水内、飯山市豊田五束(ごそく)の三ヵ所にある。このうち、長野市の城山の一角に鎮座する健御名方富命彦神別神社は、近代になって、善光寺本堂裏にあった年神堂を南宮社の後身とみて、これを城山に移転して新たに社殿を建立したものである。
地方の神社は、荘園制の成立によってもいろいろな影響をうけている。荘園領主は現地の支配を円滑にすすめるために、荘内に鎮守を設けたが、これには新たに勧請される場合と、従来から在地にあった神社が荘園鎮守として取りこまれる場合とがあった。前者の例では、伊勢神宮の荘園内に勧請された神明(しんめい)社がよく知られ、長野市内にあった布施御厨(篠ノ井)・富部(とんべ)御厨(川中島町)などにも、当時すでに伊勢神宮と同じ造りの社殿の小社が建立されていた。石清水(いわしみず)八幡宮(寺)領の荘園鎮守は八幡宮と改称されて、別宮ともよばれている。長野市近辺では更級郡の小谷(おうな)郷(更埴市)が平安末期に石清水八幡宮(寺)の荘園となったため、郷内にふくまれていた武水別(たけみずわけ)神社(更埴市八幡)は文永四年(一二六七)までに「小谷別宮」とよばれるようになり(石清水文書)、さらに近世には「八幡宮」とも通称されていた。
このように、在地にあった神社の性格がまったく変えられてしまった要因として、ほかに山岳信仰の影響等によるものもある。加賀白山を発信地とする白山信仰は、遅くとも南北朝時代までに信濃にも流入していたが、小県郡の山家(やまが)神社(真田町長)はその神体山であった背後の四阿(あずまや)山が白山と一体とされたため、加賀白山の祭神と同じ菊理媛(ひめ)命を祀り、白山権現と称されていた。
神社名が変わっていた例としては妻科神社(長野市妻科)もあげられる。当社は嘉応(かおう)元年(一一六九)に藤原清輔(きよすけ)によって編さんされた『和歌初学抄』にすでに「つまなし社」と見え、また建久九年(一一九八)に成立した上覚の『和歌色葉』や、仁治三年(一二四二)以前の成立とされる順徳上皇の『八雲御抄』にも「つまなしのみや」とある。いずれも「すわの宮」のつぎに記されているため、『延喜式』に所載される妻科神社のことと考えられているのである。当社がこうした歌学書に見えているのは、いわゆる歌枕になっていたことを示すもので、延慶(えんきょう)三年(一三一〇)に藤原長清が編した『夫木(ふぼく)和歌集』に収められた、「草ふかき野口のもりのつまやしろ、こや花すヽきほに出(いず)る神」という権僧正公朝の歌は、当社のことを詠んだとみられる具体的な例である。この背景には、当社の鎮座地が水内郡の政治的中心地であった郡家(ぐうけ)と至近の距離にあり、また東山道が通過していたことなどが関係していたとみられるが、鎌倉時代当時の公家の歌は現地を直接訪れて詠んだものは少なく、大部分は歌会などで技巧を競って詠んだ一種の空想の産物であった。和歌の世界では当時、各地の名所旧跡の呼称が実態を離れ、ことばだけがひとり歩きしていたが、右の歌もそうした一例であろう。したがって、鎌倉時代の妻科神社が現地でじっさいに「つまなし」社とよばれていたかどうかは不明だが、一五世紀中ごろまでにはこの呼称が地元でも定着していた(『戸隠山顕光寺流記』)。『延喜式』の神名がこのころにはまったく忘れられていた事実を示している。