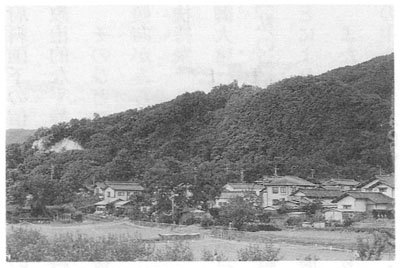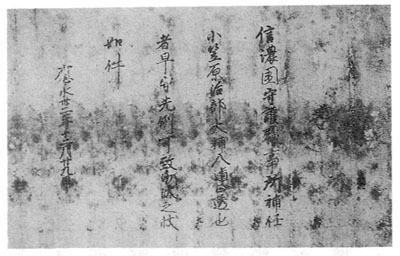大塔合戦終了後、村上氏と大文字一揆勢らは、幕府に守護小笠原長秀にかわる「清廉(せいれん)の御代官」(『信史』⑦『大塔物語』)の派遣を要請した。これにたいして幕府は、応永八年(一四〇一)二月、早急に在地の混乱を収拾する意味もあって、元信濃守護で、当時、幕府の宿老として高い声望を得ていた斯波義将(よしまさ)を再任した。義将は嶋田常栄(じょうえい)を守護代にして信濃に下向(げこう)させ、同年六月には、常栄に命じて高井郡中野郷内西条村(中野市)で生じていた所領の紛争解決にあたらせている。
須田・井上・市河各氏の所領が入りくむ西条村の地では、各氏が分割して支配をおこなっていた。このうち北信濃源氏の井上氏系武士である須田・井上・高梨氏らは結託(けったく)して、大塔合戦のさいに守護方に属していた市河頼房の領分を押領した。義将はこの押領行為を停止させ、その地を頼房に返付させることを守護代の常栄に命じている。守護の義将は国人領主の無秩序な領域拡大を抑制(よくせい)して、国人の所領支配を従前どおりの枠内に収まるように取りはからったのである。混乱した在地の秩序を沈静化し旧に復すためにとられたこの処置は、義将が守護に在職していた一年余りのあいだ、信濃国内を静謐(せいひつ)にさせるうえで効果があった。
翌応永九年五月、幕府は信濃国の守護を廃正し、将軍の支配が直接およぶ幕府料国とした。六月、幕府は信濃国内の実情を把握するために、右筆(ゆうひつ)方奉行人の依田左衛門大夫(よださえもんたいふ)と飯尾左近将監(いのおさこんしょうげん)を信濃に向かわせた。料国代官の先遣使となった「両使」(『信史』⑦『市河文書』)は、東大寺が知行する国衙(こくが)領正税(しょうぜい)年貢収納の実否調査にあたるよう命じられている。両使による信濃国内の実態調査が一段落した九月ころまでに、信濃国の代官には足利氏一門の細川慈忠(しげただ)が任命された。
幕府が信濃国を料国としたのは、応永九年ころから対立を深めてきた鎌倉御所の足利満兼に備えるために、鎌倉府の支配分国に接する信濃を、監視・牽制の政治的役割をになう国として必要としたところにあった。そのためには大塔合戦時に北信濃の国人領主たちにみられたような、守護権力を排除して自立性を強めていた国人武士を掌握し統制することは緊要(きんよう)なことであった。幕府はこのために、大文字一揆が示したような幕府に直結しようとする国人領主層の意向を積極的に汲(く)み入れ、これを直接掌握して強力に統治することを策したものと思われる。こうした幕府の方針にもとづく信濃の料国期間は、小笠原政康が応永三十二年(一四二五)に守護に就任するまでの二三年間の長さにわたった。
料国代官になった細川慈忠は、一貫して信濃守護方であったと自負する市河氏一門の市河氏貞(うじさだ)に迎えられて府中に入り、信濃国内を「如何(いか)にも取り静め」(『信史』⑦『市河文書』)るべく対応策をめぐらせた。応永十年の半ば、村上満信・大井光矩・伴野・井上・須田氏ら東・北信の国人が反抗を企てた。慈忠は氏貞らを率いて出陣し、更級郡壇原(だんばら)(川中島町段ノ原ヵ)、埴科郡生仁(なまに)城(更埴市)および更級郡塩崎新城(赤沢城とも、篠ノ井塩崎)に戦った。合戦が村上氏の勢力範囲で起きているところからみて、反抗の中心には村上氏が介在していたことが推察される。大塔合戦のときには直接戦闘に加わらなかった大井氏も参戦したほどに、反乱は大規模なものであった。
翌応永十一年秋には高井郡北部の高梨左馬助(さまのすけ)が上意にそむいたとして、細川慈忠はふたたび市河氏貞らを率いて奥郡(北信濃の水内・高井・埴科・更級四郡の総称)に発向し、水内郡内にある桐原(吉田桐原)、若槻(若槻)、下芋河(しもいもがわ)(三水村)などの高梨氏の支配する要害を攻め落とした。さらに慈忠は同郡の加佐(豊田村)、蓮(はちす)(飯山市)から、千曲川東岸の高井郡狩田(かりた)郷東条(小布施町)へと転戦してこれらを攻略し、高梨氏の本領地である橡原荘の足もとにまで迫(せま)る勢いを示した。
この連年にわたる出兵によって幕府代官の細川慈忠は、北信濃地域の国人層をほぼ制圧することができた。大塔合戦の場合とは相違して、この国人領主の反抗や敵対には「内々子細を触れ廻(めぐ)らし、おのおの同心せしめ」(『信史』⑦『大塔物語』)るという、国人相互間の組織だった協働性を欠いていたがために、幕府代官の武力平定を容易なものとし、国人側は敗退へと追いやられることになった。しょせん、国人らが大塔合戦のおりに「公方を忽緒(こっしょ)(なおざり)にし奉(たてまつ)るに非(あら)ず」(同前書)とて、幕府権力を尊重する姿勢をとっていた以上、その権力を直接体現する代官細川氏の支配にあらがうことはむずかしいところがあったといえよう。これ以後、応永二十二年(一四一五)に市河越中守を率いた幕府代官が、高井郡須田郷(須坂市)の須田為雄を追討した一件を除き、幕府料国下の信濃一円に国人の反抗は起きていない。信濃はしばしの政治的安定期を迎えたのである。このように政治的な平静さをみた幕府料国下の信濃では、一、二それを反映するような動静が見受けられた。
そのひとつは、幕府の直接統治をうけた国人領主が、幕府に直結することで領主支配の確保と発展につとめる傾向がみられたことである。応永三十年、幕府は鎌倉御所足利持氏(もちうじ)が幕府の鎌倉府監視のために組織した「京都扶持(ふち)衆」を討伐したさいに、小笠原政康に関東への出陣を命じたが、このとき高梨氏惣領家の朝秀(ともひで)は、「公方の御大事に依り、高梨方私の弓矢を閣(お)く」(『信史』⑦『小笠原文書』)との意向を幕府に伝えている。高梨朝秀は「私の弓矢」、すなわち、私戦による領域拡大を取りやめて、将軍に奉公を誓うという直接的な結びつきをもつことにより、領主支配権の進展をはかることに方針を転換したのである。
また、幕府権力の保護のもとに領主支配権の維持・確保を意図していた大文字一揆にたいしては、幕府は一揆の中心にいた仁科氏を安曇・筑摩両郡内の御料所(ごりょうしょ)(将軍家の直轄領)の代官に登用し、一揆の輩(ともがら)には将軍の直状(じきじょう)である御判(ごはん)御教書をもって、守護領であった安曇郡住吉荘や春近(はるちか)領の所々を宛(あ)て行(おこな)った。一揆は将軍家の所領給与の対象になるなど、あたかも将軍に直属する直勤御家人のように取り扱われている。幕府の直接的な統治を受け入れた国人武士には、所領の拡大があった実情をみることができる。
いまひとつは、この安定した政治状況のもとに、再生・復興の気運がきざしたことである。この時期信濃の各地では、社寺の復興が盛んにおこなわれている。応安三年(建徳元、一三七〇)に全焼した善光寺の再建事業も、その一例である。善光寺では至徳三年(元中三、一三八六)ころまでに本堂は再建されていたが、残されていた多宝塔が応永十四年(一四〇七)に、金堂が同二十年にとあいついで落成をみた。四〇年余りを費やした善光寺の復興であった。塔と金堂の落慶供養は、いずれも本寺の三井寺(みいでら)(園城寺(おんじょうじ)、滋賀県大津市)から下向して、善光寺正別当に就いた房誉(ぼうよ)を導師(どうし)にして執りおこなわれている。
他方、国人層によってその取り分を大幅に蚕食(さんしょく)されていた荘園領主の支配にも復旧がみられた。大文字一揆の成員が知行していた安曇郡住吉荘と、水内郡市村高田(いちむらたかだ)荘(芹田南市・北市、古牧上高田・南高田一帯)以下五ヵ荘の領家職は、中納言家の山科教言(やましなのりとき)が所持していた。応永十二、三年にかけて教言は、これらの荘園を管理する奉行に源清幸を据え、京都一条烏丸(からすま)に住む僧の建徳庵(けんとくあん)を年貢の請人(うけにん)にして、建徳庵と毎年一〇貫文の納入を請け負わせる契約を結んだ。同十三年から数年のあいた、教言は替銭屋(かえぜにや)による為替(かわし)を用いて銭納される領家得分の一〇貫文を手にすることができた。
その間、教言は年貢得分の皆済をはかるために、奉行の源清幸を建徳庵との交渉に出向かせたり、幕府右筆方奉行人の飯尾貞之(さだゆき)や斎藤玄輔(げんすけ)らのもとに遣わして、住吉荘などの知行安堵を得るための努力をかさねている。とくに応永十四年には、幕府代官の細川慈忠に、住吉荘などの五ヵ荘関係のことについてしたためた音信を送るところがあった。慈忠に依頼して、これらの荘園から年貢が徴収され、領家分の一〇貫文が確実に山科家に送付されるよう督促したものであろう。教言は幕府および現地に駐在する幕府代官の保護や支配力をうしろだてにすることによって、遠隔地に領有する荘園の弱小になりがちな荘務権を確保することができたのである。それは信濃が幕府料国となり政治的に安定をみたことに付随して、荘園領主にもたらされた余慶(よけい)でもあった。