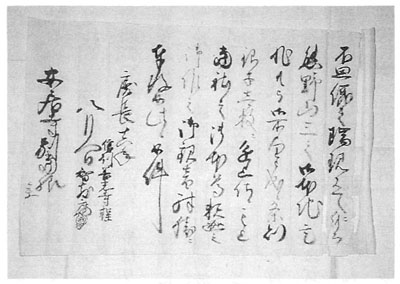このように、一四世紀末からの一〇〇年間の善光寺は、金堂を罹災するような大火を四回も経験し、その再建事業に明け暮れる日々であった。しかし、そのつど変わらぬ規模で再建が遂げられている点に、当時の善光寺信仰の強固な浸透ぶりをうかがうことができる。これらの造営事業の経過を通じて、一五世紀はじめごろまでは、なお近江三井寺(みいでら)(園城寺(おんじょうじ)、滋賀県大津市)の管領下にあったことがわかる。応安三年の火災ののち、応永十四年に多宝塔が、ついで同二十年に金堂が完成したことはさきに述べたが、そのいずれにも善光寺別当の房誉(ぼうよ)がはるばる本寺の三井寺から下向し、落慶供養の導師を勤めていた事実がその点を示している(『三井続灯記』)。房誉はその伝記によると、三井寺では探題・別当・大学頭(だいがくとう)などを歴任したことが知られ、当時、寺門派でも有力な学僧の一人であった。また、正長(しょうちょう)元年(一四二八)に没した通覚(つうかく)は善光寺のほか、宇治平等院(京都府宇治市)や紀伊粉河寺(こかわでら)(和歌山県那賀郡粉河町)の各別当職を歴任していたことが知られるが、これを最後に、三井寺関係の史料には、善光寺に関する記事がみえなくなる。おそらく、一五世紀半ばを境に、本寺である三井寺は、一二世紀ごろから保持してきた善光寺の管領権を失ったとみてよいだろう。この時期は、中央の本所や領家が遠隔地の荘園支配権をしだいに維持できなくなっていく時代であった。
これにかわって善光寺に進出したのは、国人領主の栗田氏であった。栗田氏は『尊卑分脈(そんぴぶんみゃく)』によると、北信濃第一の名族とされていた村上氏(清和源氏)と同族で、村上為国の子、寛覚(かんかく)が「栗田」を名乗った最初とある。第一章第一節で述べたように、栗田氏は平安末期以来、戸隠別当を輩出していたことが知られるが、一五世紀ころまでに、戸隠山に居住する「山栗田」と本貫地の水内郡栗田郷に拠(よ)る「里栗田」に分かれていたといわれている。「善光寺別当」と称して善光寺にたいする支配権を強めたのは、この里栗田の一族であった。といっても、栗田氏は依然、領主的性格が強く、法名と俗名の両方を有しており、また「堂主」などともよばれている点からして、じっさいにはいわゆる「俗別当」に当たるものとみたほうがよいだろう。栗田氏による善光寺支配は甲越合戦までつづいており、永禄(えいろく)元年(一五五八)武田信玄によって本尊や仏具が甲府に移されると、それにともなって甲斐国に移住した。このへんのことは、あとの「戦国武将と善光寺如来」のところでもふれる。
栗田氏が進出したのとほぼ同じころ、善光寺においては、再建事業にさいしての勧進(かんじん)形態にも変化が生じている。堂塔や社殿の修復・再建にさいして、必要な資金を調達するために人びとから寄付を募る活動に従事した勧進聖(ひじり)は、鎌倉時代から南北朝時代にかけては、修造のたびごとに主として禅律僧のなかから起用されるのがふつうで、第一章第二節でみたように善光寺についても同様であったが、一五世紀末から一六世紀初頭にかけての時期に、こうした中世的な勧進のありかたが変化して、「本願(ほんがん)」と称する宗教者が出現した。勧進と本願との大きな違いは、前者があくまでも臨時に設置された役職であるのにたいして、後者は特定の寺社に居住して、いわば専属の形で勧進行為に従事するようになったものである。本願は本願房・本願上人などともいい、とくにその集団の統率者は大本願とよばれていた。善光寺の場合、本願の史料上の初例は応永三十四年(一四二七)の火災のあと、文明元年(一四六九)に供養された塔の造営費用の勧進を勤めた「本願慈観上人」であった。ただ、この典拠である『新撰和漢合図』はのちに編さんされた一種の年代記であるため、その信憑(しんぴょう)性がやや問題となるが、年代的には全国でももっとも古い本願の所見例であることが注意される。
この慈観上人については他に所伝がないため、経歴等はまったく不明だが、善光寺では一六世紀中ごろ以降、史料上にみえる本願上人の例はいずれも尼であったことが知られるので、この慈観も尼であった可能性がある。全国的にみると、これについで史料にあらわれるのが紀伊粉河寺や伊勢神宮の本願で、これら一五世紀後半から存在が知られる本願はいずれも尼である点から、本願聖はもともと尼を主体として出現したとみることも、あながち無理ではない。善光寺も乱世におけるそうした社会的動向のなかで、女性宗教者によって寺内の営繕や経済活動が支えられる寺院に転化したのである。彼女たちの出自については、中世の勧進比丘尼(びくに)・唱導比丘尼たちの拠点の多くが熊野であったことから、やはり熊野系比丘尼が主流ではなかったかと推定される。享禄(きょうろく)四年(一五三一)の善光寺造営図によると、当時境内に熊野三社権現(ごんげん)が勧請(かんじょう)されていたことや、近世初頭の事例だが、慶長(けいちょう)十六年(一六一一)勧進途中に越中国砺波(となみ)郡安居(やっすい)村(富山県砺波郡福野町安居)の安居寺(あんごじ)に立ち寄った「善光寺聖」の智教尼(ちきょうに)が、『熊野之本地』を所持していたことなども(安居寺文書)、その点を示唆(しさ)している。
この時代に本願尼が活躍した背景としては、中世後期は決して女性の社会的地位が失墜(しっつい)した時代ではなく、女大名なども存在したり、とくに女の物売りが広範に出現したことなどにうかがわれるように、女性がもっとも社会的に躍動していた時代であった点をまずあげうる。しかし、善光寺についてはそうした点のみではなく、鎌倉時代以降、「女人救済」の寺として京・鎌倉をはじめ、全国の女性たちの信仰を集める寺院であったことも関係している。