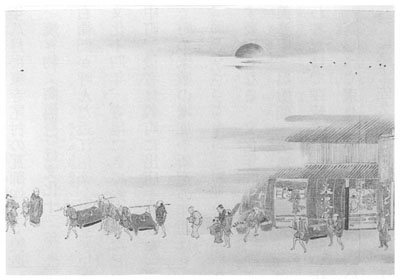文化九年(一八一二)十月六日、藩主真田幸専(ゆきたか)が御用人原織部(おりべ)宅へ立ち寄ったとき、お慰みとして昼間は太神楽(だいかぐら)、夜は伊勢町の踊り狂言を御覧にいれた。同様に、同月二十一日の御側役(おそばやく)小川友衛(ともえ)宅では昼は玉隠し、夜は伊勢町の踊り狂言、十一月七日の家老小山田主膳(おやまだしゅぜん)宅では昼は狂言と采女三番(うねめさんばん)(謡曲)、夜は中町の踊り狂言七幕を御覧に供した(漫筆)。踊り狂言は歌舞伎芝居である。家中や町々に謡曲・能や太神楽、歌舞伎芝居などが盛んで、藩主もまきこんでいたことが知られる。
この文化年間(一八〇四~一八)ごろは、町の家数が増し、町内のあちこちに新道もできた。新道には盲目の座頭(ざとう)の献金によるものもあった。馬場町裏の新小路は文政年間(一八一八~三〇)に座頭篠の一(しののいち)の志願と献金でつくられた。寺町から石切ヶ脇へ出る小路は、座頭豊寿一の献金をもとに世話人が尽力し、嘉永元年(一八四八)に完成した(家記)。町八町(まちはっちょう)からあふれだした人びとが寺社境内、武家屋敷、侍(さむらい)町などや、清野(きよの)村内の新馬喰(しんばくろう)町など村々の町続き地に住みつき(見聞録)、藩が町外町(ちょうがいまち)として把握する住民が増加した。文化・文政の化政期(かせいき)は町が活気に満ちてきたときで、その前後のころにわたり、町々の景観、武家・町民の衣食住から風俗・趣味・ことばなどにいたるまで、さまざまな変化があらわれてくる。変化は早い時期から徐々にすすんできていたのだが、ここではめざましく変化した化政期を中心に変化をみよう。
生活の変化の基礎には生産の高まりがある。松代領では、木綿(もめん)・菜種(なたね)をはじめ多様な商品作物とその加工業が展開した(『市誌』③五章)。また、蚕糸業は一八世紀末から急速に発達し、文化七年には松代糸市(いといち)が設けられる。その前年の文化六年、先進地の上州(群馬県)から女性二人を招いて八丈縞(はちじょうじま)・郡内縞(ぐんないじま)など絹縞織の生産がはじまり、町家(まちや)や武家屋敷に織り所が八ヵ所できた。機具(はたぐ)では、寛政十二年(一八〇〇)藩士小幡(おばた)家に越後高田藩(播磨(はりま)姫路より移封(いほう))の家中から嫁(とつ)いできた女性が、播磨機具(京機具)をもちこんでいた(漫筆)。
武家・町民の暮らしと直結するひとつに水車の普及がある。城下界隈(かいわい)で最初に水車を設けたのは、明和年間の西条村(松代町)友左衛門だったが、文化年間には西条村内だけで水車家(や)が二五軒になり、城下の武家も搗き米(つきまい)・搗き麦から麦粉・うどん粉まで、一〇中九まではこれらの水車家へ出すようになった(漫筆)。
水産物の増殖も、町の暮らしと直結する。松代周辺はもともと川魚が豊富で、漁師のほか下層藩士や町民にも川漁をおこなうものがいた。鮭(さけ)・鱒(ます)・鮠(はや)(ウグイ)・鮒(ふな)・鮎(あゆ)などである。たとえば、関屋川(せきやがわ)などから流れでて寺尾橋をへて大鋒寺(だいほうじ)裏(松代町柴)で千曲川に落ちるあいだの川には、七、八寸の大ものの鮠が多かった。四ッ手網には深すぎるため「ケイサンデといふ汕網(すくいあみ)を以て水中へ沈み汕(すく)ふなり。(中略)大鋒寺裏より寺尾下迄汕ひ来れば、鮠・鮒取り交ぜ六、七百目はいつも取り得たり」という(見聞録)。しかし、千曲川水系には鯉(こい)や鰻(うなぎ)はいなかった。「アラメ・アキワと唱ふる二種も産して里俚(りり)(俗説)呼んで鯉となせしが、世上に金鱗(きんりん)と称する真(しん)の鯉魚及び鰻魚は古(いにしえ)より未曾有(みぞう)なり」であった(真田貫道「一誠斎紀実(いっせいさいきじつ)」『北信郷土叢書』⑦以下、紀実と略記)。
鯉と鰻が千曲川に繁殖するようになったのは、関屋御林(おはやし)(松代町豊栄(とよさか))の桑園開発などで著名な吾妻銀右衛門(あがつまぎんえもん)による。銀右衛門は「松代地方に鯉魚無きを看(み)て山城(やましろ)(京都府)淀川(よどがわ)の鯉魚の子を贖(あがな)ひ養育して漸次成長せり。一年大雨降り続き谷川の水溢(あふ)れて、銀右衛門が穿(うが)ちし池の堤防を破り、数千頭の鯉魚流出し、別池に養ふ鰻魚と同じく千隈川(ちくまがわ)に入りしより、鯉・鰻の二種始めてこの川に産殖(さんしょく)す」(紀実)。鯉子を購入したのは近江(おうみ)(滋賀県)愛智川(えちがわ)だともいい、金二〇両だったという(家記)。ただし、千曲川上流の佐久地方ではより早くから「淀鯉(よどごい)」(淀川の鯉)を飼い、洪水で千曲川へ流出している。その後も、文政年間の末に東条(松代町)大日(だいにち)池で増田孫兵衛らが鰻・鮒を飼いはじめた。天保初年(一八三〇ごろ)には、四ッ谷(同)の西の堤(つつみ)という池で藩士のものが「ドキョウ(蚕の蛹(さなぎ))」を餌(えさ)にして鯉を飼った。しかし、これは上水道の水源池のひとつだったため、強い苦情が出て藩が禁じた(見聞録)。中・下級藩士たちは、屋敷を流れる用水で泉水(せんすい)とよぶ堀池をつくり養鯉をおこなった。幕末には、千曲川・犀川とその支流から用水にいたるまで鯉が生息するようになった(家記)。
蜆(しじみ)も、もとはいなかった。蜆は薬用にも用いるが、諏訪湖か江戸方面から入手するほかなかった。藩士片岡此面(しめん)が遠地から蜆を運び川々に放ったのが繁殖して、「今は衆人朝夕の菜(さい)に供するに至」った(紀実)。
諸産業の発達が町の暮らしを高める一面、町の需要が新たな産業をよびおこす。石工(いしく)が増し切石(きりいし)の製造と施工が盛んになったのは、後者の色あいが濃い。木橋だけだった町の橋に石橋が登場する。天明四年(一七八四)木町にできた石橋(思案橋)が切石づくりの橋の最初で、それから城の御馬出(おうまだ)しの橋、紺屋町の筋違(すじちがい)橋なども石橋になった。神社の石鳥居は古くは皆神山(みなかみやま)の秋葉(あきば)社、加賀井(かがい)村(松代町東条)の住吉(すみよし)社ぐらいだったが、天明以降、東条の池田宮や中条・寺尾(松代町)の愛宕(あたご)社なども石の大鳥居になった。大石灯籠(おおいしどうろう)もはじまった。かつては土蔵の石垣に切石を用いることはまれで、用いても一、二尺の石だったが、文化年間になると三尺、なかには四、五尺もの大切石が使われるようになった。塀下の石垣も切石が多くなった。文化五年には城内の焔硝蔵(えんしょうぐら)が切石づくりでつくられた(漫筆)。さらに、町の辻や村々の路傍(ろぼう)の石造物が急速に増したのも化政期で、道祖神(どうそじん)や地蔵、火伏(ひぶ)せの秋葉山(あきばさん)などの石仏・石祠(せきし)が立てられた。
松代町と周辺で使われている石材は、古いものは赤みのある皆神山産の皆神石だったが、新しいものは白っぽい金井山産の柴石(しばいし)である。皆神石は硬いが、柴石は軟らかく細工しやすい。増大する石材需要にこたえ、切石を製造・施工したり石造物を刻んだりしたのは、主として柴石の石工たちであった。
瓦(かわら)屋根はもとは長国寺御霊屋(おたまや)のぐし(屋根の棟)、東条村の虚空蔵(こくぞう)の祠(ほこら)のみだったが、天明年間(一七八一~八九)に東寺尾村に瓦師(かわらし)が住みつき、城の御殿玄関・門・櫓(やぐら)からはじまり、武家や上層町家の土蔵の屋根なども瓦になった。城の門や櫓に瓦製の鯱(しゃち)がのるのもこのころである(漫筆)。鯱瓦には釘彫りの文字があり、天明五年八月に東寺尾村の瓦御作事(おさくじ)で製造し、瓦工は尾張(おわり)(愛知県)からきた文助であると記す(『海津旧顕録』)。
焼き物(陶磁器)は文化十三年(一八一六)、八田嘉右衛門(はったかえもん)が呼んだ京都の焼物師が寺尾で、普請奉行の上村何右衛門が呼んだ近江信楽(おうみしがらき)(滋賀県信楽町)の焼物師が天王山で、それぞれ窯(かま)を築いて焼きはじめた。鋳物師(いもじ)は翌文化十四年、寺尾にきて鍋(なべ)・釜(かま)などの鋳物(いもの)細工をはじめ、その後田中(松代町)にも鋳物師が住みつき、前者は中町、後者は穀町に出店を設けた(家記)。
町の家数の増加や新道の開通はもとより、石材建造物や瓦屋根、石仏群などは、上水道の敷設(『市誌』③四章二節)などとともに、町並みの景観を大きく変えるが、個々の商い店や職人細工店の変化も景観の変貌(へんぼう)をもたらす要因となる。文化年間(一八〇四~一八)ごろ、町のなかで目立つ大店(おおだな)には、「角見世(かどみせ)菊屋(八田家)、呉服(ごふく)北一美濃屋(みのや)、呉服間一美濃屋、中美のや、中町小升屋(こますや)七郎太等」があった(漫筆)。こうした大店は家屋の造作が変わるだけで存続するが、町々の商い店や職人店には消長があり、町並みのなかに新規の店が登場してくる。
藁(わら)しべで束ねていた髪を元結(もとゆい)で結(ゆ)い、鬢(びん)付けに伽羅(きゃら)油を使いはじめたのは江戸中期である。宝永五年(一七〇八)に藩士佐久間一学が婚礼の餞(はなむけ)に江戸元結と小さな蛤(はまぐり)入りの伽羅油を贈ったことが、あとあとまで語り草になったほどで、当時一般の町人・百姓は鬢へ水をつけて紙のこよりで結い、下層のものはまだ藁しべだった。ずっと後年に、中町で伽羅屋弥右衛門が江戸で仕入れた伽羅油を売ったが、小さな貝に少しずつ入れた貴重品だった(家記)。化政期(一八〇四~三〇)になると、紺屋町の松屋惣左衛門の店で「ま津の香(かおり)」という鬢付け油を売りだし、それから流行してあちこちの店で元結・髪油を売るようになった。丁字屋(ちょうじや)喜三郎は、江戸神明(しんめい)大横町の丁字屋文蔵に長く奉公したもので、木町に髪油・元結・蝋燭(ろうそく)の店を出した(見聞録)。
昔は髪は家で結っていた。櫛(くし)道具をもって町々を回りあるく髪結(かみゆい)が登場してからも髪結床(どこ)はなく、明和年間(一七六四~七二)にはじめて髪結床ができた(漫筆)。「髪結は紺屋町に小兵衛と申す者、下中町半蔵と申す者、田町梅翁院(ばいおういん)前に円蔵と申す者、この三人なり」(見聞録)といい、「五ヶ所あり」(漫筆)とも書かれ、増えてきていた。しかし、「町方の者、中以上の者は銭湯(せんとう)・髪結床へ決して行かず。中以上の見世(みせ)にては売子(うりこ)・丁稚(でっち)の髪は、番頭(ばんとう)か年頃の者髪・月代(さかやき)いたし呉(くれ)たり。番頭等は相互にいたしたり」という(見聞録)。
中以上の商家は利用しないという銭湯(湯屋(ゆや))は、一八世紀後半に登場したらしい。「湯屋は昔は鍛冶町に一軒ありしのみなりしが、三十年来紺屋町にも一軒あり」(漫筆)だった。鍛冶町の銭湯が廃業したあとは、「紺屋町に一軒、鏡屋町(伊勢町の枝町)に一軒きりなり。文化五、六年頃、中町下横町へ西寺尾村(松代町)水主(せんどう)某出張銭湯を始め、都合三軒と成りたり」(見聞録)という。家中にも銭湯を好むものがいた。鍛冶町に銭湯があったころ、大熊四郎左衛門は銭湯の留め湯が好きでつねに出向いた(家記)。しかし、文政六年に藩主が幸貫(ゆきつら)になったあと、給人(きゅうにん)(知行取り)以上の藩士の入湯は禁じられた(見聞録)。
菓子屋は、ひなびた煎餅(せんべい)・饅頭(まんじゅう)や駄菓子(だがし)ばかりであった。宝暦年間(一七五一~六四)に東木町で店借(たながり)の河内(かわち)屋が砂糖入り饅頭を売りはじめたが、まだ在来の砂糖なしの駄(だ)饅頭のほうが好まれていた程度だった(見聞録・漫筆)。また「浪花屋茂兵衛(なにわやもへえ)と由す者、鏡屋町にて浪花煎餅と号すを焼き始め、松代に始めて売り出し、百文につき百八十枚より二百枚位」で(見聞録)、江戸の三美人と評判の難波(なにわ)屋おきたの画像を看板にした(家記)が、家中や上層町家は贈答品用の菓子を上田や松本から取りよせていた(見聞録・家記)。しかし、寛政二年のころ、「大坂屋磯右衛門(いそえもん)といふ者、江戸にて習ひ候趣にて、伊勢町北野屋の下隣へ開店、京御菓子所といふ看板を出し」た(見聞録)。「今の大坂屋は三都(京・大坂・江戸)に比すべし」と評され、文化四年に藩の御菓子司に指定されている(漫筆)。
豆腐屋は古くから町々に存在したが、文化七年に竹山同心町にできた豆腐店は、長く江戸の料理茶屋で修業してきたものの開店で、求めに応じて豆腐ばかりで包丁(ほうちょう)さばきよく種々の献立をつくった(漫筆)。
職人では、伊勢町に来住した馬具師(ばぐし)六兵衛がすぐれた腕の持ち主で、文化八年に御馬具師に任じられた。時計師の市左衛門は、文政元年に松代へきた。江戸中橋南槙町(みなみまきちょう)(東京都中央区)の水戸藩御時計師田中市右衛門方で修業したもので、伊勢町の借家で開業した。鎌原桐山も所持の自鳴鐘(じめいしょう)(時計)を修理させている(漫筆)。
下駄屋(げたや)ができるのは文化年間以後のことで、文化七、八年にはまだ下駄はなかった。差立(さしだち)とよばれる最上級の藩士たちですら、ガヅとよぶ麻屑(あさくず)や竹の皮などでつくった粗末な草履(ぞうり)だった(漫筆)。易者(えきしゃ)では、文化八年に中町に逗留した平川亘理(わたり)がよくあたるという評判をとった。伊達和泉(いずみ)という易者も回り、よくあたるといわれた(漫筆)。
藩士のなかにも職人並みに手細工(てざいく)で生計を支えるものが多かった。文化七年の記事のなかに、「藩士の小禄なるは窃(ひそか)に手細工をなして家内の口を糊(のり)する者多し。提灯(ちょうちん)・傘(かさ)(雨傘・日傘)・竹笠・漆(うるし)細工・檜物(ひもの)細工などその工人よりは製作勝(まさ)れり。書写をなす者絶(たえ)て鮮(すく)なし。漁(りょう)する者最も多し、鳥獣を猟(と)る者は少なし」とある(漫筆)。
衣食住の変化も当然に大きかった。「松代町で家造りに天井(てんじょう)を張った最初、土蔵を建てた最初、竹を栽培した最初は、みな木村縫殿右衛門(ぬいえもん)」(漫筆)である。江戸中期のことだが、江戸中期でも上層を除く一般の町家では、平屋(ひらや)建て、土間(どま)、板・茅葺(かやぶ)き屋根といった家が多く、掘っ立て柱の家も残っていたと思われる。文化年間にくだっても、やや場末の馬喰町・紺屋町・紙屋町あたりでは、まだ土間にねこ(厚手の莚(むしろ))を敷いた店で商っていた(漫筆)。しかし、このころになると表通りの大店(おおだな)は礎石柱の二階建て、屋根は瓦葺き、部屋は板敷きの間で、そのうち座敷は畳敷き、天井を張り、障子(しょうじ)・襖(ふすま)や窓があるといった家が増していた。町の大半を焼亡した享保(きょうほう)二年(一七一七)、天明八年(一七八八)の大火などを契機に、家屋の改造がすすみ、また土蔵が建てられた。上層の家では、改築のとき門・塀(へい)・玄関をしつらえたり、床の間や造りつけの仏壇などを設けたりする。
衣類の変化も大きい。江戸初期には藩主ですら紙子(かみこ)(紙製の衣服)を着ることがあり(家記)、絹はたいへんな貴重品で、一般には麻衣料だったが、一七世紀後半に麻から木綿への「衣料革命」が信州でもすすむ。とくに地元で木綿の栽培・加工が拡大する一八世紀からは木綿衣料が町人・百姓にも普及した。また、一八世紀末から蚕糸業が発達するにつれ、紬(つむぎ)や絹の衣料が武家をはじめ、公けには禁じられていた町人・百姓にもひろがる。むしろ、財政窮迫から藩主幸貫が木綿衣料を着るなど武家のほうに制約があり、豪商・豪農はじめ上層民の絹衣料のほうが豊富多彩だったと思われる。嫁入りの持参衣装は、武家より豪農商のほうがよほど豪華であった。
木綿にせよ紬・絹にせよ衣服には流行があった。布の丈(たけ)・幅、織り方、文様(もんよう)、染色等々の趣向が移りかわる。たとえば、安永の末年(一七八〇ごろ)には、茶色や栗皮色が流行し、帯幅(おびはば)も衣服の身幅(みはば)もひろく、羽織の丈の長いのが流行した(漫筆)。とくに女性は、衣服も髪形もはやりすたりがいちじるしかった。一例だが、「昔は女の髪につと(日本髪で後方に張りだした部分)がなかった。享保のころからつとを背まで出し、つと差しを金(かね)でこしらえて差した。宝暦ごろはまったくつとなしに結った。明和四年(一七六七)ごろからつとを少しにして鬢(びん)を羽のように出し、鬢差しというものを横に差した。最近は髷(まげ)の中ほどを紅縮緬(べにちりめん)・紅絹のくけ紐(ひも)で結う」(家記)と、髪形が転々と流行した。
畳の座敷や床の間を設ける家屋の改造を背景に、生け花や書画骨董(こっとう)趣味などがひろがる。ほかにも多彩な趣味が出てくるが、はやりすたりがあった。長唄(ながうた)のとき三味(しゃみ)線のほかに笛・太鼓を交えて演ずるのは、善光寺町では以前からあったが、松代町では享和(きょうわ)年間(一八〇一~〇四)からである(漫筆)。蹴鞠(けまり)は一時期家中に流行し、明和六年(一七六九)には殿中で蹴鞠の殿様御覧があったが、このころが極盛期でしだいに衰え、文化六年には毬場(まりば)一ヵ所、愛好の家中五、六人にすぎなくなった(漫筆)。
風流な趣味では、秋に鈴虫を飼って鳴き声を楽しむことが天明年間ごろはじまる。化政期には、子どものいる藩士宅では山から鈴虫を採ってきて虫籠(むしかご)を柱に掛け、茄子(なす)を薄く切り細かな刻みをつけ砂糖を塗ったものをあたえるなどして、鳴き声を競った(漫筆)。秋には菊の大作りも流行した。一本で高さ六、七尺、幅一丈余りに作る。あるいは物の形に作る。立枝を接(つ)いで紅白その他の異色をもって形をなす大作りが東都(江戸)で流行したが、松代では文化四年の秋、「柘植量右衛門(つげかずえもん)が黄の中菊を扇子の形に作り、高さ七尺、横二間、元枝五本、末枝四百六十四本、花数七百余枚に仕立てた。以来年々作っている」(漫筆)。
ことばの変化もいろいろおこる。「有り難(ありがた)し」という口上は、昔は殿様にだけ用いたが、延享年間(一七四四~四八)ごろ家中へも使うようになり、明和年間ごろから下層の侍相手でも使うようになった。また、願い書に「様」を付ける相手は、昔は殿様ばかりで、ほかは家老へも「殿」付けだったのが、今は様付けがひろがった。食べ物を食べることを「いただき候」などというのは、最近のはやりことばであるという(家記)。