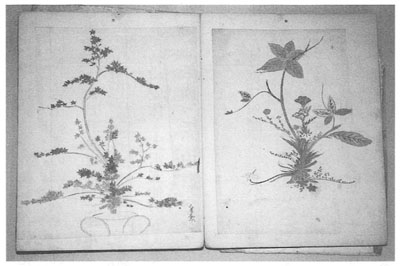茶の湯も武家のたしなみであった。松代藩では、安永末年から天明初年までさかんにおこなわれた。遠州流の松代藩始祖祢津要左衛門友直(高三一五石)、石州流の小山田主膳(しゅぜん)(高一一六九石、家老)、真田図書(ずしょ)(高五〇〇石)、河原舎人(かわらとねり)(高五五〇石)の四人が名人で、このころは一年に茶会が八〇~九〇席あったという。しだいに衰えて、文化五、六年(一八〇八、九)には大英寺や八田嘉右衛門宅で茶会があったものの、それぞれ年に三席を出ないほどになっていた(漫筆)。袮津友直は若いとき、芝居に夢中になって芝居中間(ちゅうげん)になって越後へ行ったこともあるという。
六代藩主信弘の給仕となった大沢安仙が石州流門人となり、石州流開祖片桐貞昌いらいの正伝をうけ、松代で多くの門人に茶道を教授した。文化五年(一八〇八)十一月十二日、大英寺茶会が住職崆峒(くうどう)上人の招きであった。床の間には古田織部(おりべ)の軸がかざられ、釜(かま)はあしや霰(あられ)、炭取りはふくべ、薫物入れは駿河(するが)(静岡県)の賤機焼(しずはたやき)、花は水仙、これは花桶とともに第下(だいか)(藩主幸専)の賜品という。水指しは高麗(こうらい)焼、茶入れは藤四郎(二代目加藤藤四郎景正の真中古(まちょうこ)をさすか)、耳付き茶碗(ちゃわん)は絵半洲、茶杓(ちゃしゃく)は怡渓(いけい)和尚の作であった。客は矢沢頼容・鎌原桐山・矢野清武・竹村安休・大沢安仙の五人で、桐山は土産として京都嵐山の桜木でつくった盃(さかずき)に土佐光貞が描いた桜花の蒔絵(まきえ)などを贈って、中酒(ちゅうしゅ)(茶会での二献めのお酒)の興趣を添えた(漫筆)。上級武士層の雅(みやび)やかな茶の湯の世界がうかがえよう。
立花(りっか)は寛文年間(一六六一~七三)に池坊(いけのぼう)二代専好(せんこう)の門弟安立坊(あだちぼう)周玉らが編みだした新しい生け花の様式で、胴作(どうづくり)に景色を表現するように工夫するもので、寛政年間(一七八九~一八〇一)以後七九(しちく)の道具ともよばれた。松代藩では、宝暦・明和(一七五一~七二)ころ、菅木工右衛門(もくえもん)が立花の名手で、伊勢参りのついでに上京して池坊の門弟となり、松の一色そのほか種々の技(わざ)をうけて達人となった。同じころ、立花が藩内でさかんとなり、中村原民や村田新五兵衛、矢沢氏家臣の宇佐美清右衛門も上手であった(漫筆)。青山流の大森庄兵衛もいた。明治維新後、宏道流もさかんになり、大英寺に二世青木挿花暁雲斎、願行寺に三世青木清義暁雲斎、岩村春学陽雲斎らの碑がある。
菅家は代々小笠原流の指南をつとめ、信之の葬送については、菅木工右衛門(文化年間の菅杢右衛門の高祖父)が勤め、そのときの器物が文化年間(一八〇四~一八)まで多く残り、婚礼などの儀式を指南していた。近藤民之助家にも小笠原流の書籍が多く残されており、同家もそうした儀礼には詳しかった(漫筆)。文化年間に普請奉行をつとめた大日方勘助も立花の名手だったらしく、同家には池坊流「立花口伝書(くでんしょ)」や大日方勘助が筆写した色彩豊かな立花図が残されている。
寛政年間ころから江戸で菊の大作り(一本に高さ六、七尺、幅一丈余)に仕立てたり、紅白の挿し枝をして帆掛け船や孔雀(くじゃく)などさまざまなかたちにして楽しむことが流行した。松代藩では柘植量右衛門(つげかずえもん)が、寛政七年(一七九五)の秋に黄色の中菊を高さ七尺、横二間の扇子のかたちにつくったのが評判となった。かれは隠居後も作り物に励み、菊作り名人として知られたようである。文化ころには大菊つくりはまれになった。中菊は天明(一七八一~八九)の末ごろ、出浦半平が作りはじめた。花のまわりが三寸くらいで、藩士池田右近がつくる菊は伊勢種といって、花周囲が五、六寸あった。また、数種接ぎ木をして品種改良をおこなう者も出た。(漫筆)。