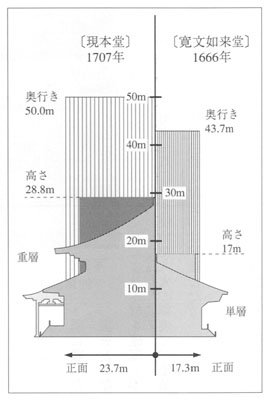寛文如来堂(本堂)の傷(いた)みがすすんだ元禄年間(一六八八~一七〇四)、善光寺は本格的な本堂再建を計画した。造営事業の進行は、善光寺の自力による造営計画がすすめられた前期と、元禄十三年(一七〇〇)の火災でその苦労が水泡に帰したあと、幕府が介入し松代藩が監督して宝永四年(一七〇七)に完成するまでの後期とに大別される。
まず、造営のための資金集めが不可欠であった。善光寺は元禄五年(一六九二)、三都(江戸・京都・大坂)の出開帳(でがいちょう)を寺社奉行所に願いだして許可を得、さっそく江戸の回向院(えこういん)で六〇日間出開帳をおこなった。同七年、京都・大坂でも出開帳をおこない、奉加金約二万八〇〇〇両を得た。これにより木材を確保し本堂工事を進展させたが、元禄十三年七月、大門町の下堀小路で出火し町家一八〇軒を焼いた大火の類焼で、集積してあった用材の大部分が焼失し、本堂も焼け落ちた。責めを負って大勧進(だいかんじん)住職見海法印(けんかいほういん)は辞職した。
同年十二月、幕府のてこ入れにより、日光門主(寛永寺住職)によって江戸駒込(こまごめ)大保福寺・谷中(やなか)感応寺住職の慶運(けいうん)が善光寺大勧進住職に補(ほ)され、戒善院(かいぜんいん)の号を賜わった。慶運はこれまでの奉加金の使途をきびしく追及して不正分を弁償させるいっぽう、寺社奉行所の許可をとり翌十四年三月十日から六〇日間、谷中感応寺で出開帳をおこなった。しかし、前回の出開帳から間もないこともあって予想外の不振に終わったため、願いでて日本国回国(かいこく)出開帳の許可を得、同年九月から足かけ六年間をついやして本州・九州・四国をまわった。回国奉加金は旅先から数千両ずつ松代藩に預けられ、二万三〇〇〇両余にのぼった(一〇章一節参照)。
新本堂の建設地としては、中世以来の本堂が門前町に近すぎて幾度も類焼の難にあってきたことから、町家(まちや)から離して北へ移すこととした。寛文本堂から約一〇〇メートルほど北に、一〇〇間四方(一万坪、約三万三〇〇〇平万メートル)の敷地を確保した。このため、旧本堂の北方にあった北之門町の二十数軒の住民を城山下の新町(しんまち)に移転させ、耕地を買いとった。これまで新町地域に住んでいた人びとは横山下へ移された。北之門町には人家のほか畑と丘があり湯福川(ゆぶくがわ)が流れていた。削平(さくへい)整地して新境内をつくり、その東・北・西に土塁(どるい)をめぐらせ、土塁の外がわに今みるような直角に折れ曲がる湯福川の人工流路をつくった。