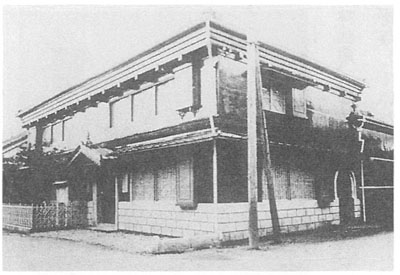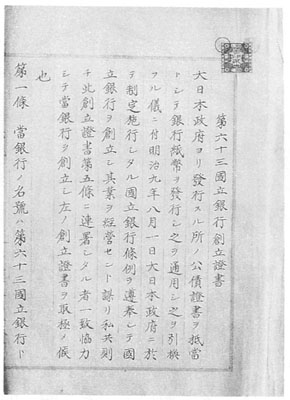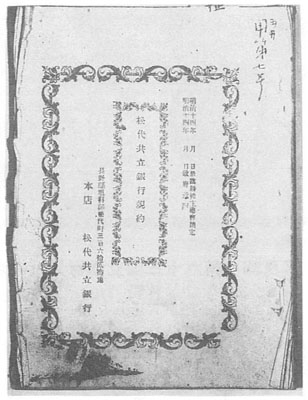長野県内の地元資本による最初の銀行設立は、県為替方(かわせがた)をつとめた彰真(しょうしん)社であった。この金融機関は、早川重右衛門ら佐久郡の一〇人の素封(そほう)家と水内郡栗田村の倉石吉左衛門によって、明治九年(一八七六)六月に結成され、長野西之門町五九九番地で営業を始めた。為替方とは、県へ収納すべき金銭を徴収し、また県の指示にもとづいて諸方へ払い渡す銀行である。為替方としての業務には契約期限があったようで、明治十三年四月に、同社は一七ヵ条にのぼる誓約書を県に提出して、二年間の公金取り扱いを命じられている。またいっぽうで同社は一般の金融業もあわせおこなった。そのうち、『荷為替(にがわせ)貸付帳 長野彰真社』によって、生糸の生産などのために前貸しされる資金(荷為替取組みによる資金貸し)の動向をみると、つぎのようになっている。
創業後の七月二十一日から貸し付けが始まっているが、年末までの貸付総件数三〇件、その総額二万九三二〇円のうち、器械製糸場に貸し付けられた分は、九一・二パーセントにもおよんでいる。貸付対象としては、須坂町の製糸結社・東行社の社長小田切武兵衛がほとんどを占めている。生糸の受取人は横浜の生糸売込問屋野沢屋(茂木林兵衛、惣兵衛)であった。このようにして、彰真社は公金を預かり、それを製糸業に振り向けて、その振興に寄与していたといえる。また同社のなかに、第十九国立銀行(本店上田町)長野出張所が併設され、両社は業務を融通し合っていたが、県が為替方業務を全面的に田中銀行に移すことによって、十七年六月で彰真社の為替方としての使命は終わり、自然に休業状態になった。
国立銀行条例公布にもとづいて、松代町では八田知道らが発起人となって、国立銀行の設立を願いでた。その背景には以下のような事情があった。松代地方の多大な生糸生産額に比べて、地元商人の資金力は乏しかったため、製糸家から少しずつ生糸を買いいれて、横浜へ輸送し、それを担保として横浜生糸問屋から資金を得て、再び地元で生糸を仕入れる。これを数回繰りかえすことによってようやく一まとまりの荷になった。これによって無駄な費用と時間を費やし、有利な相場で販売する機会をのがすのみか、横浜の倉庫には半端(はんぱ)な商品があふれていたために、外国商人の買いたたきにあっていた。もう一つの事情は士族に支給された金禄公債が生活困窮の余り、人手に渡るのを防ぐことであった。松代士族は、帰農するにも土地がなく、他に就産の機会もなかったために、公債を資本金に組みいれて、国立銀行設立を希望した。松代士族に支給された金禄公債総額はおよそ八十余万円であったが、十年九月までに一三万円分を収集し、その後も若干増える見込みであった。
さいわい、第六十三国立銀行は県内第四番目の国立銀行として認可され、明治十一年十二月に松代町三三一番地で、開業の運びになった。当初、四〇〇人の株主によって資本金一〇万円(二〇〇〇株・一株五〇円)で発足した。経営には小県郡生田村(丸子町)吉池文之助(八〇株所有)、松代町八田知道、同町太田藤右衛門、同町増田徳左衛門、同町永島新兵衛、北佐久郡布施村(望月町)常田五郎三郎、上水内郡檀田(まゆみだ)村(長野市)荒木佐右衛門、上水内郡栃原(とちはら)村(戸隠村)岡本廣太(以上、いずれも六〇株所有)の大株主があたった。このうち、八田と太田は士族であり、これらの経営者につぐものの所有株式は高々一三株にすぎなかった。全体として、総株主の九四・三パーセント(三七七人)、総株式の七八・七パーセント(一五七四株)は士族が占めていた。
翌十二年に長野西町五三四番地に同行長野出張所を設け、それを荒木佐右衛門・山口久米太らに任せたが、十三年に荒木ほか五人が発起人となって長野銀行を創設したので、同行に国立銀行業務を委託した。
明治十四年から始まる不況(松方デフレ)によって、国立銀行の業績は悪化し、ついに二十一年になって、資本金二五万円のうち一〇万円を減額して不良貸付の処分にあてざるをえなかった。しかし、このあとも経営は好転しなかったのみか、二十四年の松代町の大火で致命的な打撃を受け、稲荷山銀行に救済を求めるはめにおちいった。
国立銀行とは別に、私立銀行の設立も多くみられた。明治十三年中には前述の長野銀行を筆頭に、長野貯蔵銀行が、翌年には松代貯積銀行と松代共立銀行が、十六年には更級郡原村の原銀行が相ついで認可され、開業している。ところがこのうち、松代共立銀行は明治十五年に、原銀行は十八年に、長野銀行と松代貯積銀行は二十六年に姿を消している。国立銀行の場合と同様、十年代後半を経営的に乗り切れなかったのである。とりわけ松代共立銀行はきわめて短命であったため、実態がよくわかっていないが、松林左金吾(松代町)、近藤千三郎(同)、山崎寛左衛門(御厨(みくりや)村)ら一四三人の株主によって、松代町三六二番地に設立された資本金一二万円の規模の大きい銀行であった。
ところで、不況期の銀行の実態を長野銀行の場合でみると、不況が深刻化するにつれて預金と当座貸越が減少したのに対し、貸付高は増加しているが、それが取りたてられず、不良貸付化している。その結果、十八年上半期には資金貸付よりも安全な公債証書の買いいれに走るなど、経営が消極化し、抵当物の流入によって資金繰りは苦しくなっている。受取利息も十五年下半期と十七年同期で比べると半減しており、経営事情のきびしさは明らかである。
これに対して、長野貯蔵銀行は宮下太七郎ら五人によって、長野町大門町八九番地に建てられた資本金一万円の零細銀行であるが、破産したのは明治四十三年にいたってである。同行の経営で注目されるのは、明治十九年二月の慈善事業であろう。『信毎』の記事によれば、長野町では長びく不況も手伝って、飢えと寒さに苦しむ細民が大勢いた。かれらに対する同行の救助策として、単に金銭を施すのではなく、大門町の同行前付近の道路修繕に従事させて、賃金を払う方法をとった。同行ではまず、土砂を入れるかご二百余を買い置き、一かご運搬につき、三銭をあたえた。体力のない老幼のかごには、なるべく土砂を少なく入れてやり、しかも五回運ばなくても一五銭支払ってやった。鞋(わらじ)を履(は)いていないものには、それをあてがった。この施与にあずかったもののなかには、二、三日の絶食もめずらしくなく、歩行さえ困難な極貧者もいた。いっぽう、かれらに紛れこんで稼ぐものに、田畑を所有し、貸金をもっている裕福なものもいたという。一〇日以上にわたる労働で、一日あたり二〇〇人余が三十余円を受けとった。これは、同行の美挙として当時、話題になった。