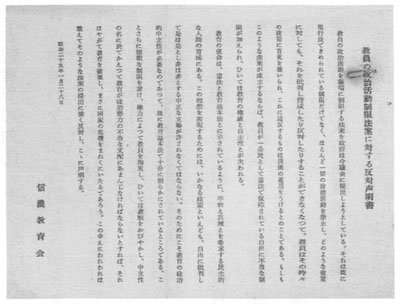昭和三十年(一九五五)前後から四十年代にかけての、全国的な教育制度の改定や市町村合併の進行は、教育現場に大きな影響をあたえ、それぞれの問題についての対応と解決には、賛否両論のなかで時間と苦悩をともなうものであった。数多くの問題のなかから長野県と長野市が抱えたおもなものをあげれば、つぎの四項目である。
①教育委員会制度の改定
②教職員の勤務評定問題
③「道徳」の特設をふくむ教育課程の改訂
④市町村合併にともなう教育会組織の分離統合問題
戦後間もなくスタートした公選による教育委員会制度は、昭和三十一年六月二日可決(同年十月一日施行)の「地方教育行政の組織および運営に関する法律」により、教育委員が首長による任命制となったほか、教育長は上部機関による承認制となり、また、上部機関は下部機関への措置要求権をもつことになった。そしてさらに、勤務評定と学校管理規則の作成と実施などが規定された。これらの理由については、「教育行政と一般行政との調和をすすめ、教育の政治的中立と教育行政の安定の確保のため」としているが、一面では教育の国家統制と管理強化を強めるものでもあった。これにより教育委員の公選(昭和二十七年実施)は一回だけで終わり、一般行政から独立した教育行政の画期的な改革は後退せざるを得なくなった。公選制として最終の長野県教育委員の六人は、「新教委法は政府が教育内容に介入し、教育行政が官僚化する危惧(きぐ)がある」として反対していたが、公選委員のすじを通して新法公布の前日(六月二十八日)総辞退した。市町村教育委員会も三十一年十月から任命制によりスタートしたが、旧委員からひきつづき任命されたものは全体の二二パーセントにすぎなかった。
長野市でも第一回任命制教育委員は、三十一年十月一日、甘利恒雄、太田進、吉沢幸重、中村京子、竹内菊雄(教育長)の五人であった。このうち、新教育委員長は篠原辰弥から甘利恒雄にかわり、教育長は竹内がひきつづいて就任したほかは、委員はすべて入れ代わった。県下一般に教育長は旧委員会では八〇パーセントが助役あるいは教育課長の兼任であったが、改選後は大部分が専任となり、兼任も三十二年四月までには、新法によりすべてが専任となり強化されていった。新法により検定教科書以外の教材使用の際は、教育委員会の承認または屈け出が必要のため、県は三十一年十月教材取扱規則を決めたり、また、学校管理規則を決めて教職員の勤務条件などに制限を加えていった。
昭和三十年代当初に、文部省による日本教職員組合対策によって、教員の勤務評定(以下、勤評)の問題がおこった。勤評は三十二年度から実施した愛媛県教育委員会と同県教職員組合の紛争に、日本教職員組合(以下、日教組)が非常事態宣言を出して、日本高校教職員組合と提携して強力な阻止運動をおこし、全国の勤評問題として展開された。文部省は同年十二月都道府県教育委員会を通じて三十三年度からの勤評実施をもとめた。
長野県教育委員会(以下、県教委)も実施試案の検討をはじめ、長野県の教育事情に応じた「独自方式」で三十三年十月実施を決めた。これにたいし、県教職員組合(以下、県教組)・県高校教職員組合(以下、県高教組)などが共闘を組んで勤評阻止闘争を展開した。県教委は両教組との交渉のなかで、三十三年七月には勤評試案説明会第一回を、八月には校長管理職手当支給の意向を表明した。勤評の第二回説明会は九月に、第三回は十月に開いたが、十一月の県教委と両教組の団体交渉は決裂した。その後知事の調停で、勤評に関する九人の審議会が構成され、第四回の会合で答申を作成し知事調停書として示された。これは、評定者が記入する「A表」と、被評定者個人の自己観察と希望事項記録の「B表」とから成るもので、後者がいわゆる「長野方式」と呼ばれるものであった。この方式にたいして文部省が異存のないことを表明したことにより、県は「県立学校職員」と「市町村立学校職員」の勤務評定規則を三十四年二月九日に制定公布した。しかし、この実施にあたり、県教組では臨時大会で執行部原案として「B表」不記入の問題が討議されたが否決され、各職場において全員記入提出の結果となった。いっぽう、県高教組では、三十四年度は各職場での校長交渉や九月末のB表提出期限をこえる多数の不提出あるいは不記入記名提出であった。
勤評と併せて出された校長管理職手当は三十四年九月の県議会の議決により、他府県より一年遅れて同年四月にさかのぼって支給となった。また、教頭制は翌三十五年から実施された。
勤評実施問題は、県高教組が県教委を相手に長野地裁に「B表記入義務不存在確認請求」を提訴し、さらに、三十六年には知事を相手に提訴して裁判は並行してすすめられた。この裁判は数年間におよんだが、三十九年六月の最終公判の判決で、原告の請求を「B表は違憲でない」として棄却した。原告は直ちに東京高裁へ控訴したが、同高裁は四十一年二月「この控訴には具体的な争いがなく、県は当事者適格がない」という理由で、原判決を取りけしたため、原告は最高裁へ上告した。四十七年十一月最高裁はやはり二審判決を支持して上告を棄却した。
教育課程の改善については、国が昭和二十九年ころから研究調査をはじめ、教育課程審議会の答申を経て三十三年十月文部省告示で「新教育課程」が発表された。その内容は、従来の各教科と教科以外の活動の二領域をあらため、各教科・道徳・特別教育活動・学校行事等の四領域とし、とくに、「道徳」の時間を特設した。小学校は三十年度から移行して三十六年度実施、中学校は三十五年度から移行して三十七年度に実施とされた。
長野市教育委員会(以下、市教委)は、三十三年十月二十五日新教育課程に準拠した「長野市基準カリキュラム」の作成を、市教育会に委嘱した。これをうけた同教育会は、小・中学校別に教科(道徳をふくむ)ごとの基準カリキュラム委員会を組織し、小学校は三十四年度、中学校は三十五年度からの移行措置案の作成にあたった。そして、市基準カリキュラムは小学校分か三十六年度前半までに、中学校分か同年度末までに市内各学校へ印刷配布された。
このうち、新設の「道徳」については、一週一時間以上を特設することになっており、国の実施要綱には、小学校四、中学校三の指導目標をあげ、こまかい指導案が示されていた。これにたいしては、一般に「修身科の復活」との批判もあったので、これにこたえ得るもので、しかも学校現場では教科書のない授業展開に有効なカリキュラムの作成に苦慮することになった。
昭和四十一年十月の長野市と周辺一市三町三村の大合併は、合併後の各郡市教育会の分離統合に大きな影響をあたえた。長野市内の小中学校教職員数は、統合前の昭和四十年には七七五人であったが、統合後の四十五年には一三七五人となり、およそ一・八倍の増員となった。統合前の上水内・上高井・更埴の各教育会に所属していた学校職員は、合併により長野市教育会へ加入することになるが、事情があって必ずしも直ちに長野市教育会へ加入はできなかった。全員の加入が実現したのは合併後三年余を経た四十五年であった。
更埴教育会は、昭和三十年代の町村合併により、それまでの更級郡と埴科郡の各教育会が三十六年三月四日に篠ノ井の更級教育館と通明中学校を会場にそれぞれ「解散総会」を開き、同日ひきつづき通明中学校を会場に更埴教育会の「創立総会」を開いて、同年四月一日から「更埴教育会」として発足していた。それからわずか五年余にして再び長野市との合併による教育会の分離統合問題となった。まず、大合併直後四十一年十二月二十二日更埴教育会代議員会では、同会内の対策委員会の検討結果案として「四十二年以降の更埴教育会の組織の在りかたは変更しない」と決議された。また、若穂地区教職員会長は「本年度内は現組織のままで活動を継続し、来年度四月から十分に研究された新組織によって活動したい」と長野市教育会長あて暫定措置を申しいれた。長野市側はこれを了承し、若穂・七二会の両地区は四十二年度から長野市へ加入することになった。
いっぽう、長野市当局は新長野市の早急な統一が急務であるとして「長野市教育大綱」を作成し、また、長野市教委は四十三年四月、長野市校長協会(犀川北部と南部に分かれたので一本化までの名称)に「長野市の教育をさらに前進させるため」の方途を諮問した。これを受けて市校長協会は研究を重ね、校長会・学年会等と教育会の一本化を答申した。これにより、四十四年度には教育会以外は長野市に統合された(『長野市教育会史』)。
更埴教育会では四十四年五月「在り方委員会」を設置し、研究に入ったが、意見は分離論・慎重論・現状維持論に分かれて合意に達しなかった。このような情勢のなか、長野市・更埴の両教育会代表者は分離統合について協議を重ね、同年十一月には一本化の方向が了解され統合委員会をつくってすすめることとなった。更埴教育会でも同年十二月の代議員会で「更埴教育会の長野市南部は分離して長野市教育会に統合する」ことが議決され、つづいて四十五年三月五日臨時総会で、四十五年三月三十一日をもって長野市南部は更埴から分離することが可決された。こうして新しい長野市教育会は同年四月一日から発足することとなった。