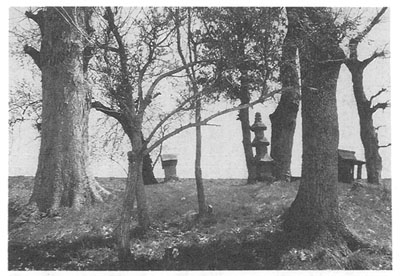長沼城は、戦国期から江戸初期、千曲川左岸の穂保(ほやす)にあった平城である。城は防衛、領民支配の拠点であるが、長沼城の東は千曲川を外堀とする要害、北国街道東回り通りの要衝を占めて渡河地点をも掌握し、西は湿田で区切り、北は外堀をへだてて越後街道をおさえ、すぐれた立地条件に着目して城を築いた。近世中期の「長沼古城之図」(長沼藩時代末)をみると、城の形は南北に長く、東中央に本丸、北に大枡(ます)型、西に二の丸、南に三の丸が本丸を囲み、その周りを水堀がめぐり、本丸の北・西・南を内堀がめぐる。北の大手、南の搦手(からめて)など三ヵ所に「丸馬出し」と呼ぶ武田流築城の特徴がみられる。城の東に馬場、西に侍屋敷を設けている。
長沼城は太田荘島津の居所で、戦国期に同氏は長尾(上杉)方に属した。弘治(こうじ)三年(一五五七)武田軍に攻略され、島津忠直は大倉城へ退き戸屋城を守った。永禄(えいろく)六年(一五六三)、赤沼にいた支流の島津尾張守は、武田信玄から長沼の地下人(じげにん)を還住(げんじゅう)させるように命じられた(島津文書)。その後当城は、北信濃において海津城につぐ武田氏の重要な拠点となる。同十一年三月、信玄は当城で越後攻略の戦勝を祈願している(慈眼寺文書)。
信玄による長沼城修復は三回おこなわれた。第一回目弘治元年には、島津氏の屋敷跡を増強して城とした程度のものであった。第二回目は永禄四年、弟の武田信豊に命じ掻上城を築いて何倍もの大きさにした。第三回目は永禄十一年馬場美濃守信房に築かせ、原与左衛門・市川梅印に守らせた。
天正(てんしょう)十年(一五八二)武田氏滅亡後、一時、織田信長の将森長可(ながよし)が領有、信長の死後同年上杉景勝の領有、旧主島津忠直が城将となった。慶長(けいちょう)三年(一五九八)島津氏が景勝にしたがって会津に移ったのち、豊臣秀吉の蔵入地となり、飯山城に入った関一政が長沼付近の蔵入地を管理した(玅笑寺(みょうしょうじ)文書・浄興寺文書)。同八年松平忠輝か川中島四郡を領し、山田長門守を長沼城代とし長沼領を管理させた。元和(げんな)元年(一六一五)佐久間勝之が大坂の陣の戦功で城主になり、長沼村以下水内郡(みのちごおり)一七ヵ村、一万二五一八石余をはじめ、近江国高島郡と常陸国筑波郡をあわせて一万八〇〇〇石を領した(「寛永諸家系図伝」、貞心寺文書)寛永(かんえい)十一年(一六三四)、二男勝友が一万三〇〇〇石を領して二代藩主となり、長兄勝年の子勝盛に五〇〇〇石を分知した。三代藩主勝豊の子勝茲(かつちか)(勝親)は貞享(じょうきょう)二年(一六八五)家督を継いだが、元禄(げんろく)元年(一六八八)奥小姓を命ぜられながら登城しなかったことを咎(とが)められて改易された。長沼城は廃城となって破却された。