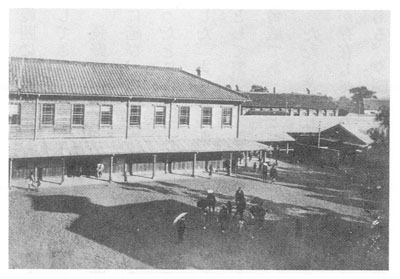長野市は明治三十年(一八九七)に市制を敷き、大正十二年(一九二三)に吉田町・三輪村・芹田(せりた)村・古牧村を合併して以来、昭和二十九年(一九五四)に周辺の一〇ヵ村と合併するまで、その範囲にそれほど大きな変化はみられなかった。ただそのなかにおいて、市街地化は徐々にではあるが確実に進行してきた。
長野駅が明治二十六年に営業を開始するとともに、善光寺から駅前にいたる中央通りのにぎわいはしだいに南に延び、川中島方面などから訪れる人びとを対象とする商店も増加していった。また、かつては水田や桑畑であったところにも人家ができ、新興の町として展開しつつあるところもあった。このような町は主として東に展開した。古くから西の入り口の町として、戸隠村(上水内郡)・鬼無里(きなさ)村(同)方面との物資の受け入れ・提供の拠点として繁栄してきた桜枝(さくらえ)町の商人などからみても、緑町などの新しい町の商人たちは進取の気性をもち、大きな脅威であったという。
ただ、こうした市街地化の進行の速度は遅々(ちち)たるものであって、長いあいた町場と在との境界には、広い耕地が存在していた。村の人びとは、その田畑の向こうに見える町の家並みに、華やかな町の世界を望んでいたのである。夕闇が迫ってもまだ秋の収穫作業に忙しい村人の目には、いち早く瞬(またた)きだした街の明かりは別の世界のもののようにも思われた。また、町から帰ってくるときにも、町はずれからつづく暗い夜道は心細く、村の家々の乏しい明かりに何となく歩みが緩んだという。
村の家々は、耕地などのなかに集落を作って点在し、それぞれの生活を営み、地域社会としての歴史を刻んできた。村境には神をまつり、お宮を中心とした集団として、さまざまな儀礼も伝承してきた。そこには土とともに生きる農民の生活があった。もちろん、県庁所在地として、役場に勤める人もいたし、鉄道の工機部などに勤める停車場行きの人びともいた。そうした勤め人も多くは農家の人びとであり、まったくのサラリーマンとして生活する人びとは少なかった。
ときには分家に出てサラリーマンとして生活する人もいなかったわけではない。また、なんらかの事情で新しく村に住み着く人もいた。そうした人びとの家は村はずれか、なかには耕地のなかの一軒家であることが多かった。だが、そのような人も村の一員としての付き合いをすることがふつうであった。
町には町としての、村には村としての生活がおこなわれており、それらは共通するよりは相違しているものであるという意識が強かった。大門町や権堂町の商家の旦那が落ちぶれて、村はずれで一銭商いをしているなどといわれている家もあった。そうした家の主人は、やはりいい着物を着、妻は白足袋を履いていたという。村の人とは異なる生活をしているといわれているのである。少なくとも、大地を耕して生業をたてる村の人とは異なる生活をしているとみられていたのである。