小金牧とは、現在の松戸市・柏市・印西町から習志野原にまたがる広大なもので、士分の牧士が管理に当たっていた。小金や佐倉の牧で育てられた馬は、民間に払い下げられることもあった。天明二年(一七八二)払馬(はらいうま)があるから、買受けたい者があれば村役人が印鑑持参で金ケ作陣屋まで罷り越すようにという回状が郷村に回された。(32)
この牧で、将軍が猪鹿狩を催すことがあった。江戸時代最高の権力者の遊びは、農民に大負担をかけた。寛政七年(一七九五)の猪鹿狩の際の桜谷村の騒ぎを名主御用留(33)から拾ってみると次のとおりである。
将軍家(家斉)御鹿狩の期日は、三月五日である。それまでに、上総国大多喜辺から下総国六方野まで猪鹿を追いたてよ、という御触が回された。二月二五日には、長南組合の村々の人たちにより棚毛村から金堀川まで追い寄せられて来た。桜谷村年番名主三郎兵衛は、村の壮健な男子四二人を集め追立ての準備を整えた。鉄炮一丁をよく手入れし、えんしょうも準備した。白木綿に「上総国長柄郡桜谷村」と大書した吹流(ふきながし)ののぼりを作り、これにふくべをひとつぶら下げた。二本の高張丁(じょう)ちんには五と書き五郷組合の目印とした。食糧として六升程の餅と焼飯一升、それに干飯(ほしいい)・焼米も少々用意させた。各人は五寸まわり長さ六尺の竹を持ち、みの笠を背につけた。壮健な男たちが不在となり不用心であるから、留守の老人や体の弱い者に、村の上下二か所で夜番するよう申付けた。
二六日早朝六ツ時(六時)金堀川を越して長柄郡に追い込まれた獲物を引継いで、長留・桜谷二か村の者は、山根村・千代丸村と追い立て、四ツ時(一〇時)に御子屋台に達した。九ツ時(一二時)から更に追い立てて道脇等新田に至ったが、大風雨のため新田泊りとなった。二七日は山之郷村で昼食、国吉村に泊り、二八日は中野村昼食、野田村から並木村(四街道町)まで追い立て、ここから帰村した。この時の追い立ては、榎本・小榎本・徳増・長留・桜谷の五か村が共同で行なう約束になっていたのに、榎本・小榎本は下村々と同道し、徳増村は二宮郷の村々と合流して舟木村から帰村してしまった。御触のとおり実行したのは長留・桜谷の二か村だけである。全く長留・桜谷両村を「鼻ぬけ」にした行動であると、年番名主三郎兵衛は憤慨している。この追い立てで、桜谷村は銭三貫七百文を費した。
将軍家慶の行った嘉永四年(一八五一)の小金野猪鹿狩御触書写(34)を見ると、追い立ての全ぼうが明らかとなる。追い立ての規模は、上総国大多喜辺、下総国銚子辺、常陸国真壁郡・野州都賀辺から始まるものであり、「稀成る御鹿之儀ニ付き、一根限り猪鹿残らざるよう精出し一村人別総掛りで追い立てよ、」という厳命が出ていた。
追い立て方は次のとおりである。先ず上村の者共が足並揃えて大声を張り上げる。下村の者共は静かに待受ける。下村へ追い込んだら、上村・下村の者がいっしょになり、大声を立て、足並を揃えて追い立てる。このようにして、五、六か村も追ったら遠方の村の者から順次帰村する。勝手に猪鹿場まで行くのはよいが、早々に引揚げると罰せられた。追い立て方法の諸注意は細微にわたっている。休みなく追い立てると獣が後へ引返す率が高いので、半日位ずつ追い立てよ、とか、留めておく場所は、なるたけ前方に川・沼・堀などのある場所がよいとか、夜は火を炊き大声を立て、眠るのは交替でせよとか細々と述べられている。竹棒・貝などを持参するが、その他「鳴物勝手次第」であった。空砲も大いに使うように書いてある。このような大掛りな追い立てをしたにもかかわらず、嘉永年間、既に郷土には猪鹿はいなかったようである。そのため、房州方面から買求めて小金野に放している。刑部村組合でも鹿一匹と兎二匹を割当てられたが、房州から買って来た鹿に死なれ、兎八匹で勘弁してもらった。(35)(第八節第五項参照)このように、南関東一帯は大騒ぎとなり、勢子の動員、金銭の費えなどで村の負担は大きかったが、農民たちも案外楽しんでいた様子もみえる。稀な催しであり、農閑期であったからであろう。ちなみに、寛政七年の記録は「乙卯歳小金原御猟記」(37)として残されている。上総・下総・常陸武蔵の四箇国十五郡から勢子人足七万二五六七人が動員されたという。尨大な経費と人力をついやして一個人の娯楽の用に供したのであり、現代から見ればまことに不思議な時代であったわけである。
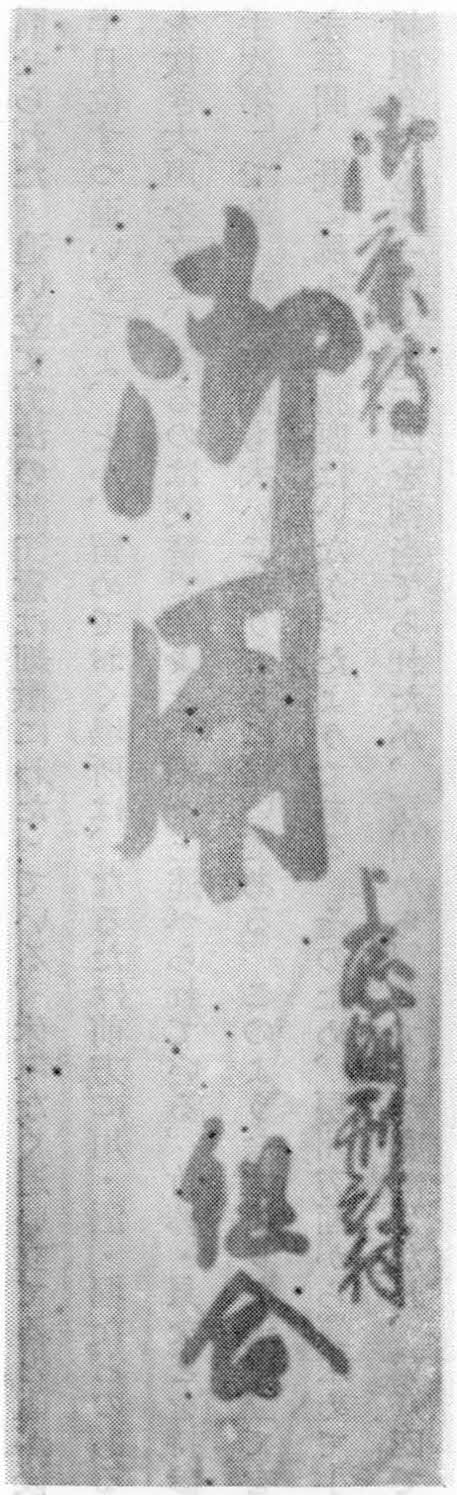
御鹿狩御用掛札
(刑部 村上忠義家蔵)