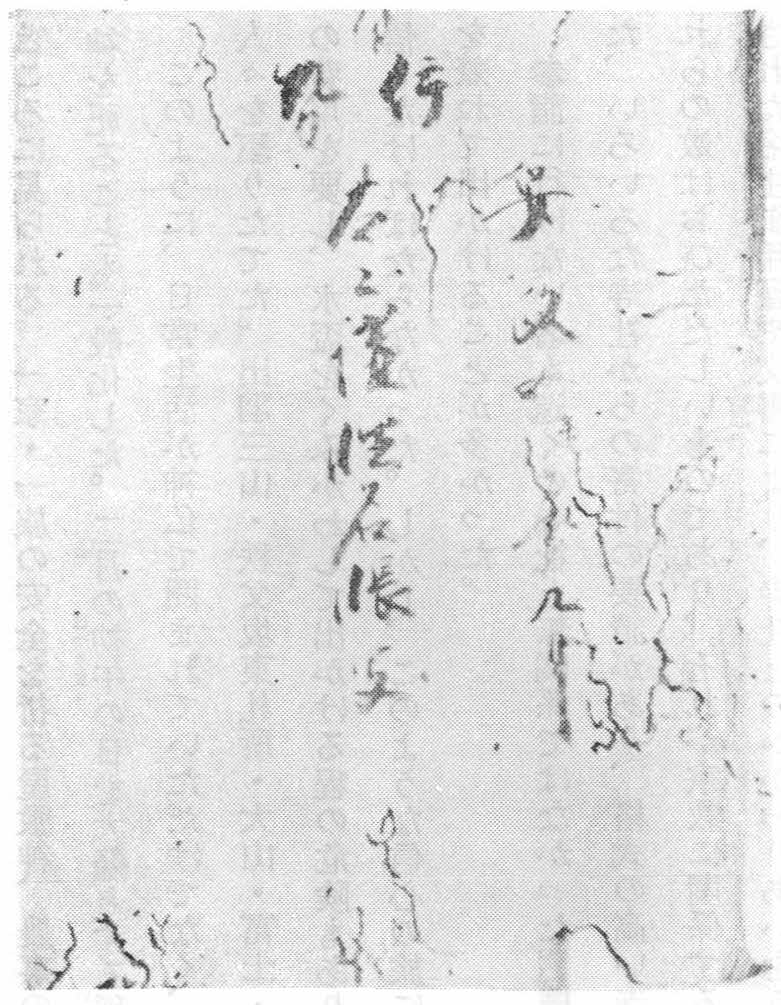
安政5年伊勢太々講姓名帳写
(針ケ谷 小倉喜与巳家蔵)
御師とは御祈祷師の略称で、祈祷するのが本業であったが、一面宿坊の経営者でもあった。江戸時代、庶民の寺社参詣が盛んになるに従い、旅籠(はたご)だけでは参詣者を収容しきれなくなったため宿坊が発達した。皇太神宮の御師は百家にも及び、地方別に檀徒をもち、その地方の人々が講を立てて参宮するときにはその御師の宿坊に泊った。御師は神宮所属の被官となってその職を世襲したから、檀徒との関係は親密となり、年々正月には諸国の檀家を回り初穂料を集めた。御師の中には五位に叙せられる者もあり、某太夫と呼ばれ、権勢と富裕を誇っていた。(38)郷土を檀家とする御師は杉木宗太夫である。
刑部村名主年々用留に伊勢皇太神宮旦回の先触や回状が記録されている。それは、寺社巡行のうち最も物々しいものであった。太神宮御殿(組立式)・御神鏡・勅筆御神号を持参し、これらを餝立(かざりた)てて参拝させた。巡行の手人は上下一〇人、多量の荷物を持ち歩いたので、その先触は巡見使の回村に匹敵する程の人足馬割りや、宿泊割りがなされた。「御旦廻日割并列書」は、御師杉木宗太夫内松村又蔵・藤野証七郎の名で発せられている。「元治二年三月二二日八幡出達、同日刑部泊り、翌二三日昼食も刑部でとる。その間、刑部村に太神宮を餝(かざり)立てておくから近郷の者は、隙取(ひまどり)申さず、残らず御参詣に相成候様に吹聴しておいていただきたい。寄付の儀は、銭であると村方の人足がふえて気の毒であるから、なるべく金子にしていただきたい。」といったような趣旨のことが、細々と述べられている。
刑部近郷の者の参詣が終わると次の寄場へ回るのであるが、村方で継(つぎ)人足二八人、馬四匹も用意しなければならなかった。杉木宗太夫は、上等な夜具や蚊屋まで持ち歩いているので、大変な人馬を要したわけである。刑部村からどこへ回ったか不明であるが、回状は小生田村から大滝(おおたき)(大多喜)猿稲町伊勢屋まで届けるようになっている。先触には、朱印状や寺社奉行の証文について一言も触れていない。皇太神宮の旦回りは天下御免の行事であったのかもしれない。
幕末諸物価の高騰で皇太神宮の経営も苦しくなったとみえ、元治二年一二月には初穂料の値上げが通知されている。「諸色三倍の値段」というから、正に悪性インフレである。そのため、御祓(おはらい)に折暦(おりごよみ)と箸(はし)で百五十銅、御祓と巻暦・箸で百銅、御祓と箸で五十銅、御祓だけで二十四銅となった。