土をもりあげて造ったものがすなわち塚であるが、多くの人力を投じてつくったこれらのものも、その当時には誰びとも皆よく知悉していた筈だが、年代が経過するにつれて記憶がうすれ、それを記録した文献が亡くなれば全くその理由が判らなくなることが多い。上野にある大塚とよばれる巨大な円堆形の丘があるが、おそらくは自然の丘陵を利用した塚ではないかと、その名から推測出来るが、今となってはその名称が残るのみで全く判らない。鴇谷大橋より県道沿いに三百米ほど西よりの地にネイブツ塚とよばれる所があった。今は整地されて全く痕跡を残していないが、昭和四九年ごろまで畑にならずに草地のままであった。「立鳥村由緒書」(立鳥大野弘司家文書)によればこれは念仏塚で、立鳥汲井谷の大部分が真言宗妙泉寺(鴇谷)の檀徒であったのが、昔ある時に日蓮宗に改宗した時に各自の家にあった仏像仏具経巻などを集めて埋めたという。その年代は弘安八年十月と伝えている。同じ立鳥のサイトウ塚は斉藤氏の持山となっているが、ここに寛保三年(一七四三)妙立寺の住職であった人の墓のあった為にこの名が生じたものとおもわれる。また篠網に経塚があり、山の中腹から多くの小石が出てそれらには墨書で一字または三字位の漢字が記されている。これは本来は釈迦滅後五十六億七千万年の後に弥勒(みろく)菩薩が兜率天(とそつてん)からこの世に下生して衆生を救ってくれるその時まで、経典を外道(げどう)の手から守って後世に伝えようという平安初期から始まった埋経思想と、経を心をこめて写すことによって功徳を得たいとする写経の習俗が結びついたもので、写経は紙または布などに写すのであるが、それを小石を集めて経文を書写して地に埋める習俗となったもので、普通はその上にその趣旨を示した石塔をたてるのであるが、この場合は何等の地上の建造物はなく、おそらくは当時、木の塔婆を立てる程度ではなかったろうか。近世のものと推察されるが、ともあれやはり熱心な敬虔な信仰心のあらわれの一つであろう。
また飯尾から御小屋(みこや)台に上る路は中世以前からの古い往還であろうが、この上りきったところに塚があり、今は下に倒れているが一つの石碑のごときものがある。正面に「日元上人説法一万座塚」(高さ一米四四糎)とあり、右に「宝塔山二十九代、享保廿乙卯壬三月十五日、」左に「御飯山五世 建之日領」とある。これは飯尾寺旧址に墓のある日元上人(享保二〇年八〇歳没)の布教活動の記念碑ともいうべきもので、会津の妙法寺の二十九世であり、飯尾寺の住職であった日元の業績を讃えて、飯尾寺の第五世の日領が建立したもの、往来の人に誇示するためのものであろう。
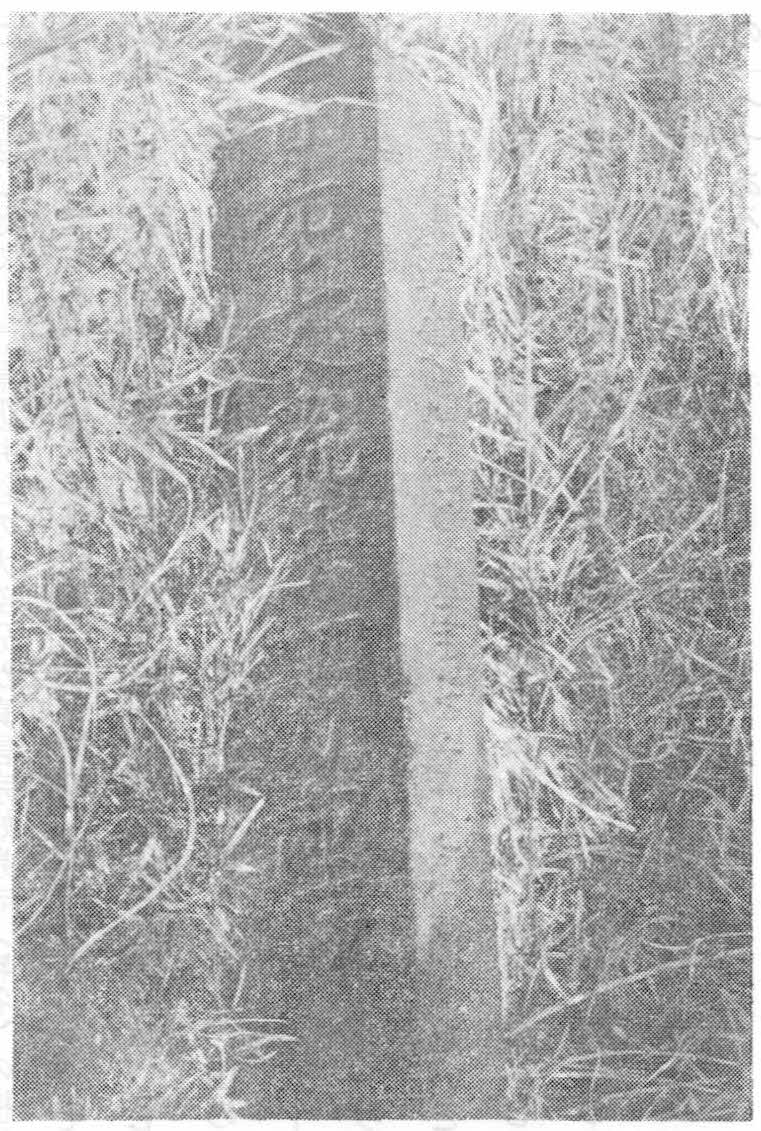
日元上人説法一万座塚碑
また、別に特色ある書体の「南無妙法蓮華経」と頭目を石にきざんで路傍に立てている事が多い。大津倉の路傍にいま倒れているのもその一つだが、寺の入口にもあって例えば飯尾寺山門前、大正寺(千代丸)針谷寺(針ケ谷)その他などにも立てられている。すべて日蓮宗の積極的な布教精神の表現であろう。他に出羽三山供養碑があり、近世のものも若干あるが、それについては研究篇でくわしく論述している。