大田原市教育委員会社会教育課文化係長 益子孝治
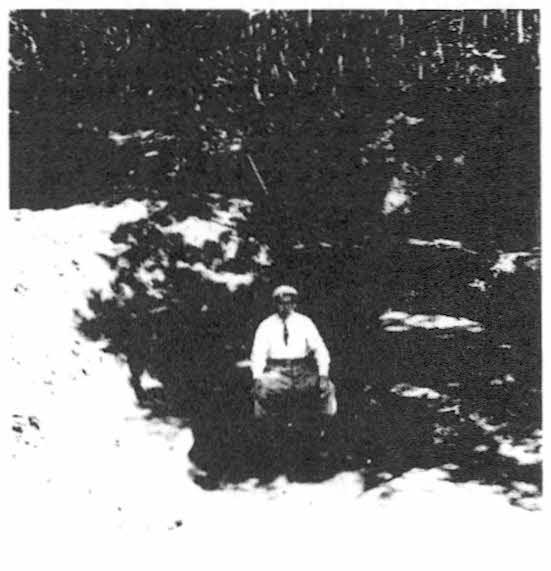
大田原市北金丸湯坂遺跡から出土した,縄文中期阿玉台式深鉢との出会いは,私にとって奇遇といえばまさに奇遇であった。顧みると,私は土木技師が本業であったために,これまでにもしばしば遺跡の発掘現場に直接に接する機会に多く恵まれた。
昭和32年10月の湯坂遺跡発掘調査では,土木課の技師として,大田原市と隣接町村との市外連絡道路改修整備地元請負工事,湯坂黒羽町篠原線,延長 150米。巾員 4.5米。工費4万円を計画担当し改修工事に着手したところ,多数の土器等,石器等が出土した。のち地元の(故)新江元吉,(故)新江丈夫,小泉喜義氏らから強い調査の要望があって,大田原市教育委員会の採択するところとなり,市教委と地区との調査団受入体制が整い調査実施に踏みきったのである。このうらには当時の故大田原市長益子万吉氏のもちまえの豪気沈着機敏な決断によって予算,運営の方法も決らないまヽに調査が行われたと,当時の市教委社会教育課長飯島博(現市議会議員)氏は語っている。
行政サイドでこの発掘調査に直接タッチしたのは飯島課長で,当時合併市として誕生したばかり。職員も社会教育課長外係一名という配置であったヽめ,私が道路改修工事にタッチしたとの理由で発掘調査に行政サイドで補佐することになったのである。
大田原市始まって以来の意義深い調査であったが,発掘現場に馳けつけた当時のことをいまでもありありと思い出す。
10月4日午後1時30分から鍬入式があり益子市長,磯副議長,関谷教育長,池島教育委員長,新江丈夫,新江元吉,小泉喜義,小滝三酉,調査担当者渡辺竜瑞氏外関係者,学生,青年団,飯島課長等が参列して行われ,本格的な調査に入ったのである。宿舎は湯坂公民館,飯島課長は毎日,愛用の自転車で十粁の道程を豚肉を持って宿舎慰問に通ったと聞く。
10月11日,8日間の調査も予期以上の成果をあげて終了した。調査が終了したとともに私も土木課に復帰し,第二次発掘調査については外からながめ,建設担当技師として,昭和51年4月市教委社会教育課文化係に配嘱されるまで,建設事業の一端を担って来た。市教委配嘱によって,今度は文化財に関する係として湯坂遺跡出土縄文土器との再会であり出土土器の管理責任者となったのである。まさに奇遇であった。
この間に於いて,湯坂遺跡発掘担当者渡辺龍瑞氏が,日本考古学年報,10,(昭和32度)に「栃木県那須郡湯坂遺跡」と題して発表。つづいて,宇大歴史研究会(昭和33年)1月発行)「史友」第8号に,同氏が「大田原湯坂遺跡調査メモ」を発表した。
発掘調査に宇大生として参加した海老原郁雄氏は「下野考古」第一号に「湯坂の土器」を発表。
大田原市教育委員会においては,昭和32年の事務報告書のなかで次のように記している。「10月3日より11日迄北金丸湯坂地内の遺跡を発掘調査した結果,縄文式中期の阿玉台―加曽利式の中間の新式らしく目下出土品を整理調査中である。なお住居跡は教育上資料として保存する予定」と。
なお,同書の昭和33年版においては「市道改修に伴い市道の中央で発掘した遺跡を撤去することに社会常任委員会,教育委員会で決定。出土品の保存については,陳列箱を作製し適当なる場所に保管陳列し,学術的参考にする予定」と報告している。
さらに,同書昭和34年版では「湯坂の出土品は復元し,那須庁舎会議室,湯坂公民館え保存展示してある」と報告し,出土品の一部は現在大田原市総合文化会館ロビー並びに湯坂公民館に保管展示されている。
遺跡は,昭和36年3月「埋蔵文化財包蔵地調査カード」に登録し,同年3月22日,大田原市指定第二号の史跡として文化財に指定,大田原市教育委員会告示第四号で告示するに至ったのである。
その後,昭和38年11月第二次発掘調査が塙静夫(作新学院教諭)氏を中心に海老原郁雄(氏家高校教諭)氏をはじめ宇大歴史研究会のメンバーにより,同月22~24日の3日間市教委の指導の下に行われた。
この調査報告は,塩谷郷土史館発行(昭和39年12月)海老原郁雄,田代寛両氏が「栃木県湯坂遺跡調査報告」と題して報告している。
以上の経緯でもわかるように,二回にわたる発掘調査結果報告は市教委より発刊されていなかったのである。
はからずも,昭和52年8月,西那須野町槻沢先住民遺跡発掘現場において,当時二回にわたる湯坂発掘調査にたづさわった海老原郁雄氏と出会い,湯坂遺跡出土品と考古学上重要な意味をもつこの地域と位置付を聞き再度湯坂遺跡と出土品に対する認識を新たにした次第である。20年目にして,又,私の手元で今まで発行されなかった調査報告書が発刊できるか,できないかが,今度は発掘現場ではなくして,机上に於いての問題となって来たのである。
海老原指導主事は,当時発掘した土器の復元も終り市教委に移管したい,又,文化財として指定してもはずかしくない出土品でもある。調査報告書も市教委で発刊してはどうか,とのことをうけたまわったのである。
縄文中期文化の栃木県の出発点として学術的価値が高い湯坂遺跡,出土品を,20年間にもわたって,コツコツと土器復元した熱意と御苦労,好意に打たれ,又20年目にしての私と出土品との出会いが何等かの因果であろうと市教委,市執行部との予算化の折衝に当り昭和53年度に於いて,湯坂遺跡発掘調査報告書,土器陳列ケース7個,出土品収蔵棚4個,土器整理箱50個,金額143万円余を予算化し,この度の調査報告書並びに出土品の陳列化の運びとなった次第である。調査報告書発刊に至る間,多くの関係者特に海老原郁雄氏には大変とお世話になったことをお礼申しあげたい。
私の10数冊あるアルバムの中に一枚の写真が残されている。それは昭和32年10月の湯坂遺跡発掘に参加した時のスナップであった。「湯坂に約4500年前の先住民の住居跡があり,市道の真中に住居跡が出現,土器石斧等多数出土した,測量の手伝などする。市長と共に鍬入式を行った」と添書きに記されている。
湯坂調査にて 渡辺龍瑞
人工星飛ぶ世の秋の遺墟掘れり 大珠の孔確と秋光遍しや
そねもみじ坂の地層も黄昏る, 穴底の古土器秋日へ揚げつづく
遺墟の秋落暉は青き石斧に 遺墟の土器手に手を宿へ月のぼる
カンテラに揚げる秋夜の土器妖し 炉趾の赫さ疎林の秋の木洩れ陽に
光沢今に秋土を出し大珠掌に 遺物積み貨車発つ月の稲田中
(「史友」8号=宇大歴史研究会刊より)