主な地名は『注』のとおり多彩である。
河原の名がしめすように、かなり広い洪涵地(こうかんち)で、穀倉地帯をなしている。ここは延宝元年(一六七三)ころまで大蔵(おおくら)と称したが、その名も同じ意味である。
こゝは旧黒羽藩領で石高は九百九十石四斗三升九合六勺であった。文化十四年(一八一七)ころは家数七十九軒であった。主な生業は農林業である。
八溝山地を刻む松葉川沿いの谷は古くから主要な交通路で、文化の移入路であった。喜連川筋から奥州筋への脇(わき)街道で、人馬の往来もあったので、延宝(一六七三~八〇)のころ前堀村の名主をしていた掃部右衛門は、川押跡に町並みをつくって問(とん)屋を開いたという。今もこの辺り長屋門のある旧家が多くみられる。
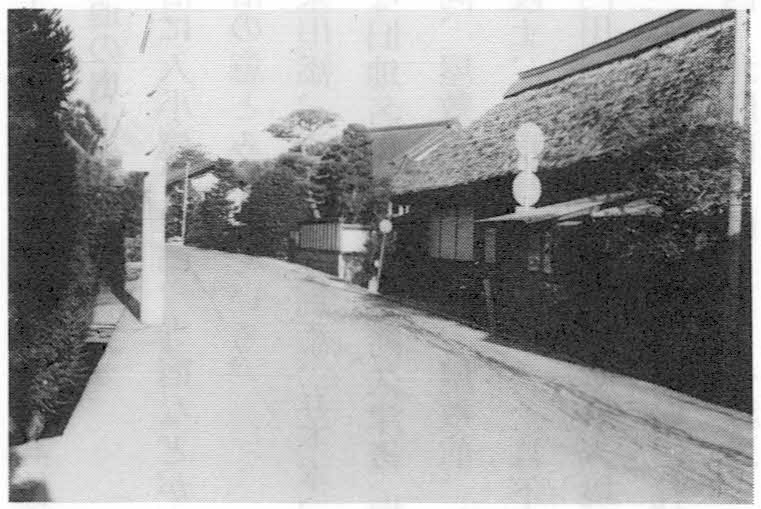
河原の集落景観
(注)河原の地名「奮検地帳所載ノ字河原村 宝暦四年 検地役人井上数右衛門外五人」家ノ前・屋敷前・石田・〓平前・河原田・〓平下・松葉平・於坪内・山下・塚田・屋敷脇・阿久戸田・西ノ入沢・上ノ台・関場・屋敷ノ上・沢水・外手・田ノ入・石田古屋敷・胡桃沢・屋敷内・日向前・腰巻・道添・上人田・小城入・朴ノ木田・五升蒔・梯木田・堂ノ脇・堂ノ前・壱斗弐升蒔・日吉・仲田・三斗蒔・糠田・堂ノ上久保多・道ノ上久保多・堂ノ上・ワセガキ・六斗蒔・河原久保田・谷中田・坂下・石田ケ・天宮・多ケ田・関根沢・間々下・屋敷後・脇沢・井戸ノ上・北向・横沢・井戸ノ尾・妻ノ田・石河原田・古蔵田・ラントウ前・高黒・沢女・横道前・円応寺前・橇田・前棚・日渡シ・〓田・祭田・染田・鰻田・島田・五斗蒔・双六田・清水田・清水祭田・大尊田・大尊田・大水田・籠田・荒屋敷後・下カマ・中田・下田・脊戸山・白屋・屋敷前・横道・屋敷後・町後・屋敷上・河原田・古屋敷・長田・上ノ山・円応寺脇・五ツ譯・一水口・川上り手・川端・於堀・町尻・望田・八作田・下河原・堀ノ女・家ノ前・新屋敷前・屋敷脇・家ノ脇・前堀前・前堀・屋敷前・川端照田・川端・〓下・古屋敷・屋敷ノ内・森ノ前・谷津前・北条田・谷津・一ツ外り田・谷中・川田・沢女・シトウ内・榎町・谷津後・清水尻・谷津入・谷中・通り沢・大沢・北向・評所前・屋敷南・松木下・山館・明地・屏風岩・岩下・鳥居田・月ノ木田・薬師免・石河原畑・十二所・滝沢・四ツ譯・木下・林後・諏訪免・下沢田・大子堂前・道ノ上・水天坊立・天井堀田・壱斗蒔・三角田・八座田・道下・橋場・力ノ内・藍田・遠法師田・〓後・冨貴田・石崩・藤切沢・壱斗五升蒔・家後・屋敷前・森下・清水田・原田・宮下・中沢・膳棚・丸山・大久保尻・於畠ケ沢・中畠ケ・鹿カ窪・横坂・納田・家近所・向山・行人田・森於祭免・越中久保・貉久保・蛇沢・後平・笹田輪・馬坂越・納田稲荷前・上河原・下河原・六斗蒔・小滝・北久保・落久保・林ノ上・納豆内・道ノ目・向沢・平山沢・名主作り・柳町・樋口・南・大子田後・大畠堀向・大子堂原・東町・塚前・西原・明神前・長袖口・梯木平・反田・二本松・縄手添・関場・西ノ久保・百目岳・山ノ神前・戸九沢入・荒屋前・河原田・中ノ内向
(注)この辺り一帯は、古代の『全倉郷』とみられている。