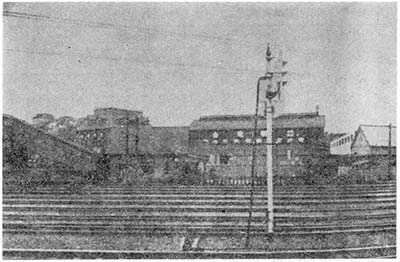つぎに、機械器具工業に移ろう。米騒動も静まり、第一次世界大戦も終結した大正七年十一月、大崎町に芳水小学校を創設・寄付した人こそ、明電舎を創設した重宗芳水とその妻たけ子であった。ところで明治二十年の夏八月、ちょうど十五歳に達した重宗芳水は故郷の山口県岩国から上京、遠縁にあたる三吉正一の経営せる三吉電機工場に徒弟として入職した。当時の三吉工場は、芝四国町(現港区)の二番地の通称薩摩原に移転した直後で、地所三〇〇坪に粗末な掘立小屋のバラック式工場で、徒弟は七名だったという。また、かれはそのころ創立されたばかりの工手学校(現在の工学院大学の前身)の夜学に入学、一生懸命仕事と勉学に励んだ結果、明治二十五年には電燈電力機械部の助手に、さらに明治二十七年に、三吉工場の拡張(明治二十六年には男工一九〇名、女工一〇名、機関は六馬力)とも重なって主任に抜擢された。だが、日清戦争後の景気反動の襲来から三吉工場の経営は悪化し、ついに明治三十年には重宗自身が、独立すべく三吉工場を去ったのである。かくて明治十六年に本邦における最初の電気機械製造工場として創立され、同十八年度当時の工部大学校教授藤岡市助の設計と指導で日本で最初の一五キロワット直流発電機を製作したように、多年本邦電気機器製造工場の濫觴としての地位を占めていた三吉電機工場も、本格的な恐慌の波にうちかつことができず、明治三十一年頃には解散した。ところで、重宗自身は明治三十年十二月、独立自営を決意し、京橋区築地船松町(現中央区)十一番地に約二〇坪の二階建家屋と、漸く入手した五〇〇円の資金を基にして新しく出発したのである。これが明電舎の起りである。しかし、開業はしたものの、注文とてはなく、切換スイッチやナイフスイッチのようなものを二つ三つ拵へる位だったという。だが、翌三十一年春、思いもかけず、京都帝国大学より蓄電池製作の注文があった。当時の京都大学に電気工学科が新設されたため、同教室の実験用電源として、容量一二〇アンペア時、個数五〇、ペースト型極板のものという注文であった。もちろん、この注文品は大量ではなかったが、創業期の明電舎(まだ、その名称になってなかったが)が世に知られるチャンスになった点は疑いない(『重宗芳水伝』、『明電舎技術史』、『東京電燈株式会社五十年史』)。
このような創業期の経営状況の一端を示したのが上の表であるが、当時は日本資本主義の確立期であり、まだ本邦電気産業の展開が十分にみられなかったので、明治三十年代中葉の明電舎は、現状維持が精一杯であったといえよう。かかる経営的苦況にありつつも、重宗は、外国の知識を積極的に吸収しつつ、三相交流発電機の国産化に成功して、明治三十四年には三河電力株式会社より受注、納品、さらに、これの改良を重ねていった。さらに、日露戦争後の明治三十九年三月には、東京電燈株式会社が、東京市内に交流昼間電力を一般需要者に送電すると発表してゆくのであるが、明電舎はこの機を逸せず、三相電気モーターの月賦販売や、賃貸商売に乗り出すこととしたのである。いわば、「明電舎モーター」が精米・印刷・製材などに広く使用されるに至ったわけで、明電舎にとっても発展の原動力となってゆくものである。ただ、これとても、日露戦争むけの発火機(発火用発電機)が陸軍兵器本廠より発注され、日露戦争終了までに、合計三〇二箇を納入するが、いわば軍需生産より得た利益を「明電舎モーター」製作にふりむけた結果だったと考えられる。このようにして、重宗は国産奨励と輸入防遏を志向しつつ東京府農工銀行より十ヵ年賦返還の条件で一万四〇〇〇円を借入れ、工場拡張にのり出してゆくのである。しかも、「明電舎モーター」販売の盛況が高まるにつれ、当時京橋区三十間堀一丁目(現中央区銀座四丁目)にあった鉱山機械・銅鉄ならびにゴム製品販売の守谷商会との間に一手販売契約を結ぶに至った。そして、明治四十四年ごろまでに、前述の東京府農工銀行よりの借入金も全額返済したので、明治四十五年二月、国電大崎駅に近い六、〇〇〇坪の工場敷地を撰定した。当時の大崎駅付近は人煙稀な郊外の田畑の続く風景であったが、目黒川との舟運の便もよく、桐ケ谷村より土砂を運んで地均しをし、二、〇〇〇坪をこす工場建設に着手してゆくのである。
| 項目 | 資産評価額 | 差引損益 | 収支計算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 総収入 | 総支出 | 差引 | うち財産損失 | 純益 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 明治34年6月 | 5,601 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12 | 4,046 | △1,554 | 14,399 | 11,829 | 2,569 | 1,554 | 1,015 |
| 35.6 | 5,197 | 1,150 | 706 | ||||
| 12 | 4,665 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 36.6 | 4,904 | 238 | ― | ― | ― | ― | 238 |
(注)『重宗芳水伝』による。 △は損失額,―は不明。