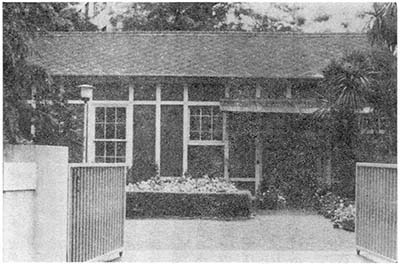日本精工の企業活動が第一次大戦期の山武商会の苦況を乗切らせてゆく動機ともなった点は、すでにふれた。しかも、日本精工と兄弟会社であった日本酸素も同様の働きを示したものといえよう。
日本酸素合資会社は、すでに明治四十三年十月十日、日本精工と同様資本金五万円で創立された。前年、山武商会がドイツのリューベック市ドレーガー=ウェルケ製作の酸素溶接切断器の納入のため横須賀海軍工廠と契約を結び、その年八月、現品を造兵部水雷工場へ納めたのが契機となっている。この時、山武商会は酸素溶接切断に使用する酸素もドイツから輸入し、当初は器具一台ごとに、一、五〇〇リットル入瓶「ボンベ」といわれる鋼製の容器で、内容積約一〇リットル入りに酸素を一五〇気圧で充填したもの(現在でも散見される)を数本添えて販売したという。ところで、このボンベは酸素製造元から借用したもので、当時は使用済になると再び、空瓶をドイツに送り返し、詰めかえてもらい、さらに遠路取寄せるという仕組みであった。山武商会で調査したところ、ドイツ・フランス両国でも、当時酸素製造は新興工業であったがかなり有望だと思われていた。もともと酸素は空気から分離するのであるから、原料代はかからない。むしろ容器が鋼製のため長距離輸送のため運賃が高くつく。もし、酸素を日本国内で製造することができるなら、採算的にも有利で、将来発展性をもつものと考えられ、ここで酸素製造会社の設立が計画されてゆくのである。日本精工の場合と同じく、時の日本銀行副総裁高橋是清の応援をえて、会社の存立期間をいちおう設立の日から満四十ヵ年、山口武彦を会社代表の無限責任社員とし、本店を東京市京橋区(現中央区)南伝馬町三ノ二一番地の山武商会方において発足した。
最初の酸素製造工場用敷地に、明治四十三年当区域内の荏原郡大崎町大字桐ケ谷字谷戸窪四九九番地(現品川区西五反田五丁目二五―二)の三五八坪を買入れ、のち三八坪を買いたしている。現在の「日本酸素記念館」の所在地である。この土地は目黒不動尊に近く、丘の上にあったが、山口武彦らも「空気から酸素を取るのだから、山の中がよい。人家の少ないところが酸素が余計あるだろう」と考え、また付近の人々も「酸素を取ってしまったら、この辺の空気が悪くなってしまう」と真面目に考えて苦情を持ちこんだと伝えられている。公害問題のやかましい今日、夢のような話であるといえよう。
かくて、明治四十四年五月三日、総合運転をおこない、本邦最初の酸素の工業化に成功したのである。この創業当初における酸素分離器は、ドイツからのヒルデブラント社製の単精溜式一台で、空気圧縮機はドイツのワイス=コップ社製を、酸素圧縮機はイギリスのホワイド=ヘッド社製を輸入して酸素工業界の歴史の第一ページを飾ったのである。
当初、この工場は「合資会社日本酸素工場」とよばれたが、大正二年九月、広島に工場が設置されると「東京工場」に、さらに大正五年からは「大崎工場」と改称された。その組織は酸素を製造する「酸素製造部」と溶接、切断等の作業をする「酸素工業部」とに分れたが、後者は規模も小さく、大正五年以降は本所押上(現江戸川区)に溶接切断の専門工場が新設されてゆく。ともあれ、この創業期大崎工場の総勢は一三名で、組長一名、職工四名、火夫一名、定夫三名を含んでいたのであり、小規模ながら装置工業の特徴を示していたといえよう。第一次大戦期の工場従員数は、前表の通りであって、広島・押上両工場設置もあり、全社的には著増を示すが、大崎工場は、大正四年を除けば大差はない。販売状況も大戦勃発後に増大を示し、平均単価も減少してゆくのである。
| 大崎 | 全社計 | |
|---|---|---|
| 年次 | ||
| 名 | 名 | |
| 大正3年 | 13 | 25 |
| 4 | 21 | 32 |
| 5 | 14 | 55 |
| 6 | 12 | 48 |
これに対応して、従来酸素の一手販売を山武商会と契約していたが、大正六年四月からは大崎工場の販売先を日本酸素が譲り受けその代りに満三ヵ年間、売上高の一・五%の口銭を山武商会に支払うこととしたのである。この理由は、かならずしも明らかでないが、日本酸素創立の事情が示すように、軍工廠との関連は密であったが、広島工場が呉海軍工廠を重要得意先としていたのに反して、この大崎工場では、横須賀工廠の入札参加も見送り、民間への酸素供給に傾注してゆく。市中での酸素溶接も次第に普及して「ハイカラ鋳掛け」の新造語も流行したといわれ、溶接・切断などの工業用のほかに、医療用として「日酸式吸入器」を大正六年から売出しており、採算上有利なこともあって、大崎工場の酸素を医療用に充当していったのである。
| 年次 | 大崎工場 | 大崎工場/全社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売量 | 販売金額 | 平均単価 | 販売量 | 販売金額 | ||
| m3 | 円 | 円 | % | % | ||
| 明治44年 | 下 | 5,634 | 10,914 | 1.937 | ||
| 45 | 上 | 7,083 | 13,720 | 1.927 | ||
| 大正元年 | 下 | 12,938 | 25,060 | 1.927 | ||
| 2 | 上 | 14,671 | 30,440 | 2.075 | ||
| 6 | 上 | 28,527 | 35,090 | 1.230 | 26.0 | 42.7 |
| 下 | 30,831 | 45,625 | 1.480 | 28.5 | 49.1 | |
| 7 | 上 | 29,478 | 50,545 | 1.710 | 29.5 | 44.8 |
注)『日本酸素50年史』による,大正2年上期までは,大崎工場のみ。
このように、第一次大戦期の発展につれて、大正七年七月十九日には、公称資本金一〇〇万円の株式会社に組織を変更し、ひきつづいて亀戸工場・小倉工場・名古屋工場をはじめ、大阪・福岡両出張所など続々と経営規模を増大している。たとえば、官営八幡製鉄所の規模拡張あるいは活況をみこしての小倉工場建設にみられるように、第一次大戦期の重化学工業の展開に対応していたものといえよう。
このような展開の側面は、いわば酸素工業勃興期の競争と相重なりあうのであるが、第一次大戦終了後は、当然不況の波に直面することとなったが、例外的に、さきの医療用酸素に関連して「酸素吸入器」にふれた通り、たまたま大流行したスペイン風邪と重なり、特殊の需要増大を示しているのである。
しかしながら、この時期以降、関東大震災の被害も軽微だった大崎工場の実態は、資料的制約もあり、かならずしも明かでない(『日本酸素五十年』および高橋直行『酸素一路』)。
日本酸素の株式会社への改組に先立つこと二ヵ月、大正七年五月十五日に、後述する日本光学の一母胎ともなった東京計器製作所和田嘉衡ら一〇名は、坂本潮の酸素製造技術と経験を基礎に、設立発起人会を開き、鉄鋼業の発展のための「圧搾酸素瓦斯」製造の必要を訴え、以後二回の発起人総会を重ねて、同年十月八日、公称資本金五〇万円の東洋酸素株式会社を創立したのである。当初、本社は、神田(現千代田区)錦町二丁目一六番地におき、府下荏原郡平塚村大字戸越三八〇番地に一、四一一坪の土地を求めて、荏原工場を建設したのである。ここで、日本酸素に比べて興味あることは、ドイツからのヒルデブラント社製酸素瓦斯製造装置一式(毎時三〇立方メートル)を輸入したほかは、空気圧縮機ならびに酸素圧縮機は東京計器製作所小名木川工場製を、空気分離器は東洋酸素創立の契機をつくった坂本潮の指導により、充填装置は小笠原鉄工所製を、酸素瓦斯タンクも石井鉄工所製を使用した点である。ただいわゆるボンベも五〇〇本、アメリカのハリスバーグ社製のものを使用したようである。第一次大戦開始後の輸入機械の杜絶のなかで、主要設備は大略国産品に依拠していったのであるが、大正八年十月の試運転中に破裂事故をおこしたことに露呈されたように、操業安定には、技術的にもかなりの時間が必要だったものと考えられよう。かくて正式操業は大正九年四月五日からで、まさに反動恐慌の真只中だったのである。鉄鋼需要の急減で酸素の需要も亦低調を極め、さらに加えて、日本酸素をはじめとする諸酸素工業との競争も烈しかった。東洋酸素としては、これらの得意先の間をぬって、鍛冶屋・鉄工所等を訪ねて新しい販路を開拓していったのである。例のボンベの運搬といっても、トラックが普及していない状況であったから、大八車に酸素やアセチレン発生装置を、さらに溶接切断器具等を積んで、実際に使用実演をおこない、やっとのことで顧客の増加を図ったという。医療用酸素についても、薬剤師の雇用を条件に警視庁より許可され、説明パンフレット配布とともに、市電の車中にも「吸入用酸素」の写真広告を掲げて、新しい需要の開拓を試みたのである。しかも、需要停滞は、ボンベの回収をおくらせ、昼夜連続の操業は生産過剰ないしは注入容器の不足を生む恐れがあることから、辛うじて昼間運転に止めざるをえなかったともいわれている。
このような苦況を乗切るためにも、大正十年十一月、本社を神田錦町から荏原工場内に移し、合理化の実施と代理店政策をはかろうとしたのである。まさに創業期の苦しい開拓宣伝であったが、さらに関東大震災の発生は、東洋酸素の場合も損害軽微であったが、「帝都復興」の進展につれ、酸素の需要もまた増加傾向を示し、大正末期以降高純度酸素製造装置の増設計画を立案させてゆくこととなる(東洋酸素株式会社『四十年の歩み』)。