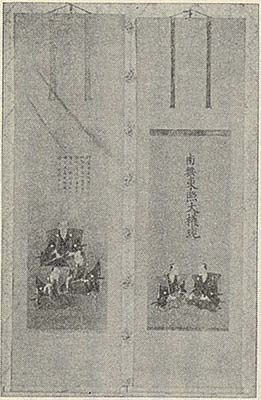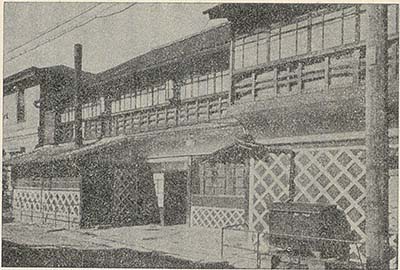旅籠屋は食事を供給する宿屋であり、旅人が食料を携帯して自炊をする木賃宿とは区別されていた。品川宿の旅籠屋は、一時は一八〇軒もあったことがあったが、江戸時代末期には一〇〇軒前後であった。そのうち食売女を置いている食売旅籠屋がほとんどで、食売女のいない平旅籠屋は、その四分の一ほどであった。江戸に近い品川宿では旅籠屋は休泊の施設というよりは、遊興場としての性格が強かったのである。
食売女は飯盛女、食(めし)たき女ともいうが、単なる給仕女ではなく、宿駅において遊女にかわって出現した売春婦であった。幕府は慶安元年(一六四八)吉原以外の場所に遊女を置くことを禁止したが、実際はあちこちに非公認の遊郭(岡場所)ができ、繁昌した。また元禄十五年(一七〇二)に、吉原から遊女商売をしている所として訴え出した中には、品川・千住・新宿・板橋の四宿も入っていた。同じく吉原から差し出した宝永五年(一七〇八)の訴状には「音羽町(護国寺門前)・池之端宮永町(上野山下)の二カ所は家作おびただしく、遊女を多く置いて商売している。別して品川入口の新町(のちの歩行新宿)の茶屋はいずれも特にりっぱに居宅を海手へかけ作りにし、遊女を大分に置いて、昼夜にかぎらず遊女商売をしている」と記されている。
この高輪町寄りに形成された新町の繁栄は本宿の営業をおびやかしたので、正徳五年(一七一五)に北品川新町、善福寺・法禅寺門前の茶屋町に食売女を置くことを一切禁止した。しかし、やがてまた、ゆるんだので、幕府は、享保三年(一七一八)、食売女を抱えていた家主から過料をとり、戸〆(とじめ)を申し渡し、女たちは親か親類に引き渡し、家の造りを改めさせた。同時に本宿の食売女も調査して、旅籠屋一軒につき二人に限ることを通告した。この規定は他宿にも通達され、江戸一〇里四方の宿場では旅籠屋一軒につき食売女二人、一〇里外の宿場はこれに准じるよう、制限が加えられた。
品川宿の食売女は享保期には一、〇〇〇人以上もいたといわれる。ことに歩行新宿の食売旅籠屋のなかには派手に商売を営む者もおり、江戸の遊廓吉原にとっては目の敵(かたき)であった。寛保二年(一七四二)には、吉原の訴えによって品川宿で食売女を多く抱えすぎていることが発覚し、もっとも繁昌していた歩行新宿の松屋六右衛門が所払(ところばらい)となったのをはじめ、多くの者が処罰をうけた。このあと食売女の過人数召抱え事件はしばしば起こったが、明和元年(一七六四)七月になって、歩行新宿の旅籠屋足立屋藤四郎が召使の食売女のことで町奉行所の手入れをうけたことから、宿内は騒然とした。これにより支配代官から、三宿に対して、考えていることを遠慮なく上申するよう命じられ、三宿は食売女が規定の数では到底足りない事情を説明した。同年八月七日三宿の名主らは道中奉行所に召換され、奉行の安藤弾正少弼(惟要)から「これまで食売女は南北品川宿では旅籠屋一軒に二人、歩行新宿では一人という定法であったが、以来は本宿と新宿の差別なく、一軒に何人と限らず、三宿で五〇〇人まではかかえることを許す」という申し渡しがあった。同時に板橋・千住の両宿へは、それぞれ一五〇人の食売女を置くことを許可した。これらの宿々にとっては思いがけない吉報であって、品川宿では、それから毎年の八月七日には、弾正日待(だんじょうひまち)ととなえ、安藤弾正少弼(しょうひつ)と代官の伊奈備前守・勘定組頭江坂孫三郎の画像と姓名の軸をかけ、そのときの請証文へ神酒をそなえ、赤飯をたき、三宿の旅籠屋がより集まって感謝の祭りをするのが例になった。道中奉行や代官は宿駅の繁栄が食売女の存否と関係のあることを知っていたので、食売女の増員を認めたのである。
五〇〇人の食売女は、南品川宿に一五五人、北品川宿に一四三人、歩行新宿に二〇二人ときめられ、さらに一軒ごとに定数があったが、天保改革で大粛正が行われたときには、三宿の旅籠屋はすべて九四軒で、食売女は一三五八人もいた(南品川宿には旅籠屋四〇軒に四一七人、北品川宿には二二軒に三八五人、歩行新宿には三二軒に五五六人)。平均すると一軒に一四人はいたことになる。中には二~三〇人もの食売女を置いていた旅籠屋もあったのである。このときに五〇〇人を超える分は請人・人主方へ引き渡され、五〇〇人の食売女は一六六人ずつ三宿に分けられた。しかし、幕末には再び増加した。
品川の食売旅籠屋の中では土蔵相模といわれた歩行新宿の土蔵造りの相模屋が有名であったが、幕末には北品川宿の岩槻屋佐吉が全盛をきわめた。佐吉は横浜に異人相手の妓楼岩亀楼を作ったことで有名である。なお品川宿の客でとくに多かったのは芝山内(しばさんない)の僧侶と薩摩屋敷の武士であったといわれている。
人を泊める旅籠屋に対して、休憩するところを茶屋といった。品川の遊客はまず茶屋に立ち寄りそこから旅籠屋に案内されたのである。このさい茶屋が旅籠屋から受け取る手数料を引手料といい、この茶屋を引手(ひきて)茶屋といった。その中には遊女を置いて商売をするものも少なくなかった。品川宿の茶屋は弘化頃には歩行新宿に三一軒、北品川に五軒あった。