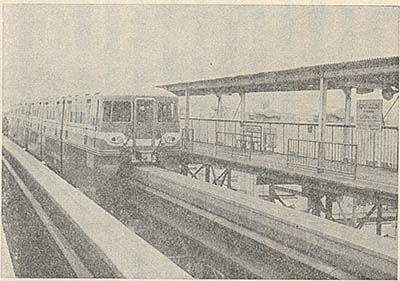(「近代・現代の品川」中扉の写真)
慶応四年正月、鳥羽伏見での戦闘に破れた徳川慶喜は大坂城に退いたまま、戦意を失って、軍艦に投乗して江戸へ逃げ帰った。浜御殿より上陸して、江戸城に入り、抗戦か江戸城(といっても当時西の丸が本城だった。)明渡しかの大評議が開かれた。慶喜は浜御殿につく前、横須賀操練所を出て慶喜と船中で会見したフランス公使ロッシュの戦費を貸すから戦ったらという申し出を退けて既に江戸城明渡しを決心していたという。こうした時、有栖川宮を総督とする江戸城総攻めの東征軍が品川めざして進軍していた。
しかし、品川は東海道の江戸からの最初の宿駅にあたり、本来なら東征軍の本拠地ともなるべき場所であったのに、そうならなかった。
それは前年暮の二十五日三田の薩摩屋敷の焼打ちで、南品川は逃げてきた薩摩藩の人や浪士たちによって焼失させられ、残っている家がほとんどないといった状態だった。そのため東征軍としても、先発は北品川宿に入ったものの、南品川宿が復興していないため、やむなく本営は池上におくといった状態で、人馬の往来はげしい中で、脚光をあびることが出来なかった。
四月十一日に江戸城明渡しが行われ、東征軍の支配下となっても、混乱はつづいた。閏四月の一カ月の間に、江戸を去るべき人々は大体去り、随分市中はさびしくなった。その中で彰義隊が気勢をあげていたが、五月の十四日から十五日にかけての戦闘で、彰義隊が一敗地にまみれ、江戸の混乱が終りをつげた。大崎や品川の方まで逃げて来た彰義隊の兵士に疵(きず)の手当をしてやったり、米をもたしたりして会津方面におちのびるのに手をかした人々が区内に多数いたということは、どんなに徳川びいきの人々がいたかを物語っている。