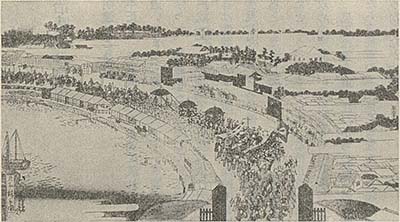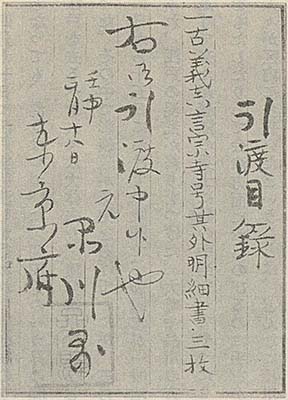こうして品川宿を中心とした人々の生活も一応、平静に帰したが、東北方面の状況悪化と人心一新という点から、新政府側に遷都論が起っていたが、京都市民の反対が猛烈で、江戸遷都とまではいかなかった。この時、東西二京説が唱えられたのをきっかけに、慶応四年七月十七日、江戸を東京(トウケイ)とするという詔勅が出て、江戸は東の京となり、東西二京で進むことになった。
九月に東京府が開かれ、明治と改元があり、十月明治天皇は東幸された。品川到着は十月十二日で、鳳輩は今の荏原神社におかれ、天皇は本陣に宿泊された。品川宿は人夫の大量徴発もあり、大変な騒ぎだったという。明治天皇一行は、翌日、隊伍堂々と品川を出発、増上寺に赴き、衣冠束帯に改めて、江戸城に入られた。江戸はこうして東京として、事実上の首都となり、東西二京の東京は西の京をおいて地名となった。
しかし、行政的に東京というのは旧町奉行支配の地で、別に三人の代官がおさめていた郊外は、品川県・小菅県・大宮県(のち浦和県)の三県に分れ、大体明治二年正月より出発した。当時の品川県というのは、今の品川・大田・世田谷・目黒・渋谷・中野・杉並などの区部、それに新宿区の一部に、多摩の大部分を占める広大な区域だった。
新しい行政がここで行われたが、変転期であったため財政が確立せず、品川県民との間にトラブルもおきた。一番有名なのは備荒貯蓄という名目で、苛酷な積立を強制したため、不満の県民のうち、武蔵野新田の村人たちを主に、当時まだ県庁がなく、日本橋の浜町で事務をとっていた、その品川県事務所へ門訴することに端を発した農民騒動であった。三年一月十日のことである。この時は新政府も県も、これら農民の首謀者を断乎処罰することで威信を示そうとした。
品川県ではビール製造など、少しは目新しいこともやったが、成果をあげるに至らぬうちに、明治四年の廃藩置県となり、各宿村は神奈川県や埼玉県、東京府に分割されて、終りをつげた。
品川宿を中心とする周辺村々は東京府に属し、大区小区時代を迎え、何大区何小区といった名称で呼ぶようになったが、明治十一年いわゆる三新法の出た結果、郡区町村編制法により、東京は十五区六郡に分れ、品川や荏原の地域は全部荏原郡に所属し、郡政が行われることになったが、やはり品川宿のあった関係上、郡役所も旧品川宿におかれることになった。
もちろん、荏原郡になっても、はじめは戸長というものが連合村々の戸長役場にあって行政事務をとるといった、連合戸長役場制の時代であった。