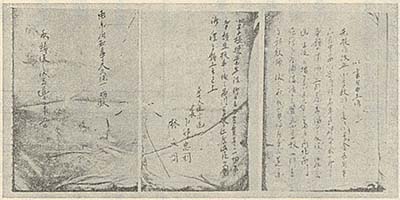江戸時代の庶民教育はかなり古くから寺子屋という私塾で行われ、読み書き算盤などを教えていた。品川宿に一一、下大崎一、小山一、中延一、戸越二、桐ケ谷一と寺子屋があったらしい。さすがに品川宿が寺小屋が多かった。
明治政府は教育の近代化に力を入れ、特に初等教育の発展をめざし、学制を明治五年に発布したが、各村はこれに基づいた公立小学校設立の機運が到来した。
まず上大崎に富士見(日野の前身)、下大崎・戸越・桐ケ谷・居木橋各村連合で設けた桐渓(京陽の前身)の両学校が設けられたが、これは寺小屋と余り変ったものでなかった。
公立小学校としては明治七年二月認可された第二中学区第六番の品川学校、同じ年の十一月設立の第八番城南学校、翌八年大井村の大井学校、更に九年九月に鮫浜、十一年日野、また八年には京陽、七年延山、十二年杜松、十四年には洲崎などの公立学校が出来ていった。
もちろんこの外、一二校の私塾があったというから、区内の初等教育はかなり普及度が高かったといえる。村々に於ては、父子引続いて一つの寺小屋に通い、公立学校ができても、通学させない家庭が多かったため、戸長など村の主なものが公立学校へ通学するようにすすめて歩いたという。
このほか小学校では十九年まで授業料をとっていたから、小学校へ通いたくても行けない児童もかなりあったという話である。
何しろ十九年小学校令が出てから、三年制の下等小学が尋常小学校に、上等小学が高等小学校に変ったりして、教育制度の上でも変化があったが、二十三年から教育制度も小学校令によって整備されていった。
しかし品川宿は別、当時、周辺は全くの農村であったから、農繁期には子供たちまで家の手伝いに追われ、学校を休むものが少くなく、多くの児童は、午後になると半分位に減少するのが常だったという。
当時は品川の宿場町は別として、文部省令による冬休み、夏休みが、時期的に農家の慣習による正月とか稲の植付、刈取りの季節と合わず、公立学校が「新暦」という明治六年以来の政府の方針に従ったため、父兄との間がうまくいかなかった点があったという。農家は新暦を、はじめは無視していたようで、そこに教育上の問題があった。
もっとも町場といわれた南北品川宿においてさえも、なかなか公立小学校へ父兄があげたがらなかった話が残っているほどである。
明治十八年に洪水後の郡部の視察をも兼ねて渡辺府知事が巡回したが、その時には、もうすでに北品川の品川小学校は生徒数が二九七名あって府下六郡中第一位、南品川の城南小学校は二一九名あって第三位だった。この頃品川宿が、東京の郡部で、ずばぬけて繁華な町だったことがわかろう。