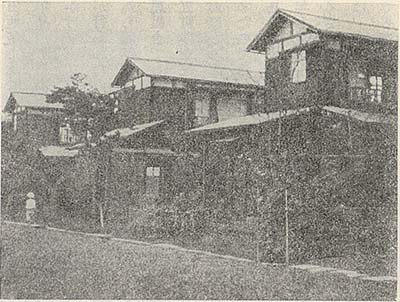大正の初めの品川区地域は、まだ平塚村はじめ大崎町、大井町などが広い部分にわたって田畑で占められ、東京近郊農村としての地位から脱していなかった。当時の農村では細分化し、分散している耕地の交換分合、区画整理灌漑用水の改良などを進める耕地整理事業が一つの重要な課題となっていた(明治四十二年耕地整理法)。しかし、農民の意見が容易に一致しない上に資金も多額を要するため、実施はかなり長い期間にわたり大正初期から昭和六~七年頃までの約二〇年間にわたって全国各地で実施された。品川区地域では目黒川流域や大井海岸部にあった水田地帯で比較的早く実施された。たとえば、明治四十五年品川町耕地整理組合が設立され、それから大正六年にかけて、広町・二日五日市の水田一〇六・九町歩の工事が行われたのを皮切りに大井町の鈴ケ森組合で大正二年から四年にかけて五十七・五町歩、品川・大崎町耕地整理組合で目黒川流域を大正二年から七年にかけて四十六五町歩を完了した。こうして、大正七年頃、品川区地域のほとんどの水田は短冊型にきちんと整理された姿になったのである。ところが、皮肉なことに米の生産力を高めるために行われた耕地整理をすました田んぼは、一〇年も経たないうちに、次々と工場や住宅によって埋めつくされてしまった。きちんと短冊型に区分けした田んぼは、工場や住宅を建てるのにも好都合な条件となったのである。むろん、工場・住宅の建設が進んだ原因は、一次大戦下の工業ブーム、東京への人口集中、とくに関東大震災の結果この地域への人口流入を中心とする都市化によるものであった。しかし、結果的には、いわば耕地整理は工場用地造成のためのおぜん立ての役割りを果したわけである。畑地の耕地整理事業もこれに引続き、この地域でも昭和七、八年頃までに完了した。畑地の場合は、さらに明瞭に最初から住宅地化に適応するための区画整理・道路整備に本当の目的が置かれ、農業の基盤整備は単に名目に過ぎないというありさまであった。しかし、この耕地整理のおかげで、品川区地域は、一部他地区にみられるような迷路のまま宅地化が進むという事態だけは、ともかく回避することができたのである。