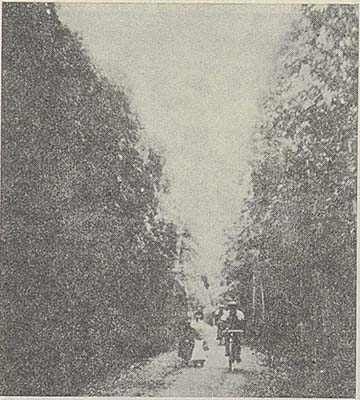明治末期から大正期にかけて東京市の人口は、いちじるしく増加した。市内人口の増大は、それだけ蔬菜などの農産物の販売市場が大きくなったことを意味した。その上、第一次大戦下の好況で農産物価格も上昇し、近郊農村経済は繁栄した。東京府の農業生産は、大正九年を境として米麦よりも蔬菜類の生産額が上廻るに至った。品川区地域では、この変化が一層はっきりと進んだ。すなわち、河川流域の水田の耕地整理の展開とともに工場が建ちはじめたからでもあった。他方では近郊農村として「園芸本位の集約農業」化が進んだ。それは、いたみやすく鮮度がとくに重視される葉菜類をはじめ品川区地域の農業は市街地に、もっとも近いという有利な条件にあったからである。また荏原郡農会の指導も、この方針をとったものとみられる。耕地面積全体は減少する中で、やや畑地の減少傾向が鈍化しているのは、園芸農業の発展によるものと推側してよいだろう。
蔬菜の採裁が盛んになると作付の種類もふえてきた。一軒の農家でも十数種、多ければ数十種類にのぼる蔬菜を、一つの作物の取り入れが終るとすぐ他の作物にかかるという輪作が行われた。それも温室やフレームを使って「七毛から十毛作(間作・輪作)」という集約的土地利用度を高める方策がとられたのである(第14表)。
| 時期 | 作物 |
|---|---|
| 1~3月 | 大根・ネギ・カブ・コマツナ・ホウレンソウ |
| 4~5月 | ミズナ・イチゴ・タケノコ・コマツナ |
| 6月 | 小麦・ネギ・タケノコ・トウナス・キウリ・ジャガイモ |
| 7~9月 | スイカ・ナシウリ・アカウリ・キウリ・ナス・ジャガイモ |
| 10~12月 | サツマイモ・コカブ・大根 |
市街地に隣接していたため、鮮度の高い蔬菜を消費者に届けることができたし、何を消費者が需要しているか、もっとも有利な作物は何かなどの情報も、いち早く知ることができるという利点もあった。また、当時の蔬菜生産には不可欠の人糞肥料を入手し、持ち帰えるのにも距離が近いということは、決定的に有利な条件だったのである。
しかし、近郊農村の園芸農業の繁栄は、永くは続かなかった。その第一の理由は、一時的に近郊農業の繁栄をもたらした東京市の発展そのものが、近郊農業を衰退させる要因に転化したことにある。すなわち、都市人口の郊外への流出と宅地化・都市化によって農業生産の環境が悪くなる。たとえば日照・通風・病虫害の発生・飼犬が荒す・盗難がふえるなど、が指摘されている(帝国農会「大日本農会農談会報告」)。しかし、それに留まらず、農業そのものの魅力よりも、宅地化して、土地を貸した方が、汗水ながして働くよりも収入が多いという事態が生じてきたからである。そうなると、宅地としての借り手や、買う人を待っている土地であれば、いつでも小作人から土地を引きあげることができるように、小作料は低廉しておくか、場合によっては小作料は無料という事例さえ生じたともいわれている。
近郊農業衰退の第二の理由は、交通運輸の発展によって東京市の蔬菜を供給する農村の範囲が急速に拡大し、品川区地域の農業にとって強力な競争相手が生じたのである。きゅうり・なす・トマトなどは神奈川県の農村は高く売れる初物として四月頃出荷できるのに、品川区地域では五月中旬になってしまう、居木橋かぼちゃで有名だったが、碑衾・玉川・駒沢の各村で生産するようになっていたし、千葉からさらに高知・宮崎あたりからも東京市場へ入ってくるようになり、これらの競争相手の前に品川区地域の農業は衰退していったのである。