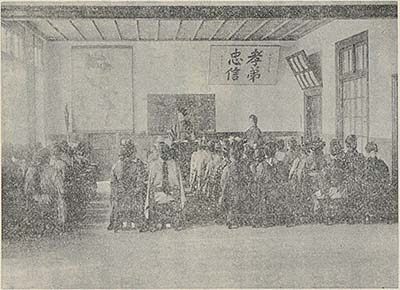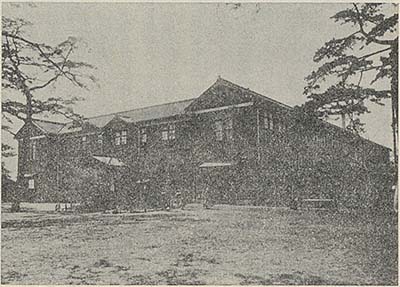明治末期における近代工業の発達、それにともなう都市構造の変化、東京近郊としての人口増大は、教育のうえにも大きな影響をおよぼした。
明治前期における品川の公立小学校は、品川・城南・大井・鮫浜・京陽・日野・杜松・延山・洲崎(大正十三年廃校)の九校であった。その後、何回かの「小学校令」の改正とともに整備され発展を遂げた。明治十九年の法令改正に対応しては品川小と城南小に尋常科とともに高等科をおき、尋常高等小学校となった。三十三年の改正では、義務教育制度の整備確立を目的として尋常小学校の修業年限を四年に統一し、二年の高等小学校の設置を奨励した(明治四十一年、尋常小学校六年、高等小学校二年となる)。大井・鮫浜の二校が尋常高等小学校へと格上げされ、新たに、第二日野尋常高等小学校、平塚高等小学校、東海尋常高等小学校が開校した。
大正期に入ると、大崎町の田園地帯にも工場ができ、品川・大井の各町の海岸部も、工場・住宅が密集する市街地に変貌をとげた。特に、平塚村においては、大震災を境に、のどかな近郊農村風景が一変して、東京市内へ通勤する都市勤労者層を主体とする人口密集地へと急激な変化をとげた。その近郊農村中最大の就学児童の増加をもたらし、これまでの教室には入り切れないので教室の増築や小学校の新設・教員の増員・中学校の設置など教育機関の急激な整備拡充が必要となった。新しく品川町には、浅間台・三木、大井町には山中・鈴ケ森・原・立会、大崎町には芳水・第三日野・第四日野・第五日野、平塚村には小山・大原・宮前と計十三校が開校された。
この大正期における就学児童の増加には驚異的なものがあった。たとえば、品川小学校の生徒数の変遷にその例をとってみると明治七年の開校当時にはわずかに全校で八一名であったが、大正元年には六六二名、大正十五年には一、二四三名と急増したのである。
その間、教室の増設では間に合わず、午前と午後に生徒をわけて授業を行う、いわゆる二部授業や分教場を利用しての授業などで対処しなければならない学校が続出したのである。
当時の二部授業の思い出を大正十四年の卒業生は次のように回想している。
一年に入学した当時、既に校舎が狭かったらしく、一年生だけは午前の組と午後の組との二部教授であった。午前の組と午後の組とは確か一週間毎に交代をしていた。入学してまもない頃、私は午後の組だったので午後からのんびりと出かけて行った。……午後の組の同級生には一人も会わず、何んだかいつもと違って静かな感じがして不思議な気がしたが、花の散った葉桜の日比谷さんの山を眺めながら何時もの様に学校へと入って行った。ところが何時もと違い学校はしんと静まりかえり庭に遊んでいる筈の生徒もみえなかった。さては遅刻をしたなと思い、おそるおそる石段を上り、教室の戸あ明け、中へ一歩はいったとたん、私はびっくりして仕舞った。中には生徒が皆ちゃんと席についていたが、一人も知った顔がいないのである。先生がいたかどうかもわからなかった、忽ち顔や頭が充血してぼーっとなり、どうして部屋を出たか知らないが静かな庭に下り立った時、恥しいやらくやしいやら、かなしいような怒りたいような、何んともいえない気持になった。考えてみるとこの日から私の組は午前であったのである。しかも遅刻をしたのである。急に重くなったカバン、ブランとぶらさがった草履袋、未だ明るい日が輝いているのに、生徒の一人も歩いていてい道をすごすごと我家へと帰った(『品川学校八十五周年記念誌』)
昭和に入っても、とくに都市化現象がすさまじかった荏原町には、昭和三年にもさらに、第二延山・後地・源氏前・大間窪の四校が新しく設立された。この時期において、ほぼ都市化の一段落着いた他の各町村では、品川町で御殿山小学校が一校だけ昭和四年に設立されたのみであった。