画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。

[内題]
娯勢武肥也矩仁無移新喩
(改頁)
[序文1]
建武のみたれより君臣上下こゝろこゝろに九重をいてゝ
みやこちかきしるへのかたへしりそきたまひける中に、
後普光院摂政殿下は嵯峨の中の院に世の塵をさけ
おはしましける時、京極中納言の跡にやならはせ給ひけん、天
暦の御門より其比の君臣に至るまてをおほし出るまゝに、
時代のあとさきをもついてす、み心によしとおほすまゝを
かいあつめおかせ給ひけるか、其後六首(あるひは八首とも)虫はみほろひ
けるを、後の中の院の関白(顕実公)殿下おき給はせたまひて、
後撰百人一首と名つけ給ひけるとなん、此書は彼御家の
太夫のもとより長門の国阿武の春日の祠の宮司波多野
なにかしか家につたへたりしをうつしえて梓にちり
はむることにはなりぬ
(改頁)
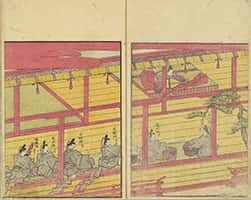
※御会参加の歌人名の翻刻は割愛
(改頁)

※御会参加の歌人名の翻刻は割愛
(改頁)
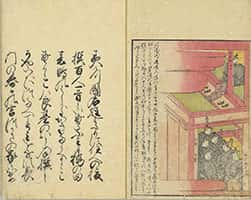
[建保六年八月中殿御会]
順徳院建保六年八月十三日、中殿御会の図にて筆者は正五位下藤原信実
朝臣也、この日管絃の御遊ありて後に主上をはしめ奉り、 池ノ月久ク明シといふ
題にて公卿殿上人廿六首の和歌をよませ給へり、信実朝臣も此人数の内にて
「明らけきみかけになるゝ池水を月にそみかく万代の秋」といふ歌をよまれたり、
(改頁)
[序文2]
みけつ国名庭わたりに住人の後
撰百人一首といへるふみに、秋の田
の鴫のはしかきたかへよとこ
へり、こは良基のおとゝの御撰と
かやいひつたへて、うみをなす長
門の春日の宮つかさの家にひめ
(改頁)

置し書とて、抑もゝつ人の歌を
あつめしは定家の中納言の賢
寂入道のかきとめに随ひてかい
つけおくられしを始として、後の世に
も是かれ集し人もあれと、彼おとゝ
のみ撰ひは、石上ふりにしころより、
(改頁)
いかゝさきいかなる事にか聞つたへ
さりしか、今なむ呉竹の世に
おほやけにもなりなは、誰も誰も
玉くしけ底たからと木綿花
のめてさかへて、此たはかりをも
谷くくのさわたるきはみまてよろ
(改頁)
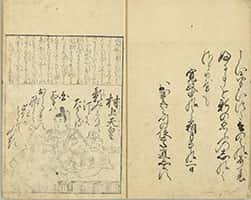
こひにおもひつゝ、言のはの露の
ふる事を、軒の忍ふのしのは
さらめやも、
寛政申のとし霜月中の二日
おほきみつの位さた直しるす