天明三年 浅間焼及騒動記
信濃国浅間嶽之記
文政九年戌三月写之
信濃国浅間嶽之記
近江国(駿河歟)富士山ハ人王七代こうれい(孝霊)天皇之御宇
辛未元年に出現すといふ、
信濃国浅間嶽ハ何れの年煙立ちたるといふ事を
しらす、山の霊たる初仏不思儀をあらハす時を
定めす、只人の心より興る恐るへし慎へし、すてに
持統天皇丙申九年役行者登山なし給へて
東北の山中柳の井有、是に黒蛇住て毒水を吐
人民をなやます、行者怪て本尊へ祈誓し利剣を
以て是を助く、峯に登り巌石を平げ自草庵を
構ひ勧行す、百鬼之類ひさまついて評す、亦福一
満虚空蔵昼夜御来光まし/\て奇談被成しと也、
西北の方にむけんの谷、南方に剣の峯、北に鬼の崖、
東に遠見坂、金亀の岩山の初変無明の山也、外の
浜内の浜あり、其後久敷絶て登る人なし、
弘安四年六月九日の暮方山より西に黄なる雲出て、
(改頁)
皆人草木迄金色の光りうつる、同夜四つ時焼出し信州追分・
小諸より南四里余の間灰砂降火石今にあり、北は
山の麓迄押出し、今に此所石とまりといふ、誠に往古より
焼山なるらん、
天明元年三月十日越前国松葉の矢といふ処より僧壱人
来りて、此山に登りて一夜をあかせりといふ、其夜不思儀の霊
夢を蒙り、吾妻郡山の麓鎌原村に住居して、度々
此山に登り延命寺となりて、東都東叡山寛永寺の
末寺、此僧義海とて則延命寺開山にて北の方浅間
山大明神の別当也、
尓時天明三癸卯年四月九日より焼初め、夫より日々止事
なく灰砂降、七月三日四日別して大焼甚敷、軽井沢・坂本・
松井田・安中・高崎より武州児玉郡・榛沢郡三拾四里の内
弐尺三尺、碓氷峠字笹沢へ五尺六寸降、人馬通路なく
上り下りの大小名御家中方甲州廻り、中山道軽井沢火石
降三拾軒余焼失、碓氷峠社家拾四軒砂石の重しにて
(改頁)
家を潰し、右之外村々山々草木諸作に至る迄如冬、同四日
の晩浅間山吹出し、砂石五丈余も高く火石鞠を取か
如く、煙りの先々砂石雨の如し、同五日の晩八つ時半時分
浅間山より黒煙り寅卯の方へそろ/\と行、其中に
差渡壱丈余の光りものくる/\と廻り火花電のことく、其
けわしき事たとへん方なし、天魔外道の業ならんと鉄
炮打けるに、右妻上妻ヶ嶽と覚しき所にて光り段々薄く
なり、北国の方へ雲白く散たり、四日五日上州碓氷郡・群馬
郡・武州児玉郡之内、日中に闇夜の如く家々にて行
灯をともし、往還の旅人提灯を持、是浅間のけふり
なる故にか不思儀や、翌日の朝関八州は申に不及、信州・
加賀・能登・越中・越後・出羽・奥州迄白キ毛降事三寸
五寸或ハ壱丈余有もあり、昔慶安三寅年焼出しの節
諸国え毛降といふ事有、久安年中其外にも降たる
事年代記に見へたり、七日は別して鳴る事強く光り
地をうこかし大地震の如くに戸障子くハら/\となる、
(改頁)
山より北石とまり迄三度押出し、鎌原村にても先年の石
止り故に、夫より下へ押出す事あるましと只火石降事を
案し、人々は土蔵・岩の窟なと心かけ置し也、同七日晩
方より上州・信州山々嶽々より黒き雲浅間山へ布を
つるか如く、光りものハ東西へとひ、人のなりのことくなる物、
草津白根山・まんさ山へ飛たりといふこと疑なし、人々
天狗の仕業か外道のなす事ならんとて諸社にて祈る
事ありし也、同八日は朝より透間なく鳴事皆草
木迄も大風吹来る如くゆれわたり、神仏の石塔ゆ
りくつし、人之心持あしく諸仏・諸神へ祈誓せし処、
四つ半時分信州木曽の御嶽・戸隠山の辺より光り物
浅間か嶽へ飛入と見へしより山鳴動押出し、上州吾
妻川通り鎌原村を始として川北大前より川付村々
押通る事、第一番の水先黒鬼と見へしもの大地を
動し、家のかこひ初の森其外何百年共なく年を
経たる老木皆押くぢき、其音ハつなみ土をはき
(改頁)
たて煙をたてて震動雷電をなし、第二の泥火石
百丈余高く打上、青龍紅の舌を巻両眼日月の如く、
一時計闇夜にして大石の光りいかつち百万の震起
天地も崩るゝ計、火焔ほのふ空をつきぬく計、田畑
高めの場所不残只一面泥海の如く、何れの畑境か是
をしらす、老若男女共流死、未タ死すへき時も来らぬに
思ひかけなき天命泥海のみくつとなし、浅間の鬼神
生なからの人地獄へ進め、露の風に落る如く稲妻の
跡消たることく、誠に天変目を覚し大変前代未聞
夢のことし、
一 村々田畑泥五尺七尺壱丈余押埋、其中に火石有て
焼る事凡三十日余也、あハれ成哉、吾妻川附村々
流死人魂魄残り迷ひして、川筋沢辺ニて泣声
夜毎/\止事なかりし処に、寺々に至りて飯食
浄水をそゝき施餓鬼供養等追善の後は次第に
泣声やみしと也、
(改頁)
一 浅間山麓に往昔鬼住居有、慶長元申年に焼
失せしといふ、其頃奥州米沢の人と甲府之儀左衛門と
いふもの弐人此山に登り、大雨風頻りに吹来り、無是非
此堂に一夜を明せり、四月九日の事なりしか、其夜
四つ時女の形見へて彼堂に入らんとするを、黒赤の悪
鬼出て表へ引出し松の木にしめくゝし、釘ぬきにて舌を
はさみぬかんとする、彼女しく/\泣声聞あゝ恐ろしや
薪を寄て火を付其形炭の如くにして、亦元の如くに
せし也、何国より来りしか是も女の弐拾歳余なるを、此処
より峯のかたへ鉄の棒にて責登らんとす間もなく夜明
たりける、表の方何の気乗もなく、実にや世上の罪人此山ニ
登るといふ事疑なしと、右両国の人々信州へ下り、此事を
噺せしといふ、岩村田在の茂作といふ者の処に今にあり
堂は山より西の林処也、柳の井より壱丁程東に女人堂有、
貞享年中に武州江戸神田者三人此堂に休ける時、
頻りに黒雲出大雨風吹来東西を見失ひたりける、間も
(改頁)
なく雲はれけれハ三人の者壱人残弐人は行方しらす、是
非なく井の処迄下り見れハ、右同行弐人行倒て有しといふ、
又常陸土浦のもの四人にて此山に参詣せんとて遠見坂
迄登り、東小浅間か峯にて噺の声聞へたり、見れハ丈ヶ
壱丈余の僧白き浴衣を着て五人登り来る、皆々驚
井の下迄ひと欠に逃下り此事を噺しける、沓掛のもの共
夫は天狗といふものならんといへしと也、頃は宝暦十二年
三月廿八日の事とそ、
一 信州塩野村真楽寺ハ浅間大明神の別当なり、
一 上州鎌原村延命寺ハ浅間大明神の別当也、然処に
別当の論有之、宝永年中に出入有、上州・信州両国の
境山なる故に双方にて別当いたし、浅間大明神の配□は
両寺より是を出す、
一 信州浅間山の西南の麓普賢寺是は別当ニハ無之、
先年焼出し流失死人五百余人在之時節、此寺の真海と
いふ和尚出生ハ岩村田在之人なりしか、其節の大変流
(改頁)
死の内に母も変難に逢て流死なしけるをなけき、又
諸人をあハれみて施餓鬼せしと也、其時も七月八日
九つ時にて今に至る迄此寺におゐて毎年七月八日大施
餓鬼あり、
一 浅間焼出し吾妻川附村々、并御普請御役人村々
御旅宿御名前飢饉米相場書記す、一 天明三年癸卯年七月八日四つ八分時焼崩候次第事
[地図:左…狩宿新田ほか/右…大笹御関所ほか]
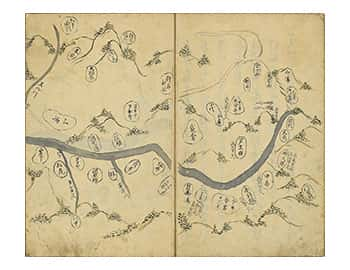
(画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。)
[地図:左…奥田ほか/右…厚田ほか]
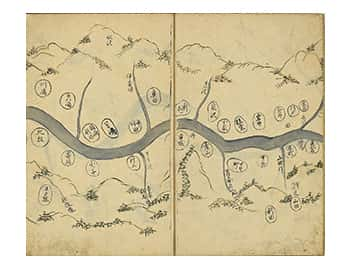
(画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。)
[地図:左…漆原ほか/右…南牧御関所ほか]
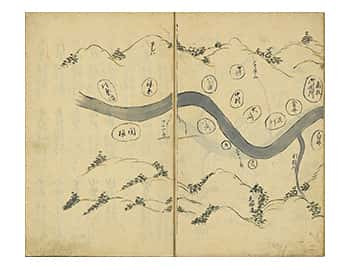
(画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。)
| 大笹 | 原田清左衛門支配所/少々荒場 |
| 西久保 | 同支配流家廿一軒/流死四十弐人 |
| 中居 | 同御支配/流死三拾六人 |
| 鎌原 | 同支配/流死四百八拾四人 |
| 赤羽根 | 同御支配/流死弐拾壱人 |
| 今井 | 深津弥市郎支配所 |
| 芦生田 | 古田五郎右衛門知行所(チキヤウ)/家不残 流死廿三人 |
| 勘場木 | |
| 半出木 | |
| 羽根尾 | 原田御支配流家/五十軒 流死廿人 馬九疋 |
| 林村 | 同御支配/流家拾壱軒 |
| 小宿 | 古田知行所 家不残/村中ニテ女壱人残ル/流死四十五人 |
| 立石 | クサ木原/流家三軒 |
| 坪井 | 伊丹雅楽之進支配所/流畑三十石余/流死八人 |
| 袋倉 | 古田知行所/流死拾壱人 |
| 長の原 | 原田御支配所流死(シ)/弐百十人内五十五人穢多 |
| 横壁 | 同御支配流畑/三十三反三畝十五歩 |
| 古森 | |
| 大前 | 原田御支配流家/百軒 流死三十四人 |
| 河原畑 | 同御支配/流死七人 |
| 河原湯 | 同御支配六十八石余/流死十七人 |
| 三嶋 | 同御支配流畑弐百七拾石余流死十六人/馬八疋流家五拾四軒 砂入十七軒 |
| 川戸 | 依田金十郎・伊丹雅楽之進・朝比奈左近・富永/二三千石四家知行所 流家十軒 人拾人 馬四疋 百石余 |
(改頁)
| 横谷 | 原田御支配 九十石余/流死拾壱人 馬廿六疋 |
| 青山 | 保科弁三郎知行所七十三石/流家拾七軒 馬四疋 |
| 市城 | 原田御支配/九十弐石 流家弐拾壱軒 |
| 村上 | 原田御支配 百八拾石内/廿三石知行所 流家十七軒/十三人 |
| 小野子 | 原田御支配 流家十七軒/壱人 馬六疋 |
| 新巻 | 小栗大学知行所/壱町四反 |
| 五町田 | |
| 箱嶋 | |
| 南牧 | 原田御支配/流死百三人 |
| 岡崎 | 原田御支配 |
| 祖母嶋 | 原田御支配/流家廿八軒 |
| 川嶋 | 同御支配/流家五拾軒 百廿八人 |
| 金井 | 原田御支配 |
| 渋川 | |
| 中村 | |
| 大崎 | 遠藤兵右衛門御支配所 |
| 厚田 | 依田金十郎・富永三平/知行所 流畑九拾石余/七人 馬四疋 |
| 松尾 | 原田御支配 十三町余/流家六軒 三人 |
| 郷原 | 原田御支配/流畑三拾石余 |
| 岩下 | 原田御支配 廿七町余/流家廿九軒 弐人 |
| 矢倉 | 原田御支配廿三町余/流家四拾軒 拾一人 馬十七疋 |
| 中之条 | 原田御支配/廿壱丁余 |
| 金井 | 保科弁三郎知行所/畑四畝八分 林三反六畝十九歩 |
| 原町 | 原田御支配 弐百拾六石内/四畝歩 東組流家拾六軒 |
| 伊勢町 | 保科知行所廿五町/流家弐軒 壱人 馬壱疋 |
| 岩井 | 保科知行所 八畝歩/流死壱人 |
| 植栗 | 古屋備前知行所/弐町余 |
| 小泉 | 小栗大学知行所/弐丁余 |
| 泉沢 | 朝比奈左近知行所/壱石五升 |
村高壱万九百八拾五石九斗七升弐合七勺
田畑荒高吾妻郡廿八ヶ村、群馬郡四ヶ村都合三拾弐ヶ村、
三千五百五拾三石四升五合也
此反別四百九拾四町三反弐畝拾三歩
高七百七石四斗五升五合
(改頁)
田反別五拾七町六反四畝弐拾歩
高弐千八百四拾五石八升九合
畑反別四百三拾六町六反七畝廿三歩
一 流家九百三拾五軒 弐拾弐ヶ村
一 流死人九百三拾四人 馬三百八拾五疋 内四百四拾三人男 四百九拾壱人女
一 流家残惣人数飢人数三千百五拾弐人 内千七百七拾六人男 千三百七拾六人女
吾妻川附私領村々
一 流家弐百五拾九軒 但吾妻・群馬合弐拾ヶ村
一 流死人四百三拾九人 馬百廿弐疋
御料私領惣〆
流家千百九拾四軒
流死人千三百七拾三人
馬五百七疋
一 信州・上州・武州灰砂泥火石、用水往還悪水除
御普請場所御役割御旅宿村々左之通
上州群馬郡渋川旅宿
(改頁)
御勘定吟味役 根岸九郎左衛門
同 組頭役 豊田金右衛門
同 田口五郎左衛門
御普請役元〆 早川富三郎
御普請役 大西栄八郎
御吟味下役 吉浜佐七郎
同所大崎旅宿 御普請金割元
御代官 遠藤兵右衛門
吾妻郡大笹旅宿
御勘定 古川五郎兵衛
御普請役 蓮見音次郎
同 萩野文吾
大笹・鎌原・小宿・大前・西久保・中居・赤羽根・勘場木・
芦生田・袋倉・古森・能谷・新井・横壁・河原湯・
三嶋・厚田・川戸・金井
同郡原町旅宿
(改頁)
御勘定 久保田進十郎
御普請役 長岡文兵衛
同 関文次郎
今井・立石・羽根尾・坪井・長原・川原畑・林村・横谷
松尾・岩下・矢倉・郷原・原町・中之条・伊勢町・平村
青山・市城・村上
群馬郡金井旅宿
御勘定 萩野伊右衛門
御勘定 久保田進十郎
御普請役 長岡文兵衛
同 関文次郎
岩井・植栗・泉沢・小泉・新巻・奥田・五丁田・箱嶋・
岡崎新田・祖母嶋・川嶋・南牧・小(北歟)牧・小野子・次屋・
白井・惣津・渋川
碓氷郡原市旅宿
御勘定 篠山十兵衛
(改頁)
御普請役 三谷佐市兵衛
同 下妻郡次郎
砂場三拾三ヶ村組合、外砂除村六ヶ村組合、外九ヶ村
組合、外四ヶ村組合
同郡中宿旅宿
御勘定 川勝多四郎
御普請役 仲田藤蔵
同 小川喜一郎
水口秋間より軽井沢・南地井・沓掛・落合・下仁田辺、
右は砂除道用水往還道引、原市・八本木・平塚迄
拾ヶ村組合、外三ヶ村組合、外四拾五ヶ村組合
武州榛沢郡中瀬旅宿
御勘定 羽倉権九郎
御吟味役 飯泉秀蔵
同 松浦勇吉
御勘定 橋爪領助
(改頁)
御普請役 岡野滝次郎
同 町田長三郎
川除八町河原迄組合拾壱ヶ村組合、外八ヶ村組合、
外廿壱ヶ村組合、八斗嶋廿三ヶ村組合、武州児玉郡
用水新井・下ノ室外六ヶ村組合、仁手外六ヶ村
組合、川除中瀬・谷ヶ嶋十三ヶ村組合、外拾壱ヶ村
組合、谷ヶ嶋・郷原五ヶ村組合、用水江波・八つ口・上
次戸拾三ヶ村組合、外十三ヶ村組合米堀之内
四ヶ村組合
武州児玉郡渋上村旅宿
御勘定 中村丈右衛門
御吟味役 吉川栄左衛門
御普請役 近藤市蔵
同 和田繁蔵
下奈良・四万・惣堀・上次戸四ヶ村組合、外弐ヶ村
組合、川除中村・番保原七ヶ村組合
(改頁)
勢田郡前橋町旅宿
御勘定 飯塚安左衛門
御普請役 石田儀左衛門
同 渡辺文平
御勘定 飯塚安左衛門
御普請役 石田儀左衛門
同 渡辺文平
用水六拾四ヶ村組合往還玉村之内
同所旅宿
御勘定 野田文蔵
御普請役 市野伊之進
同 若田喜内
同 長持武兵衛
川除往還用水砂六拾八ヶ村組合
同郡平塚村旅宿
御勘定 吉岡金次郎
御普請役 関根市三郎
同 桜井甚兵衛
道用水砂五拾八ヶ村組合
(改頁)
同所旅宿
御勘定 谷瀬兵衛
御普請役 山本亦助
同 祖母井定次
五拾壱ヶ村組合石砂除計
緑埜郡浄諸寺旅宿
御勘定 桜井徳左衛門
御普請役 加藤粂次郎
同 荻野大八
同 保田藤市
川除用悪水路九ヶ村組合、外四ヶ村組合、外
七ヶ村組合、外八ヶ村組合
同所旅宿
御勘定 栗原礼助
御普請役 豊田長次郎
同 屋計文十郎
(改頁)
飯塚用土拾八ヶ村組合、外五ヶ村組合、九ヶ村組合、
外四ヶ村組合
榛沢郡深谷旅宿
御勘定 篠田五郎左衛門
御普請役 植野直次
同 永井久次郎
御吟味役 小嶋伊右衛門
緑野郡川除用悪水路砂共ニ三拾三ヶ村組合、外
三拾三ヶ村組合、外拾五ヶ村組合砂除計
同所旅宿
御勘定 三宅源兵衛
御普請役 鶴田宇之助
同 中村弥十郎
緑野郡川除用悪水路無不附十四ヶ村砂場組合、
外五拾五ヶ村組合砂除計往還用水砂共ニ、外用
水砂拾ヶ村組合
(改頁)
一 御普請出来永見分辰正月九日御駕着
御十人目附 柳生主膳正
御徒士目附 宮田重左衛門
同 三宅権七郎
同 堀谷文右衛門
同 向山長右衛門
同 大嶋半左衛門
同 川崎市三郎
御小人目附 平嶋西右衛門
同 金井定四郎
同 豊田源八郎
同 山崎弥市右衛門
同 内田辰右衛門
同 近藤亀次郎
同 加瀬彦市
同 石井伊八郎
(改頁)
同 須藤徳次郎
同 秋山仁三良
同 井上友作
同 高崎和吉
同 小池定八
一 御普請御手伝細川越中守
御家来 白杉少助
同 上羽蔀
右普請都合七百三ヶ村御手伝御旅宿上州
渋川良珊寺
一 卯四月より度々灰降、桑の葉にかゝり水にてあらひ
ける、蚕の毒にもならすしかもまゆ半吉也
一 七月十三日八月朔日泥降諸作草木迄枯たり稗少々
実あり
一 同年正月元朝より鶏の羽音なく時をつくる、
一 同九月群馬郡三ノ倉・宝田・中村、武州児玉郡後瀬村之内梨子の花、林檎の花咲、
(改頁)
同年十一月上州群馬郡村上・小野子・本宿山つゝしの
花ひらく、
一 吾妻三原山にて五六月鹿の鳴声度々あり、
一 同郡三嶋村之内にて十月青穂出しとなり、
一 武州榛沢郡之内にて十月桑之実なりしと也、
一 奥州にて八月雪弐尺九月壱尺七寸降しと也、
一 七月四日朝八月五日朝日輪紅の如し、
一 奥州出羽之内七月三日之朝日輪二タ面見へしと也、
一 上州碓氷郡之内にて柿の花九月ひらくと也、
右陽気不順之事ハ土を動し、煙日々に雲の如く
なる故に、照り薄く土ひゆるか、又ハ灰砂降諸作の
花の実に硫黄灰の毒なるか、万物雨露のほと
こしを得て、春夏秋の花咲実のる事、天地自然
の地意気なる処に、陰強く陽薄しと見へたり、
世に奢甚成故に天変天下に此事をあたへらんとや、
むかし元暦・延宝申酉の飢饉、元文・寛文の大風、
(改頁)
宝永富士の砂、丑年の洪水、寛保戌の大水、九州
あその焼出し、其外山崩変飢饉有しといへとも
何れの村々にても其事を記しをかす、古人の言伝
計にて、事わかりかたし、依而是を記すもの也
浅間大変前後惣穀之相場左ニ記
金壱両ニ付銭五〆五百文
卯七月
一 白米百文ニ付壱升四合
一 大麦壱両ニ付弐石三斗
一 小麦百文ニ付壱升八合
一 大豆百文ニ付弐升壱合
一 素麺百文ニ付三百五拾目
一 小豆百文ニ付弐升壱合
一 ひへ壱両ニ付弐石九斗
惣而是に順す
八月
一 白米百文ニ付壱升
一 大麦壱両ニ付壱石六斗
一 大豆百文ニ付壱升四合
一 小麦百文ニ付壱升四合
一 小豆百文ニ付壱升三合
一 素麵百文ニ付三百三拾目
九月
一白米百文ニ付壱升
一大麦壱両石四斗八升
一大豆百文ニ付壱升三合
一小麦百文ニ付壱升三合
(改頁)
一 小豆百文ニ付壱升弐合
一 素麵百文ニ付三百目
十月
一 白米百文ニ付壱升壱合
一 大麦壱両ニ付石六斗八升
一 大豆百文ニ付壱升三合
一 小麦百文ニ付壱升弐合
一 小豆百文ニ付壱升壱合
一 素麵百文ニ付弐百九拾目
十一月
一 白米百文ニ付壱升壱合
一 大豆百文ニ付壱升三合
一 大麦壱両ニ付壱石弐斗五升
一 小麦百文ニ付壱升壱合
一 小豆百文ニ付壱升弐合
一 素麵百文ニ付弐百九十目
卯十二月
一 白米百文ニ付九合
一 大豆百文ニ付壱升弐合
一 小麦百文ニ付壱升
一 小豆百文ニ付壱升
一 大麦壱両ニ付壱石四斗
一 素麵百文ニ付弐百五拾目
辰正月
一 白米百文ニ付八合
一 大豆百文ニ付壱升弐合
一 大麦壱両ニ付六斗四升
一 小豆百文ニ付九合
一 小麦百文ニ付壱升弐合
一 素麵百文ニ付弐百四拾目