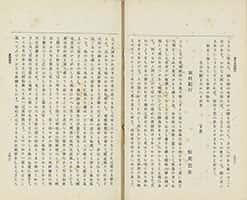画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。
更科紀行
さらしなの里、姥捨山(おばすてやま)【注2】の月見ん事、しきりに進むる秋風の、心に吹さわきて、共に風雲の、情をくるはす者、又ひとり越人(えつじん)【注3】と云。木曾路は山深く道さかしく、旅寐(たびね)の力も心もとなしと、荷分(兮)子(かけいし)【注4】が奴僕(ぬぼく)をしておくらす、自々(おのおの)心さし盡(つく)すと雖(いえど)も、驛旅の事心得ぬ樣にて、共におぼつかなく、物事のしどろに跡先なる【注5】も、中々におかしきこと而巳(のみ)多し。何々といふ所にて、六十(むそじ)ばかりの道心(どうしん)の儈、面白けもなくおかしけもあらず。只むつ/\としたるが、腰たわむまで物負ひ、息はせわしく、足はきさむ樣に歩み來れるをともなひける。人の衰れがりておの/\肩にかけたるもの共、彼儈の負ぬ物とひとつにからみ、て(からみて、)馬に付て、我を其上に乘す。高山奇峯頭の上におほひ重りて、左は大河ながれ、岸下の千尋(せんじん)の思ひをなし、尺地(せきち)【注6】もたいらかならざれば、鞍の上靜ならず。只あやうき煩(わずら)ひのみ休(や)む時なし。棧橋(かけはし)【注7】寐覺(ねざめ)【注8】など過ぎて、猿ヶ馬塲(さるがばば)、たち峠などは、四十八曲とかや、九折(つづらおり)重なりて、雲路にたどる心地せらる。步行(かち)より行ものさへ、眼くるめき、魂しほみて、足定まらざりけるに、彼の連たる奴僕、いとも恐る〻氣色見へず。馬の上にて只ねふりに眠りて落ぬべきことあまた〻び成けるを、後より見上けて、危きことの限なし。佛の御心に、衆生(しゅじょう)の浮世を見玉(みたま)ふも、か〻る事にやと、無常迅速(むじょうじんそく)のいそがわしさも、我身にかへり見られて、阿波の鳴門は、波風もなかりけり。夜は草の枕を求て、晝のうち思ひまうけたる景色、むすび捨たる發句(ほっく)など、矢立(やたて)取出て、燈(ともしび)の下(もと)に目をとぢ、頭を叩きてうめき伏せば、彼道心の坊、旅懐(りょかい)のこ〻ろうくて、物思するにやと推量し、我をなぐさめんとす。若き時おがみ廻りたる地、阿彌陀の尊き數(かず)をつくし、己があやしと思ひし事共は、な(、はな)しつゞくるぞ風情(ふぜい)のさわりとなりて何を云出(いいいづ)ることもせず。兎(と)てもまきれたる月影の、壁の破れより木の間がくれにさし入て、引板(ひた)【注9】の音、鹿おふ聲(こえ)、所々に聞へける、まことにかなしき秋の心、爰(ここ)に盡(つく)せり。いてや月のあるじに、酒振舞んと云へば、盞(さかづき)持出たり。よのつねに一廻(めぐり)もおほきに見へて、ふつ〻かなる蒔繪(まきえ)をしたり。都の人は、か〻るものは風情なしとて、手にも
ふれさりげるに、思もかけぬ興に入て、〓(王+靑)碗玉巵(せいわんぎょくし)【注10】の心地せらる〻も所から也。
あの中に蒔繪(まきえ)かきたし宿の月
棧(かけはし)やいのちをからむ蔦かつら
棧(かけはし)や先おもひいつ駒むかへ
霧はれて棧(かけはし)は目もふさがれず 越人
姥捨山(おばすてやま)
俤(おもかげ)や姨(うば)ひとりなく月の友
いさよゐ(十六夜)もまた更科の郡(こおり)かな
ひよろ/\と尙(なお)露けしや女郎花(おみなえし)
身にしみて大根からし秋の風
木會の橡(とち)浮世の人のみやけ哉
送られつ別れつ果(はて)は木會の秋
月影や四門四宗(しもんししゅう)も只一つ
吹とはす石は淺間(あさま)の野分(のわき)かな
さらしなや二(三・み)よさの月見雲もなし 越人
【注1】
江戸時代前期の俳諧師で、伊賀国阿拝郡(現在の三重県伊賀市)出身。後世では「俳聖」として広く知られ、日本史上最高の俳諧師の一人とされている。特に紀行文『奥の細道』が有名である。
【注2】
さらしなの里は、現在の長野県千曲市および埴科郡戸倉町付近を指す。この地域ある冠着山(かむりきやま)は、通称「姥捨山(おばすてやま)」としても知られている。この名前は、昔、歩けない老人を奥山に捨てるという伝説「姥捨て山(うばすてやま)」に由来する。
【注3】
越人は越智十蔵の号。越人は、越後出身の尾張蕉門の重鎮で、松尾芭蕉『更科紀行』に同行し、そのまま芭蕉と共に江戸まで同道した。
【注4】
荷兮は山本周知の号で、子は敬意を示す語。荷兮は尾張の医者で、尾張蕉門の重鎮であったが、内紛によって後に袖を分かった。
【注5】
物事の順序が混乱して要領を得ないこと。
【注6】
一尺ほどの狭い土地。
【注7】
木曽街道最大の難所で、上松町・木曽福島町の間の木曽川の崖っぷちに掛けてあった棚橋。
【注8】
寝覚めの床。巨岩に木曽川の急流が激突して水飛沫を上げていたらしい。木曽街道きっての観光名所であった。
【注9】
獣や鳥を追い払う鳴子のこと。
【注10】
立派な器物などのこと。