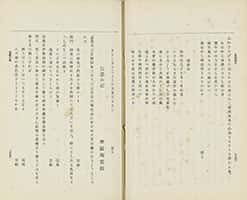画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。
信濃の記
信濃の記 摩詰庵雲鈴(まきつあんうんれい)【注1】
(前畧)今日(正德四年三月十三日)は空の氣色心にまかせず、笠の端のはら/\としければ
花の雨先づ門出から降か〻り 雲鈴
關川【注2】 燒食に味噌ぬりたるを此國にてけんざいと云ふ。串にさしたる名目なるべし、之を二つ持出る
けんさ井はとかめし關の花盛り 凉菟(りょうと)【注3】
燒食に魂いくつさくらがり 雲鈴
凉菟は伊勢山田の神主にして號を神風館或は團友齊と云ふ
野尻 暫(しばら)く茶店に休みて湖水を眺め侍(はべ)りけるに、此所の名物とて櫻うぐゐと云(い)ふ魚を主の出しければ
酒うけてうくゐ一つもさくらなり 凉菟
みづ海の景色はさくらうぐゐかな 雲鈴
善光寺 岡田未格(みかく)【注4】亭
そのまことあらはす色や春の山 凉菟
如來堂にまうで〻
生て花に此內陣ぞありがたき 雲鈴
戶隱山(とがくしやま)【注5】に詣行程五里、山に山を尋ねて、さかしき岩根を傳ひ、半腹にのぼれば、後は飛彈信濃の國をかぎりて雪の山まばゆき程に照りわたり、麓は春の半をあらはして、草靑々櫻盛也夫れより神前にぬかづき、奥の院に詣づ、其道一里、雪はたちまちに脛(すね)の上こして、家は何所にあるとも見えず、老人云されば此御神の爰(ここ)に立たせ給ふ事は有がたき故あるべし、と聞けば信心今更地
神々し戶隱の花は松ひのき 凉菟
戶かくしの尙奥ふかし雉子(きじ)のこゑ 雲鈴
川中嶋 あなたこなた見渡せば西條山里みたり見こそ古戰塲とかや
其時の車か〻りやとぶひばり 雲鈴
一そなへあれにも山の櫻かな 凉莬
姨捨山(おばすてやま) 今日は曇りかちにて定かならぬ景色なるを登りて見れば雨奇晴好とかや云も此あたりの事なるべし
姨捨(おばすて)や曇るといふは花の事 凉菟
姨捨(おばすて)の山の匂ひやわらびまで 雲鈴
打かへす田毎に見るや笠のかげ 同
月花の名をさらしなや我がこ〻ろ 凉莬
一本松と云ふ峠にのぼれば、冠着(かむりき)か嶽は笠の端にならへ見ゆ、雨に風にあらましくなりて、駒の足は雲を分る心地なり、柏崎より贈りし堅甲(けんこう)の花簦(はながさ)もあやうく麓に下り、麻績(おみ)と云ふ所に泊り、枕引よせて、浮世の思ひにはなりぬ、
淺間温泉 犬飼(いぬかい)の御湯(みゆ)【注6】とかや此所にてしばらく旅のつかれを浴て
夜の花に湯の湧くをけや枕もと 凉莬
つ〻じ藤勾ふ淺間や湯のけむり 雲鈴
善光寺の末格か本より傳したるよしにて、松本の府より、游潮と云ふ人、つかふ可き物ども、した〻めさせ來て、宵の間の物語し、やがて其所にも待べき約束して歸る
花折てつとにうくゐのかざしかな 游潮
松本 天神の松原と云ふ所に席を設て奥行
ゆふ/\と松のしげりや神の馬塲 凉莵
此松風は都より通ふかとあやしき程也
春風のこ〻にも松や南禪寺 雲鈴
宿房は木立寺に遊ん
雲水の便にもとて、此國のは〻木の枝きりて雲鈴に餞す
は〻き木の枝の茂りや和歌の友 聖人日觀
留別
卯の花の寺を見歸る夜明かな 雲鈴
信あれば德あり花の靑葉まで 凉莵
櫻澤【注7】といふ所を過る、是こそ木曾の麻衣とよみける尾張領とかや
橋こえて見かへる春や櫻澤 凉莵
直江津の過角が餞別に木曾の寒さを申侍(はべ)るは此事なるべし
是れ一つちかふ木曾路の袷(あわせ)哉
贄川 此所の時楓は風雅の聞えあり、まして神道をおろそかにせず、たのもしき主也
時鳥(ほととぎす)そなたに鳥居峠あり 凉莵
(下略)
【注1】
吉井雲鈴。江戸前期から中期の俳人で、摩詰庵と号す。雲鈴は、陸奥盛岡藩士だったが、その後僧となり、俳諧を森川許六(きょりく)などに学んだ。元禄13年(1700)、大坂から北上して佐渡に滞在し、その後、南下して京都にいたるまでの紀行「入日記(いりにっき)」を刊行した。
【注2】
關川 長野県境に位置する新潟県関川村(現在の妙高市)。江戸時代には北国街道の宿場として栄え、関所があった。
【注3】
岩田涼菟。江戸中期の俳人で、伊勢の生まれ。涼菟は、初め伊勢神宮の下級神職となったが、後に松尾芭蕉の晩年の門人となり俳諧を学んだ。各務支考(かがみしこう)らと親交を持ったことにより、「伊勢派」と呼ばれる新しい作風の俳諧を生み出した。
【注4】
善光寺町の俳人。
【注5】
長野県長野市にある山で、信州百名山および北信五岳の一つとして知られている。古くから修験道の道場で、山の中腹には戸隠神社があり、古くから信仰の対象となっている。明治の廃仏毀釈が行われるまでは、戸隠神社に聖観音菩薩が祀られていた。
【注6】
長野県松本市にある浅間温泉の古名。この地名は、平安時代に編纂された『拾遺和歌集』に記載されているが、その具体的な場所については諸説ある。
【注7】
桜沢は、木曽路の入り口に位置する集落で、「是より南木曽路」という石碑が建てられている。桜沢は、本山宿と贄川宿の間の宿(あいのしゅく)として栄えた。