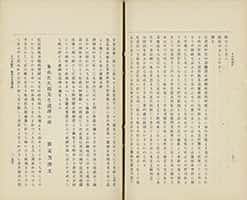画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。
象山佐久間先生遺澤の碑
象山佐久間先生遺澤(いたく)の碑 勝安芳(あわ)【注1】撰文
信濃國【注2】高井郡佐野村はもとの松代領なり此地よも(四方)に山めくりそかうち平にての〻かたちまとかなりゆへに艸木(草木)茂りことによねつくるによろし其民おのつからすなをにして古の風を存せり象山佐久間翁【注3】藩に在せし時いたく此地をめて(愛で)やかて住はやと思はれけむ詩に詠し文を賦して其志をよせられけらしまた郡治の獘せる(弊害)民の苦を察してしは/\其主に申いたく攻た〻されし事共あり是等のこといまはむかしと成りしを此民誠ある心から猶其惠(恩恵)をた〻へてやます終に石にゑりて其澤を永く世に傅(伝)へむとはかり予か一言を乞ふ予もまた其まこころに愛て拙を忘れ其需(じゅ:もとめ)に應(応)するに南牟
明治十二(1879)のとし初秋海舟勝安芳誌(しるす)
【注1】
勝安芳(あわ)
幕末・明治の政治家。下級幕臣勝小吉の長男で通称麟太郎、名は義邦、海舟は号。海軍操練所の設立や西郷隆盛との江戸無血開城など、近代国家樹立へ尽力し、激動の幕末から明治にかけ日本のために奮迅(ふんじん)した幕臣。妹のお順(順子)は幕末の思想家佐久間象山の妻になった。
この碑は、勝海舟が、盟友で妹婿にあたる佐久間象山の佐野村に遺した業績をたたえたもので、長野県下高井郡山ノ内町佐野(長野電鉄湯田中駅から徒歩15分)にある。
【注2】
現在の長野県
【注3】
佐久間 象山(さくま しょうざん/ぞうざん)は、江戸時代後期の松代藩士、兵学者・朱子学者・思想家。通称は修理(しゅり)、諱は国忠(くにただ)、のちに啓(ひらき)、字は子迪(してき)、後に子明(しめい)と称した。位階は贈正四位(1889年)[1]。象山神社の祭神。象山神社の隣が生家で、長野県の史跡に指定されている。
36歳の時、松代藩から三村利用掛(湯田中・沓野・佐野)を命じられ、新田開発・治水植林・築堤の改良・温泉場の 改善鉱物採掘等軽く見積もっても1万石の増収は図られたといわれる。
藩財政窮乏の折り、さらに充実すべきところ、家老の反対にあって実現することが出来なかった。『沓野日記』を残している。