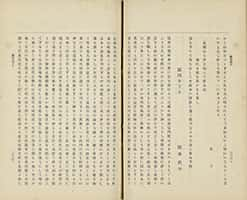画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。
犀川を下る
犀川(さいがわ)を下る 松本君平(くんぺい)【注1】
筑摩(ちくま)の都、松本の里に足を留むる三日、或る時は殷富門院(いんぷもんいん)【注2】か「わきかへりもえてそ思ふうき人は束間(つかま)【注3】のゆけ(湯気)か富士のけふり(煙り)か」と詠したりし淺間の湯泉に浴して世の憂きを忘れ或る時は宇摩伎か過きて「武士の草むす屍とし古りて秋風寒し桔梗ヶ原(ききょうがはら)」と觀したる古戰塲に遊ひてすきし昔を忍ひぬ然れとも吾は長く此地に足を留むへき身にしあらねは十一日の未明朝風寒く堪難(たえがた)かりしも吾か姓に因(ちな)む松本に名殘惜くも別れを告けて旅立ちぬ這度(このたび)は保福寺峠(ほうふくじとうげ)の途(みち)をは取らて犀川(さいがわ)を下りて見んと同行の人と便舟に搭してけり犀川(さいがわ)は源を筑摩(ちくま)の郡に發して越後に流る〻信州四大河の一にて松本より長野に出る旅客の犀川(さいがわ)の便に由る人も少からず松本の町端れより奈良井川(ならいがわ)に沿うて行く程に梓川(あずさがわ)と合する所よりして犀川(さいがわ)とはなるなり奈良井川(ならいがわ)を下る中は河底も淺く水も少なく舟の淺瀨にのり上けて困りし事も數々なりしか犀川(さいがわ)に入りてよりは水の流れも極めて駛(はや)く舟路も矢を射る如くなり文人墨客(ぶんじんぼっかく)の富士川を下りて其両岸の風景を賞し川舟の快走を説くものは世に多きも未た信濃に遊ひて犀川(さいがわ)を下りて其驚くへき山川の美を觀稱するもの少なきは遺憾なり吾れ此流を下りて初めて其天下に山水の秀麗あるを知れり吾昨年二回富士川を下りて其奇絶(きぜつ)を稱したりき今端(はし)なく【注4】此地に來て更に富士川に優るとも劣らさる江流を發見しぬ犀川(さいがわ)の流に沿ふ山光壑(がく)色の瑰奇(かいき)なるは楮墨(ちょぼく)の能く盡(つく)す所に非す」舟行愈々(いよいよ)遄(はや)くして山色愈々(いよいよ)妙なり峯白く水淸く時々刻々に變り行く両岸の勝景は錦眼鏡(にしきめがね)【注5】を覧るか如く蜀江(しょっこう)の畵卷を展(ひろげ)るに似たり犀川(さいがわ)に沿ふて下ること五六里咄咄(とつとつ)【注6】俄然として破天荒の景象に接したり両岸忽(たちま)ちにして噛むか如く合し來り左岸を觀れは崔嵬(さいかい)たる絶壁高く天半(なかぞら)に聳立(しょうりつ)し削るか如く劈(さく)るか如く百尺の刄を握るか如く千枚の屏を列するか如く巨巖盤石の狀渴驥(かっき)躍り天猊(てんげい)驅けり狂風大空に吠ゆるに似たり幾百歲を經過せる老松怪柏(ろうしょうかいはく)は根を其間に托(たく)し
て欝生(うっせい)唯た造化翁(ぞうかおう)【注7】偶意配合の怪幻に驚くのみ右岸を観れは嵯峨たる奇峯峻岳は疊々(じょうじょう)として剛に頂門上に落ち來らんとす滿山の樹木盡(つ)く雪に蓋(おお)はれ冷絶又奇絶逼視(ひっし)すへからす其間に飛瀑あり棧道あり深々たる碧水は緩く縈(めぐ)りて其下を流る一葉の輕舟に棹して其間を過く赤壁の奇謂(い)ふに足らす剡溪(えんけい)の遊何か有ん舟中の人皆立ちて「猗搓(ああ)々々」と嘆稱するのみ吾は唯々驚くへき這(この)の自然の美に醉ふて嗒然(とうぜん)吾を忘る〻のみ是は此れ山淸地一帯の概勝(勝概・すぐれた景色)なりけり更に一大曲折して河流を下れは歘(たちま)ち又驚く可き異様の山水に逢ふ合したる両岸は開張し巖石は削られて古城の如く森欝(しんうつ)たる松柏は霜雪を凌て立ち丹楓(たんふう)翠竹(すいちく)其間に點綴(てんてい)して幽逸(ゆいつ)の景致掬(きく)すへし河流の中央に一個の巨巖其狀臥龜の如きものあり舟人指して龜石なりといふ之を下山淸地の形勝となす若し文豪韓蘇【注8】の如きもの筆硯を携へて此に來らは舟を留めて一大詩賦を草せすして止まんや若し墨妙倪黃(ぼくみょうげいこう)【注9】の如きの徒の丹靑を載せて此に抵らは一代を推倒する自然の美を畵かすして空しく過きんや吾は詩人に非す美術家に非す此に來て宏壯雄大ある自然を感して徒らに此の絶美の歌はれす畵かれさるを愛しむ耳」是の如く山と水の絶景の裡(うち)に埋もれて過くること更に六七里日は暮れたり自然の丹靑る亦見えすなりぬ映するものは両岸の雪のみ聞ゆるものは吾を流し行く潺湲(せいかん)【注10】たる水音と哀れ氣に謳(うた)の篙師(こうし)【注11】か欵乃(あいだい)【注12】の歌のみ冬の夜の川風寒く膚に砭(いしばり)す正に是れ巴峡(はきょう)猿聲【注13】の感に堪へす新町と云へる寒村に着きしは宵の六時頃にてありき此宵一夜の假寝の夢を結ふへき宿を尋ねて泊りぬ溪川の鼓うつ如き音に吾夢は屢々(しばしば)破れぬ明くれは十二日都に歸る旅路の急かれてけり後京極(ごきょうごく)【注14】か「吾妻より今日逢阪の山越えて都に出つる望月の駒」と詠せしも今は吾身につまされて今日は吾妻に歸るそと駒に鞭あて四里にも餘る雪の山路を急きけり更科の里なる篠の井の停車塲に著(つ)きぬ
【注1】
静岡県出身のジャーナリスト、政治家、教育者、思想家。文学博士、衆議院議員。遠江国小笠郡中内田村(現在の静岡県菊川市)に生まれる。政界を引退し青年教育に取り組んだ。
【注2】
後白河天皇の第1皇女。亮子内親王。伊勢斎宮を勤め、寿永1(1182)年に安徳天皇の准母として皇后となった。文治3(1187)年6月に院号宣下、殷富門院と称した。
【注3】
古くは「束間(つかま)の温湯」と呼ばれ、日本書紀にも記された歴史ある温泉地。
【注4】
思いがけなく、偶然であるさまを表わす。
【注5】
玩具の一つ。円筒形の筒の中に、種々の色のガラスやセルロイドの小片と三角に組んだ鏡を入れて、端の小さい穴からのぞくと、模様が種々に変化して見える仕組みののぞき眼鏡(めがね)。万華鏡。
【注6】
怒ったり驚いたりするさま。また、怒りや驚きのために声を発したり舌打ちをしたりするさま。
【注7】
宇宙・万物を創造した神。
【注8】
韓は唐時代を代表する思想家・詩人である韓愈(かんゆ)で、蘇は北宋時代の政治家・詩人・書家である蘇軾(そしょく)のことである。
【注9】
墨妙は文章や書画にすぐれていること。倪黃は、中国元代の書家である倪瓚(げいさん)と水墨画家の黄公望(こうこうぼう)のことである。
【注10】
さらさらと水の流れるさま。
【注11】
舟を操るのに巧みな者。船頭。
【注12】
舟の艫(ろ)のきしる音。また、船に棹(さお)さす時に掛ける声。転じて、船人のうたう歌。船頭歌。船歌。棹歌。
【注13】
中国湖北省巴東県の巴峡(長江の三峡の一つ)には猿が多く、とくに舟旅で聞くその鳴き声は古来、哀愁をさそうものとされていた。
【注14】
後京極摂政前太政大臣九条良経(くじょうよしつね)。和歌、書道、漢詩に優れた教養豊かな人物で、九条家の2代目として歌人の後援にも力を尽くした。