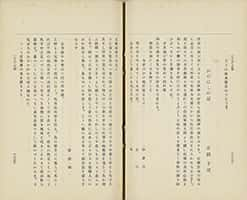画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。
かけはしの記
かけはしの記 正岡子規【注1】
浮世の病ひ頭に上りては哲學の研究も感病同源の理を示さす。行脚雲水(あんぎゃうんすい:行方を定めず思うままに旅すること)の望みに心空になりては俗界の草根木皮(そうこんもくひ)畵(画)にかいた白雲靑山ほとにきかぬもあさまし。腰を屈めての辛苦艱難(しんくかんなん)も世を逃れての自由氣儘(きまま)も固より同し煩惱(はんのう)の意馬心猿(いばしんえん:人間の欲情の自制しがたいことのたとえ)と知らぬが佛(仏)の御力を杖にたのみてよろ/\と病の足もと覺束(おぼつか)なく草鞋(わらじ)の緒も結ひあへでいそぎ都を立ちいでぬ。
五月雨に菅の笠ぬぐ別れ哉
知己(ちき)の諸子はなむけの詩文をたまはる。
時鳥み山にこもる聲(声)き〻て
五月雨に菅の笠ぬぐ別れ哉
木曾のかけ橋打渡るらん 伽羅生
卯の花を雪と見てこよ木會の旅。 古白
山路をり/\悲しかる可(べき)五月哉。 同
又碧梧桐子【注2】の文に
日と雨を管笠の一重に擔(担)ひ山と川を竹杖の一端にひつさげ木賃を宿とし馬子を友とし浮世の塵(ちり)をはなれて仙人の二の舞をまねられ單身(単身)岐蘇路(木曽路)を過きて焦れ戀(恋)ふ故郷へ旅立ちさる〻よし嬉しきやうにてうれしからず悲しきやうにて悲しからず。願はくは足を強くし顔を焦(こが)して昔の我君にはあらざりけりと故郷人にいはれ給はん事を。山ものいはず語らず。こ〻に贐(はなむけ)の文を奉りて御首途(かどで)を送りまゐらす
五月雨や木曾は一段の確永嶽。 碧梧桐
上野より滊車(汽車)にて横川に行く。馬車笛吹嶺(うすいとうげ)を涉る。鳥の聲(声)耳元に落ちて見あくれば千仭(せんじん)の絶壁、百尺の老樹、聳(そび)え/\て天も高からず。樵夫(きこり)の歌、足もとに起つて見下せば蔦かづらを傅(伝)へて度るべき谷間に腥(なまぐさ)き風颯(さっ)と吹きどよめきて萬(万)山自ら震動す。遙(はる)かにこしかたを見かへるに山又山峩々(がが)として路いづくにかある。寸馬豆人のみがかれかと許(ばか)り疑はれて
つ〻ら折幾重の峯を渡りきて
雲間にひくき山もとの里
日もや〻暮れか〻れは四方濛々(もうもう)として山とも知らず海とも知らず。かけ上る駒の蹄(ひづめ)に踏み散らす雲霧のあはひを見れば一步の外巳に削りたてたる嶮崖(けんがい)の底もかすかなることおそろし。登れども登れども極まる處(所)を知らず。山ます/\高く雲いよ/\低し。
見あぐれば信濃に續(続)く若葉哉。
輕井澤はさすがに夏猶寒く透間もる淺間おろしに一重の旅衣、見はてぬ夢を護るに難かり。例ならず疾く起きいで〻窓を開けば幾重の山嶺屏風を遶(めぐ)らして草のみ生ひ茂りたれば其色染めたらんよりも麗(うる)はし。
山々は萠黄(もえぎ)淺黃(あさぎ)やほと〻きす。
淺間は雲に隱れて煙もいづこに立ち迷ふらんと思はる。滊(汽)車を驅(か)りて善光寺に詣づ。いつかの大火に寺院はおろかあたりの家居まて扨(さて)も燒けたりや燒けたり。千歲の松も限りあればや昔の綠乍ち(たちまち)消えうせて木も枝もやけこがれさも物うげに立てるあはひに本堂のみ屹然(きつぜん)として聊(いささ)かも傷はさるは浪花堀江の御難をも逃れ給ひし御佛の力、末世の今に至るまで變(変)らぬためしぞかしこしや。
あれ家や茨花さく臼の上
又川中島を過ぎて篠井まて立戻る。古戰塲はいづくの程とも知らねと山と山とに圍(囲)まれて犀川の廻るあたりにやあらん。河の水はいたく痩(や)せてほとりの麥(麦)畠空しく赤らみたり。
稻荷山といふ處(処)にて雨ふりいでたれは
日はくれぬ雨は降きぬ旅衣
袂(たもと)かたしきいつくにか寐ん
つぐの日雨晴る。路/\立てたる芭蕉塚に興を催ほして辿り行けば行くてはるかに山重なれり。
野の狹うとかりて次第/\にはいる山路けはしく弱足にのぼる馬塲嶺さても苦しやと休む足もとに誰かうゑしか珊瑚なす覆盆子(ふくぼんし:とっくりいちご)、旅人も取らねばやこぼる〻ばかりなり。少し上りてとある樹陰(こかげ)の葭蔶(よしず)茶屋に憇(いこ)へば主婦のもてなしぶり谷水を四五町のふもとに汲みてもてくる汗のした〻り、情を汲む一口に浮世の膓は洗はれたり。一樹の陰一河の流れとや。ひじりの敎も時にあふてこそありがたけれ。
行くてを仰ぎては苦しみ越方(こしかた)を見下しては慰む。目じるしの大木やう/\近づけばこ〻にも一軒の茶屋。山の嶺をしめて池に臨めり。遠近の眺望一目にあつまりて苦あればこそこの面白さ。迚(とて)もの事山に栖(す)みたし。
またきより秋風そ吹く山深み
尋ねわびてや夏もこなくに
此夜は亂橋(みだればし)といふあやしの小村に足をとゞむ。あとより來りし四五人づれの旅客かにかくと談判の末一人十錢(銭)のはたごに定めて隣の間にぞ入りける。晚餐(ばんさん)を喰ふに塩辛き昆布の平など口にたまりて咽喉(いんこう)へは通らずまして隣室のもてなし如何ならんと思ひやるに、た〻うまし/\といふ聲(声)のみかしかましく聞ゆ。
隣の雑談に夢さまされてつとめてこ〻を立ち出づればはや爪さきあがりの立峠(たちとうげ)旅の若衆と見て取て馬子が馬に乘れとのす〻めは有難や、乘つて見れば旅ほど氣樂なものはなし。きのふの馬塲(ばんば)峠はなぜに苦みし。路の邊(辺)に咲く白き花を何ぞと問へばこれなん卯つ木と申すといふ。いとうれしくて
むら消し山の白雪きてみれば
駒のあかきにゆらく卯の花
峠にて馬を下る。鶯(うぐいす)の時ならぬ音に驚かされて
鶯や野を見下せば早苗取
松本にて晝餉(ひるげ)した〻む。早く木曾路に入らんことのみ急かれて原新田まて三里の道を馬車に縮めて洗馬(せば)まてたどりつき饅頭(まんじゅう)にすき腹をこやして本山の玉木屋にやどる。こ〻の主婦我を何とか見けん短冊もち來りて御笠に書きつけたるやうなものを書きて給はれと請ふ。いかなる都人に敎へられてかといとにくし。本山を出て櫻澤(桜沢)を過ぐればこ〻ぞ木曾の山入り、山のけしき水の有樣はや尋常(じんじょう)ならぬ粧ひ(よそおい)にうつ〻をぬかし桃原遠からずと獨(独)り勇めば鳥の聲(声)も耳にたちてめづらし。途上口占(くちうら)
優くも菖蒲(しょうぶ)咲けり木曾の山
奈良井の茶屋に息ひて茱萸(ぐみ)はなきかと問へは茱萸といふものは知り侍らす。珊瑚實(さんごみ)ならば背戶にありといふ山中に珊瑚さてもいぶかしと裏に廻れば矢張茱萸なり。二十五六ばかりの都はづかしきあるじの女房親切にそをとりてくれたり。峽中(きょうちゅう)第一の難處(難所)といふ鳥居嶺は若葉の風に夢を薰(くゆ)らせて痩せ馬の力に面白う攀(よ)ぢ上る。
馬の背や風吹きこぼす椎の花。
頂にて馬を下りつく/゛\四方を見下せば古木欝蒼(うっそう)谷深くして樵夫(きこり)の小道かすかに隱現す珍らしく晴れ渡りたる空の靑嵐を踏へながら山を下れば藪原(やぶはら)の驛(駅)なり。ある家に立ちよりてお六櫛(くし)を求む。誰に贈らんとてか我ながらあやし。此ほとりよりぞ木曾川に沿ふて下るなる。白雲をあやとる山脈はいよ/\迫りてかぶせからん勢ひ恐ろしく奥山の雪を解かして淸らかなる水は谷を縫うて其響(ひびき)凄し。深き淵(ふち)のたゞ中に大きなる岩の一つ突き出でたる上に年ふりたる松の枝おもしろく龍にやならんと思はれたるなどもをかしく久米駿公【注3】の詩に水抱嚴洲松子立雲龍石窟佛孤栖といへるはこ〻なんめりと獨(ひとり)りつふやかる。宮の越の村はづれに彳(たたず)んて待つ事半時、いど古代めきたる翁の釣竿を擔(かつ)きたるが畫(画)の中よりぞ現れいでたる笠をぬいで慇懃(いんぎん)に德音寺の道を問ふ。翁の云。さてもやさしの若者や。旭將軍のなきあとを吊(とぶら)はんとてこ〻までは來たまへる。こ〻に茂れる夏木立は八幡の御社なり。かしこの山の上こそむかしの城の跡なれ。このわたりの畑もつばものどもが住みし夢の名殘なるものを今は桑の樹ばかりが秀でたると一つ/\に指さす。そゞろに古を忍ぶ言ばのはし、この翁謠ならばかき消すやうにうせぬべし。日照山德音寺に行きて木曾宣公の碑【注4】の石摺(いしずり)一枚を求む。この前の淵を山吹が淵巴(ともえ)が淵と名づくとかや。福嶋をこよひの旅枕と定む。木會第一の繁昌なりとぞ。
翌日朝大雨。待てども晴間なし、傘を購(あがな)ひ來りて書き流す句に
折からの木曾の旅路を五月雨。
旅亭を出づれば雨をやみになりぬ此ひまにと急げば雨の脚に追ひつかれ木陰に憇(いこ)へば又ふりやむ兎に角と雨になぶられながら行き/\て棧橋(かけはし)に着きたり見る目危き両岸の岩ほ數(数)十丈の高さに劉(けず)りなしたるさま一雙の屏風を押し立てたるが如し。神代のむかしより蒸し重なりたる苔のうつくしう靑み渡りしあはひ/\に何げなく咲きいでたる杜鵑花(さつき)の麗はしさ狩野派にやあらん土佐畵(画)にやあらん更に一步を進めて下を覗けば五月雨に水嵩(みずかさ)ましたる川の勢ひ渦まく波に雲を流して突きてはわれ當りては碎くる響(ひびき)大盤石も動く心地してうしろの茶屋に入り床几(しょうぎ)に腰うちかけて目を瞑(ふさ)ぐに大地の動き暫(しば)しはやまず。蕉翁の石碑を拜みてさ〻やかなる橋の虹の如き上を渡るに我身も空中に浮ぶかと疑はれ足のうらひや/\と覺(覚)えて强くも得踏ます通りこし方を見渡せはここぞ棧(かけはし)のあと〻思
しきも今は石を積みかためたれば固より住き來の煩ひもなく只蔦かつらの力がましく這ひ纒(まつ)はれる許りぞ古の俤(おもかげ)なるべき。
俳句
かけ橋やあふない處に山鄭躅(つつじ)。
棧や水へも落ちす五月雨。
歌
昔し誰雲の往來のあとつけて
渡しそめけん木曾のかけはし
上松を過ぐれば程もなく寐覺(ねざめ)の里なり。寺に到りて案內を乞へば小僧絶壁(ぜっぺき)のきりきはに立ち遙(はる)かの下を指してこ〻は浦嶋太郎が龍宮より歸(帰)りて後に釣を垂れし跡なり。川のたゞ中に松の生ひたる大岩を寐覺の床岩、其上の祠を浦島堂とは申すなり。其傍に押し立てたる岩を屏風岩、疊(畳)みあげたるを疊岩と云ふ。象岩は其の鼻長く獅子岩は其の口廣(広)し。此外こしかけ岩爼板(まないた)岩釜岩烏帽子(えぼし)岩硯岩抔(など)申なりといと殊勝げにぞしやべりける。誠やこ〻は天然の庭園にて松靑く水淸くいづこの工匠が削り成せる。岩石は峨々(がが)として高く低く或は凹みて渦をなし。或は逼(せま)りて瀧をなす。いか樣仙人の住處(処)とも覺(覚)えてたふとし。
此日は朝より道々覆盆子(いちご)桑の實(実)に腹を肥したれば晝餉(昼餉)もせず。やう/\五六里を行きて須原に宿る。名物なればと强いられて花漬二箱を購ふ。餘りのうつくしさにあすの山路に肩の痛さを増さんことを忘れたるもおぞまし。
寐(寝:い)ぬ夜半をいかに明さん山里は
月出つるほとの空たにもなし
あくる朝又小雨を侵して須原を立ち出づ。このあたりは木曾川の幅稍々(やや)廣(広)く草木綠に茂りたる洲など見らる。野尻も過ぎて眞晝(真昼)頃三留野(みどの)に着く。松屋といふにて午飯をした〻む今は雨も全く晴れて心よき日影山々の若葉に照りそふけしきのうるはしければ雨傘は用なしとて松屋の女房に興(与)ふ。女房いと氣の毒がりてもぢ/\せしが戶棚かい探り何やら紙に包みて我前にさし出し折からの御もてなしも候はず。都の人お恥かしなからとかすかに言ふ聲(声)いとらうたし何かと聞けは栗なり。禮(礼)をのべてそこを出で路々打ち喰ふに石よりも堅し。よも人間の種にはあらずと思ふにもし便あらば都の人に送りたし。
腹わたも冷つく木曾の淸水哉。
妻籠(つまご)通り過ぐれば三日の間寸時も離れず馴れむつひし岐蘇河(木曽川)に別れ行く何となく名殘惜まれて若し水の色だに見えやせんと木の間/\を覗きつ〻辿れば馬籠(まごめ)峠の麓に來たり。馬を尋ぬれども居らず。詮方(せんかた)なければ草鞋(わらじ)はき直して下り來る人に里數を聞きながら上りつめたり。此の山を越ゆれば木會三十里の峽中を出づるとなん聞くにしばしは越し方のみ見かへりてなつかしき心地す。
白雲や靑葉若葉の三十里
山を下れば驟雨(しゅうう)颯然(さつぜん)とふりしきりて一重の菅笠に凌ぎかね終に馬籠驛の一旅亭にかけこむ。夜に入れば風雨いよ/\烈しく屋根も破れ床も漂ふが如く覺えて航海の夢しば/\破らる。
朝晏(おそ)く起き出でたれど雨猶已(や)まず。旅亭の小娘に命じて合羽(かっぱ)を買ひ來らしむ。馬籠下れば山間の田野稍々(やゝ)開きて麥(むぎ)の穂己に黄なり。岐岨(きそ)の峡中は寸地の隙あればここに桑を植ゑ一軒の家あれば必ず蠶(蚕)を飼ふを常とせしかば今ここに至りて世界を別にするの感あり。
桑の實の木曾路出づれば穗麥(穂麦)哉。
けふより美濃路に入る。餘(余)戶村に宿る。(以下略)
【注1】
正岡子規は、1867年、現在の愛媛県松山市に生まれた。俳句、随筆、評論など様々な分野で作品を残した子規は、明治時代を代表する文学者の一人である。
明治23年9月文科大学入学、夏目漱石と知り合う。24年(1891)に学期末試験を放棄して木曽を旅し、『かけはしの記』を書く。
『かけはしの記』は、子規の写生による文章革新がうかがい知られる文章で、織り込められている俳句・短歌は、散文表現とよく照応している。
明治25年5月27日から6月4日までの間、6回にわたって新聞「日本」に掲載された。(『長野県文学全集 第1巻明治編(1)』解説より)
子規は34歳の若さで他界するが、その短い人生の中で、特に俳句界に与えた影響は計り知れない。
【注2】
碧梧桐子
河東碧梧桐は、日本の俳人・随筆家。正岡子規の高弟として高浜虚子と並び称され、俳句革新運動の代表的人物として知られる。愛媛県松山市に明治6年(1873)生まれる。高浜虚子とは中学時に同級であった。
【注3】
久米駿公は文政十一年(1828)の生まれ。諱は政声、駿公は字である。父は松山藩士籾山資敬。のちに久米政寛の養子となった。
【注4】
この碑は、文化10年(1813)尾張徳川領の木曾代官伊勢守山村良由が木曾義仲(1154~84)の業績をたたえて書いたものである。