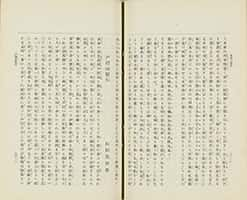画像をクリックすると原本の高精細画像が表示されます。
戸隱山紀行
戸隱山紀行(とがくしやまきこう) 山田美妙齋(びみょうさい)【注1】
去年(きよねん)の夏(なつ)信濃國(しなの〻くに)戶隱山(とかくしやま)【注2】に遊(あそ)ひ其日記(そのにつき)を書(か)くつもりで居(ゐ)て終(つひ)に果(は)たさず、思(おも)ひ至(いた)れば旣(すて)に今日(こんにち)で殆(ほとん)ど一年(ねん)山(やま)に對(だい)しては紀行(きこう)を誓(ちか)つた、それ諸共(もろとも)其日(そのひ)を記臆(きおく)するため心覺(こ〻ろおぼ)えの中(なか)から列(つら)ねて、この夏期(かき)漫遊(まんいう)を計(はか)る人(ひと)にも人(ひと)のまた餘(あま)り行(ゆ)かぬ此(この)山の名勝(しよう)を知(し)らせる所存(しよそん)、引(ひき)つゞいて是(これ)から暫時(さんし)此處(ここ)へのせます、
耶馬溪(やはけい)【注3】の奇(き)は實見(じつけん)せぬ事(こと)とて何(なん)とも云(い)へず、妙義(めうぎ)【注4】の勝(しよう)は成(な)る程(ほと)勝(しよう)、然(しか)し戶隱山(とかくしやま)に比(くら)べれば猶(なほ)規摸(きも)の少(ちひ)さい處(ところ)が恨(うらみ)です、戶隱(とかくし)の名(な)は紅葉狩(もみぢかり)【注5】の故事(こし)から緣(ゑん)を引(ひ)いて今日(こんにち)も人(ひと)が聞(き)く聞(き)いてそれで見(み)た人(ひと)は却(かへつ)て少(すく)ない、それには原因(けんいん)も有(あ)ること何(なに)を言(い)ふにも信越(しんえつ)【注6】のほとんど境(さかひ)、長野(なかの)からさへ五里(り)の險阻(けんそ)を越(こ)えなければ行(ゆ)かれぬ、是(これ)が一(ひと)つ、それに有名(いうめい)な險阻(けんそ)な山(やま)、一度(ど)遊(あそ)んだものが、懲懲(こりこり)して驚(おどろ)いて其(その)危險(きけん)を唱道(しやうどう)する、是(これ)か一(ひと)つ、つまりは第一(たいいち)の原因(けんいん)が都城(としやう)の人足(ひとあし)を隔(へた)てたわけで、第二(たいに)が信濃人(しなのひと)をさへ威(おと)した所(ところ)であつた、信濃(しなの)、而(しか)も長野(なかの)の人で猶(なほ)戶隱(とかくし)を見(み)ぬ人(ひと)が頗(すこふ)る有(あ)る、それで其險(そのけん)も分(わ)かる、長野(なかの)へ著(つ)いた其(その)夕(ゆう)ぐれ福武氏(ふくたけし)に逢(あ)つて戶隱(とかくし)の話(はな)しを聞(き)けば險阻(けんそ)は險阻(けんそ)なか
ら見(み)る價値(かち)は充分(じゆうぶん)あるとの事(こと)、福武氏(ふくたけし)は嘗(かつ)て一度(いちと)遊(あそ)んだ事(こと)が有(あ)つて山蕎麥(やまそば)の味(あち)も忘(わす)れられぬとか同行(とうかう)しやうとの言葉(ことは)、聞(き)く身(み)も勇(い)さみ立(た)つた、これを人(ひと)に話(はな)すと矢張(やは)り長野の柴田氏(しはたし)も賛成(さんせい)した、けれど三四日間(かかん)は大雨(たいう)で出立(しゆつたつ)さへ出來(てき)ず、空(むな)しく天(てん)を恨(うら)むばかり、それでなくとも戶隱(とかくし)は雨(あめ)の多(おほ)い山(やま)で、道(みち)の泥濘(ぬかるみ)は無類(むるゐ)との事(こと)まづ白河法皇(しらかははうわう)を極(き)めて空(むな)しく日(ひ)を暮(く)らしてゐた。ときに七月(しちくわつ)十五日(にち)、午後(ここ)から不思儀(ふしぎ)に雲切(くもき)れを見付(みつ)けた其(その)嬉(うれ)しさ、また晴雨(せいう)何(いつ)れとも決(けつ)せぬもの〻早(はや)晴(は)れた心持(こ〻ろも)ち、前日(せんしつ)來(らい)の雨(あめ)で道(みち)は嘸(さそ)かし損(そん)した事(こと)と思(おも)つたもの〻夫(それ)を顧(かへ)りみる處(ところ)でなく、翌日(よくしつ)は晴雨(せいう)に抱(か〻)はらず、無論(むろん)濡(ぬ)れるは覺悟(かくこ)、泥(とろ)布子(ぬのこ)【注7】を着(き)るのは必定(ひつちやう)、夫(それ)ながら朝立(あさた)ちして向(むか)はうと相談(そうたん)一決(けつ)し、翌朝(よくてう)を契(ちき)つた、其(その)夜(よ)は床(とこ)に付(つ)いた物(もの)の、目を覺(さ)ませば山嵐(やまあらし)も點滴(てんてき)とあやまたれて、田(た)の蛙(かはつ)のなく聲(こゑ)も雨(あめ)を呼(よ)ふかと胸(むね)はとつおいつ、いつか起(おこ)されて見(み)ればあ〻戶隱大明神(とかくしたいみやうしん)東(ひかし)の嶺(みね)の端(はし)しらしらと晃(きら)めいて、朝霧(あさきり)の薄紗(はくさ)が朝日山(あさひやま)【注8】の額(ひたひ)を包(つ〻)み風(かせ)しづかに、空(そら)玉子色(たまこいろ)正(まさ)に好天氣(かうてんき)の瑞(すゐ)はあらはれた、朝まだ四時(し)、既(すて)に柴田氏(しはたし)に訪(と)はれた顔(かほ)を洗(あら)つたか、洗(あら)はぬかは、全(まつた)く夢中(むちう)、單衣(ひとい)にく〻りつけた高袴(たかはかま)、脚胖(きやはん)と足袋(たび)とて足(あし)をしめてそして前夜(せんや)用意(ようい)した日和(ひより)下駄(けた)を穿(うか)つた打扮(いてたち)は登山(とさん)に似合(にあ)はぬ打扮(いてたち)と人(ひと)は轉(ころ)げて笑(わら)ふばかり、生來(せいらい)山越(やまこし)は靴(くつ)で無(な)ければ、下駄(げた)、其外(そのほか)は不得手(ふいて)な私(わたくし)、よしや黑鐘(くろかね)の岩角(いわかと)でも踏(ふ)み砕(くた)いて、進(す〻)まうものをと氣(き)ばかりは半(なか)ば抜(ぬ)けて山(やま)へ馳(は)せた、柴田氏(しはたし)は單衣(ひとへ)の着流(きなか)しに脚胖(きやはん)草鞋(わらち)かけ、福武氏(ふくたけし)も單衣(ひとへ)に高袴(たかはかま)の脚胖(きやはん)草鞋(わらち)かけ。何(いつれ)も身輕(みかる)な打扮(いてたち)であつた、金剛杖(きんこうつゑ)にも象(かたと)る蝙蝠(かうもり)つきたて用意(ようい)整(と〻の)つていざと計(はか)りに出立(しゆつたつ)した長野(なかの)町(まち)の人家(しんか)まだ起(お)きず買(か)ひ立(た)ての樫齒(かしは)音高(おとたか)く響(ひ〻)いて、而(しか)も朝開(あさひらき)の風(かせ)もろとも凉(す〻)しさう、往生寺(わうしやうし)【注9】山(やま)に差掛(さしか)かる內(うち)爪先(つまさき)は次第(したい)に上(あか)つて其谷(そのたに)を經(へ)た頃(ころ)は最早(もはや)一起(いつき)一伏(いつふく)すこしも定(さた)まらぬ峙(とうけ)となつた此處(ここ)を何(なに)と聞(き)けば其處(そこ)に聳(そひ)えるのが大峰山(おほみねやま)との事(こと)であつた、この大峰山(おほみねやま)は有名(いうめい)な松茸山(まつたけやま)で、如何(いか)さま見上(みあ)げた處(ところ)松(まつ)といふ木(き)の外(ほか)には土(つち)ばかり、山(やま)はさらめいた土(つち)で松(まつ)には適(てき)しさう、之(これ)を左右(さいう)に送(おく)り迎(むか)へての一里(り)ばかりはまことに唯(た〻)の山(やま)是(これ)と云(い)ふ興(きよう)もなければ是(これ)といふ不與(ふきよう)もなく、同行(とうきやう)三人(にん)無駄口(むたくち)を木(き)だまに響(ひ〻)かせて罪(つみ)もない途傍(みちはた)の甘草(かんそう)又(また)は釣鐘草(つりかねそう)の花(はな)をつまんでむしるばかり、果(は)ては高笑(たかわら)ひに驚(おとろ)いて飛(と)び立(た)つ雲雀(ひはり)が二つ三つ、顧(かへ)りみれば長野(なかの)にあつて見上(みあ)げた朝日山(あさひやま)やまた今(いま)まで高(たか)いと思(おも)つた大峰山(おほみねやま)も山途(やまみち)の常(つね)、次第(したい)に低(ひき)くなり果(は)て〻終(つひ)には記標(きへう)に見(み)えた絶頂(せつちやう)の松(まつ)が地平線(ちへいせん)に噛(か)まれて行(ゆ)く體(てい)、夜(よる)は充分(しゆうふん)に明(あ)け離(はな)れて山(やま)の端(は)を限取(くまと)る朝日(あさひ)の色(いろ)もほんのり紅(あか)く、此日(このひ)の天氣(てんき)いよ/\賴(たの)もしくなつた、行(ゆ)き行(ゆ)く內(うち)に荒安(あらやす)といふ處(ところ)にか〻る、掛(か〻)つたところで際立(きはた)つたのは道(みち)が楽(らく)に為(な)つた
事(こと)であつた、むかし親鸞聖人(しんらんしやうにん)【注10】か大峯山(おほみねやま)からこ〻まで來る時(とき)、道(みち)の險阻(けんそ)に弱(よは)り果(は)てやうやく荒安(あらやす)まで來(き)て「あら安(やす)と其道(そのみち)の樂になつたのを喜(よろこ)んだと云(い)ふ、それが故事(こし)で今日(こんにち)も其處(そこ)を荒安(あらやす)と名(な)付(つ)けたとか、今(いま)は婦人(ふしん)小供(ことも)にはや〻六(むつ)かしいもの〻夫程(それほと)の道(みち)でもなく、むかしこのやうで親鸞がさう言(い)つた物(もの)ならば實(しつ)に聖人(しやうにん)は飛(と)んだ弱虫(よわむし)三里(り)の灸(きう)を勧告(くわんこく)しても宜(よ)からうと一同(とう)が飛(と)んだ空(そら)威張(ゐはり)、路傍(みちはた)に一軒(けん)ばかり淋しさうに設(まう)けた茶店(ちやみせ)に立(た)ち寄(よ)つて見晴(みは)らしいのい〻椽鼻(えんはな)から遠(とほ)くを望(のそ)めば今(いま)までの山中(やえなか)に引(ひ)き更(か)へ天(てん)がまるで切(き)り開(ひら)けたやう、山(やま)は遠近(ゑんきん)にうねつて思(おも)ひ思(おも)ひの色(いろ)中(なか)に一際(ひときは)遠(とほ)く見(み)える一脉(いちみやく)は猶(なほ)あまたの雪(ゆき)を載(の)せて居(ゐ)る、あれは何山(なにやま)と尋(たつ)ぬれば、飛驒(ひた)の國境(くにさかひ)との答(こた)へ、あ〻飛驒(ひた)が見(み)える處(ところ)までもう來(き)たかと思(おも)はず感(かん)じもした、腰(こし)に帶(お)びた望遠鏡(ほうゑんきやう)を取(と)り出(た)した柴田氏(しはたし)は頻(しき)りに吾(われ)々ともとも見回(みま)はすのを村(むら)の小兒(ことも)が見(み)て羨(うらや)ましがる、「飛騨(ひた)の山(やま)に蠅(はい)が居(ゐ)る」と感じて渡(わた)せは眞面目(ましめ)で望遠鏡(ほうゑんきやう)の鏡(か〻み)の面(おもて)にとまつた蠅(はい)に欺(あさむ)かれて居(ゐ)るをかしさ、休息所(きうそくしよ)を立(た)ち出(いて)ていくらも行(ゆ)かぬ內(うち)次第(したい)々々に天氣(てんき)が悪(わる)くなり始(はし)め、遠山(とほやま)の根方(ねかた)は切(き)れて居るもの〻頭(あたま)の上(うへ)には雲足(くもあし)が低(ひく)くなつた、幸(さいはい)に凉(す〻)しさは涼し然(しか)し苦勞(くろう)も苦勞(くろう)、聞(きこ)える難所(なんしよ)にやがてさし掛(か〻)つて降(ふ)られ何程(なにほと)の不都合(ふつかふ)であらうか、雲足(くもあし)の低(た)れた割(わり)りには容易(ようい)に雨(あめ)も來(こ)ず、神々に送(をく)られてほつ/\と足(あし)を運(はこ)んだ、路(みち)は一起(いつき)一伏(いつふく)やはり定(さた)まらず、而(しか)もやうやく一間(けん)前後(せんこ)の上(あか)り下(さか)り、左右(さいう)は或(あるひ)は林(はやし)或(あるひ)は谷(たに)、人家(しんか)も折(を)り/\思(おも)ひ出(たし)たやうに一二軒(けん)あるばかり頗(すこふ)る氣候(きこう)は下界(けかい)と變(かは)つたと見(みえ)えて時(とき)/\見える麥畑(むきはた)の麥(むき)は猶(なほ)青味(あをみ)を帯(お)ひて、脊(せ)も低(ひく)く、而(しか)もそれで刈(か)つては無(な)かつた、見(み)るからか變(か)はつた心(こ〻ろ)持(も)ち、道(みち)を傍(そ)つて流(なか)れる溪流(けいりう)の透(す)き徹(とほ)るまで美(うつく)しいのに立(た)ち去(さ)りかね、はんけちを浸(ひた)して汗(あせ)などを拭(ぬく)つてゐる內(うち)に落(を)ち合(あ)つた二人(ふたり)の男(をとこ)、是(これ)も族(□ひ)よそほひであつた、最早(もはや)人界(にんかい)に遠(とほさ)かつて中(なか)/\に人(ひと)は戀(こひ)しく、言葉(ことは)をかけれは先方(せんほう)も應荅(おうたう)した、これら二人(ふたり)は丹波島(たんはしま)のもので、鶯(うくひす)の雛(ひな)を戶隱山(とかくしやま)に取(と)りに行(ゆ)くとか、矢張(やは)り朝(あさ)立(た)ちして出(て)て來(き)たのであつた、何(なに)を携(たつさ)へるかと思(おも)ふと別(へつ)にそれらしい物(もの)も無(な)く、就(つ)いて鶯(うくひす)の事(こと)を話(はな)せばなる程(ほと)黑人(くろうと)であつた、戶隱(とかくし)には以前(いせん)鶯(うくひす)が中(なか)/\澤(さん)山であつたところ近頃(ちかころ)取(と)り盡(つくし)て大(おほい)に少(すく)なくなり大(おほい)によわるとの愚痴(くち)、誰(たれ)が取(と)り盡(つくし)たと問(と)ひかへせば「私等(わしら)さ」と言(い)いて呵(から)/\とわらふ其(その)質朴(しつほく)小(こ)一里(り)の道(みち)をこれらと一途(いつしよ)して、一行(こう)すべて五人(にん)、面白(おもしろ)をかしく思(おも)はず道(おも)を捗(はか)取(と)つたやがて其內(そのうち)林(はやし)の中に突然(とつぜん)と鶯(うくひす)が見(みえ)えたとか「それ居(ゐ)た」と言(い)ふより早(はや)く二人(ふたり)は林(はやし)に飛(と)ひ入(い)ると、さても草(くさ)の深(ふか)さ、身(み)は早沒(はやほつ)して仕舞(しま)つた、心(こ〻ろ)よい田舎(ゐなか)の人(ひと)の道(みち)連(つ)れもこ〻に無(な)くなつた人(ひと)の鯛(たひ)釣(つ)り、見て隙(ひま)をつぶすのも詰(つま)らぬ噺(はな)し、其儘(そのま〻)袂(おもと)を分(わ)か
つて彼是(かれこれ)四五町(ちやう)、何(なん)と言ふか名(な)は忘(わす)れたが山繭(やままゆ)など道傍(みちはた)に多(おほ)く居(ゐ)る、山中(やまなか)の一軒家(いつけんや)を遙(はる)かに望(のそ)んで右(みき)を迂回(うくわい)し、左(ひたり)をまはり、行(ゆ)き着(つ)いて見(み)れば是(こ)は如何(いか)に、前(まへ)の二人(ふたり)は旣(すて)に其處(そこ)に腰(こし)を掛(か)けてゐた、最早(もはや)一日(いちにち)の馴染(なしみ)互(たかひ)に言葉(ことほ)を掛(か)け合(あ)つて吾吾(われわれ)も其處(そこ)に腰(こし)を掛(か)け、さて其(その)家(いへ)を見回(みまは)すと、何(なに)か無(な)し目(め)に入(い)つたのは獵銃(れうしゆう)であつた獵師(れうし)かと問(と)へば齒(は)の抜(ぬ)けた皺(しわ)がれ聲(こゑ)の老婆(らうは)が「はい」と答(こた)へる、途端(とたん)見(み)れば見馴(みな)れぬ吾(われ)/\の姿(すかた)に寄(よつ)て來(き)たのは例(れい)の日本種(にほんたね)の狐(きつね)めいた瘦(やせ)がれた狗(いぬ)、主(おも)に獵(かり)に用(もちゐ)る類(るゐ)であつた、差(さ)し出(た)す山茶(やまちや)は色(いろ)ばかり、よく有(あ)る事(こと)、烟草盆(たはこほん)に取(と)り入(い)れた火(ひ)は爐(いろり)の燃(も)えさして取(と)るや否(いな)や一服(ふく)つけさせたのを御役濟(おやくすみ)にして直(すく)さま消(き)えて仕舞(しま)つた、獵(れう)についての事(こと)を話(はな)しかけても兎角考婆(とかくらうは)の話(はな)しも火同樣答(ひとうやうこたへ)るたけで直(す)く消(き)えるばかり、前(まへ)の二人(ふたり)の鶯取(うくひ□ど)りとは傍(そば)で聞(き)いて更(さら)に分(わか)らぬ應答(おうたふ)を高聲(たかこゑ)で饒舌(しやへ)つた要(えう)するに前(まへ)の二人(ふたり)は常(つね)に鶯(うくひす)を取(と)りに來(き)て、こ〻の家(うち)とも既(すて)に入懇(しゆこん)、われ/\は一足(あし)さきに袂(たもと)を分(わ)かつた、この間(あひた)見(み)るものは山(やま)、一つ越(こ)せばまた山(やま)、空(そら)も山(やま)で支(さ〻)へられ、地面(ちめん)も山(やま)で固(かた)めてあつたて、始(はし)めてや〻珍(めつ)らしい心持(こころも)ちのしたのは是(これ)からか即(すなは)ち信濃(しなの)で有名(いうめい)の原(はら)飯繩(いつな)が原(はら)に掛(か)かるのであつた、程無(ほとな)くも飯繩(いつな)が原(はら)に出(て)て見(み)れば、何(なに)さま凄(すさ)ましい大(おほ)きな原(はら)、一望(はう)ただ茫漠(はうはく)と切(き)り開(ひら)かれて、今(いま)までに山中(さんちう)をもくつた目(め)か俄(には)かに暗(くら)いやう、右(みき)を見(み)れば例の名高(なたか)い飯繩山(いつなさん)【注11】が雪(ゆき)の中(なか)に入(はい)つて居(ゐ)た、飯繩(いつな)の不動(ふとう)と言(い)つて音(おと)に聞(きこ)えた山(やま)即(すなは)ち是かと見上(みあ)げれば山(やこ)も凛然(りんせん)と故(こと)さら威儀(ゐき)を正(た〻)した風情(ふせい)、一面(めん)に何(なん)の木(き)か隙間(すきま)もなく而(しか)も造化(そうくわ)の手(て)は過不及(くわふきう)なく其梢(そのこずゑ)を揃(そろ)へさせて評(ひやう)すれば豊富(ほうふ)な山(やま)、山(やま)の形(かたち)は西角(せいかく)に大襞(おほひた)を絞(しぼ)つて、それで目(め)に立(た)つ山脉(さんみやく)も無(な)い事(こと)とて吃然(きつせん)として而(しか)も三角形(さんかくけい)に恰好(かつかう)よく峙(そはた)つて居(ゐ)た、山(やま)の裾(すそ)からの一回(いつくわい)が即(すなはち)ち飯繩(いつな)が原(はら)、われ/\が過(すき)た處(ところ)は大抵(たいてい)山(やま)から一里(り)ばかり離(はな)れたのみ、それで山(やま)の威嚴(ゐけん)は猶(なほ)是程(これほと)であつた、携(たつさ)へたのは双眼鏡(そうかんきやう)力(つとめ)ても山(やま)の木(き)は何(なに)か分(わ)からず、それが頗(すこふ)る遺憾(ゐかん)であつたが、扨(さて)其(その)遺憾(ゐかん)に附(つ)け加(くは)へていやな話(はな)しと不快(ふくわい)とを段(たん)々に感(かん)じた、いやな話(はな)しとはこの邊(へん)に山犬(やまいぬ)(狼(おほかみ)の一種(しゆ))の多(おほ)いといふ事(こと)、及(およ)び原(はら)の景色(けしき)がやがて千篇一律(せんへんいちりつ)になつたことである、近來滊車(きんらいきしや)か開(ひら)けたから猛獸(まうしう)の類(るゐ)は皆(みな)其(その)響(ひ〻)きに怯(お)ぢ、深山(しんさん)へ逃(に)け込(こ)んで、其(その)ため從來(しゆうらい)あまり猛獸(まうしう)に逢(あ)はなかつた山(やま)にも意外(いくわい)のものが現(あら)はれて、この飯繩(いつな)が原(はら)にも折(をり)/\山犬(やまいぬ)出沒(しゆつほつ)するとの事、われ/\がこ〻に差(さ)し掛(かか)つたのは早(は)や午前(こせん)八時(し)や〻過(す)ぎた頃(ころ)で、晝間(ひるま)のことゆゑ眞逆(まさか)と思(おも)ふ氣(き)もあつたかしかし半(なか)ばは恐(こは)いもの見(み)たさの心(こころ)も交(まし)つた、原(はら)と言(い)つても中(なか)/\むかしの武藏野(むさしの)などのやうではなく小(ちひ)さな岡(をか)が高低(たかひく)して居(ゐ)る平地(へいち)で、二(ふた)つばかり湖(みつうみ)も有(あ)つた、原(はら)の土(つち)は墨(すみ)のやうな黑士(くろつち)、木(き)らしい木(き)は一本(ほん)も無(な)く
下生(したはへ)の草(くさ)は芝(しは)ばか、其外(そのほか)は實(み)のつかぬいちご、又(また)は名(な)も知(し)れぬ灌木(くわんほく)くらゐのもの、わるく言(い)へば草(くさ)さへ碌(ろく)なのは少(すこ)しも無(な)かつた、土質(としつ)の悪(わ)るさに物(もの)も生(は)へず、唯(た〻)荒蕪(くわうふ)に歸(き)して居(ゐ)るのは惜(を)しいものと飛(と)んだ實業家(しつけふか)氣取(きと)りで呟(つふや)くのは吾(われ)ながらをかしな話(はな)し、いくら歩(ちる)いても歩(ある)いても飯繩山(いつなさん)はやはり右(みき)に元(もと)の形(かたち)、原(はら)はやはり形(かたち)も變(か)はらず、もう山(やま)が鼻(はな)について八重十重(やへとへ)に列(つら)なる體(てい)を見(み)て名(な)を聞(き)きたくもなく、また聞(き)くものもなく、前後(せんこ)をふり返(かへ)れば一面(めん)圓(まる)い天(てん)に限(かき)られた平(ひら)たい土盤(とはん)の上(うへ)に人間(にんけん)はわれ/\、三人、肺(はい)が破(や)ぶれる計(はかり)に人(ひと)の事(こと)を罵(の〻し)つても空氣(くうき)の外(ほか)には聞(き)くものも無(な)く、唯(た〻)々滿足(まんそく)したのは其(その)サフライムな事(こと)此原(このはら)と戶隱(とかくし)へ旅行(りよこう)する者(もの)の最(もつと)も不快(ふくわい)な處(ところ)である、長野(なかの)から出(て)て足(あし)は早(はや)いくらか草臥(くたひれ)て來(き)た上(うえ)に増(ま)して長(なか)い間(あひた)變化(へんくわ)もない處(ところ)、同伴(とうはん)でも無(な)ければ欠伸(あくひ)は請合(うけあい)である、夏(なつ)でも人(ひと)の通行(つうこう)は一日(にち)何人(なんにん)と言(い)ふ位(くらい)、十月の初(はし)めからは全(まつた)く雪(ゆき)で埋(うま)つて、それに飯繩(いつな)おろしの吹雪(ふぶき)は馬(うま)をも埋(うつ)める計り、人跡(しんせき)は全(まつた)く絶(た)えて、容易(やうい)ならぬ所用(しよよう)の有(あ)る者(もの)の外(ほか)僅(わずか)に飢(う)えた獸類(しうるゐ)が雪(ゆき)を踏(ふ)むのみとのことであつた、いつとか長野(なかの)から兇賊(きようそく)が脱走(たつそう)して戶隱山(とかくしやま)に逃(に)け込(こ)んだ時(とき)警官(けいくわん)が其跡(そのあと)を追(お)つて此原(このはら)を徒歩(かち)て越(こ)した事(こと)が有(あ)つたさうで、雪(ゆき)は三尺(さんしやく)も積(つも)つて居(い)る內(うち)になほとんとん降(ふ)りしきつてやがて戶隱(とかくし)へゆき着(つ)いた頃(ころ)には烈寒(れつかん)にこらえて足(あし)は血(ち)がにじんで脹(は)れ上(あか)つたとの事(こと)であつた、やうやくにして原(はら)の果(は)てに當(あた)つてさ〻やかな鳥居(とりゐ)を認(みと)めた時(とき)の嬉(うれ)しさ、其(その)鳥居(とりゐ)が即(すなは)ち戶隱神社(とかくししんしや)のもので、すはや着(つ)いたかと躍(おと)り立(た)つて、さて又(また)聞(き)けば、驚(おどろ)く話(はな)し、はるか遠(とほ)くの雲(くも)の中(なか)で糢糊(もこ)として居(ゐ)るのが戶隱山(とかくしやま)との事(こと)まだ/\里程(りてい)は遠(とほ)い事(こと)、評(ひやう)すれば鳥居(とりゐ)はほんの小供(ことも)たましの藥菓子(くすりくわし)、一寸(ちよつと)氣(き)を賺(すか)すだけであつた、流石(さすか)に氣(き)は勇(いさ)んだ、ことには天(てん)の憐(あはれ)みか、泣(な)き出(た)しか〻つた天(てんき)氣も亦(また)直(なほ)つて雲(くも)も梢(や〻)薄(うす)く折(をり)/\の破(わ)れ目(め)から目的(めあて)の山(やま)の中腹(ちやうふく)を見(み)せた、そこに眸(ひとみ)を疑(こ)らせば、さても妙絶佳絶鼠色(めうせつかせつねすみいろ)の巉崖絶壁(さんかんせつへき)【注12】、や〻催(もよほ)した足(あし)の疲(つか)れも忘(わす)れ果(は)てるばかり、既(すて)に原(はら)をば後(あと)に見(み)て山道(やまみち)を左右(さゆう)に迂回(うくわつ)し山(やま)の位置(ゐち)をこ〻かしこに見(み)かへて、とある人家(しんか)二軒(にけん)ばかり有(あ)る處(ところ)に出(て)て、それを見過(みす)くせば一軒(いつけん)の休息所(きうそくしよ)、直(すく)に入(はい)つて憇(いこ)ふ間(ま)に無殘亂雲(むさんらんうん)が其處此處(そここ〻)に湧(わ)いて日影(ひかけ)も忽(たちま)ちかくれ、ねばるやうな雨(あめ)が降(ふ)り出(た)した、亭主(ていしゆ)は世辭(せし)のい〻、小利口(こりこう)らしい男(をとこ)、而(しか)もここは戶隱登山(とかくしとさん)の者(もの)のために力餅(ちからもち)を賣(う)る處(ところ)とて頻(しき)りに之(これ)をす〻め、それでも感心(かんしん)に白砂糖(しろさとう)をふりかけて出(た)した、今(いま)、までの道(みち)の寂莫(さひしさ)に引(ひ)き更(か)へて、意外(いくわい)なのはこ〻の茶店(ちやみせ)に糸莚連中(いとたてれんちう)が同(おな)じく旅(たひ)よそほひて二十人餘(にしうにんよ)も居(ゐ)たことで、聞(き)けば是(こ)れは飯山(いゐやま)(信濃(しなの)の北隅(ほくく□)、雪(ゆき)の名所(めいしよ))最寄(もより)の農家(のうか)のもの、近頃(ちかころ)の降(ふ)り續(つ〻)きに晴(は)れを山神(さんしん)に祈(いの)るための登山(とさん)との趣(おも)むき、いづれも力餅(ちからもち)の
馳走(ちそう)に大口(おほくち)を開(あ)いて口中(こうちう)は丸(まる)で眞白(まつしろ)、かや/\わや/\目(め)を眠(ねむ)れば繁華(はんくわ)な土地(とち)へ出(て)た心持(こ〻ろもち)もする程(ほと)であつた、われ/\が腰(こし)をかけた處(ことろ)は向(むかつ)て左(ひたり)の庭(には)めいた處(ところ)で屹然(きつせん)と其前(そのまい)に當(あた)つて峙(そはた)つのは全(まつた)く石質(せきしつ)の大盤石(おほはんせき)、千年(せんねん)の苔(こけ)蒸(む)して谷水(たにみつ)のした〻りが膩(あふら)を絶(た)やさず、名(な)も知(し)れぬ異草(いさう)が生(は)へて居(ゐ)た、はや空氣(くうき)の温度(をんど)は冷(ひや〻)か、思(おも)へば、今日(けふ)は盆(ほん)の十六日、都下(とか)の此頃(このころ)の暑(あつ)さと比較(ひかく)すれば猶(なほ)冷(ひや)やかと言(い)ふ中(うち)に言(い)ひ盡(つく)され凄味(すこみ)が山(やま)の常(つね)とて身(み)に染(し)みた、この雨(あめ)は晴(は)れるかと亭主(ていしゆ)に聞(き)けば、いつかは晴(は)れるだらうとの言葉(ことは)、戶隱(とかくし)は餘處(よそ)が降(ふ)らぬ時(とき)でも降(ふ)るゆゑ珍(めつ)らしく無(な)いとの澄(すま)した答(こた)へ、聞(き)いても聞(き)かぬでも同(おな)じ話(はな)しであつた、雨(あめ)は無論(むろん)覺悟(かくこ)の事(こと)、いざとばかり立(た)ち出(いつ)ればさあ今度(こんと)は飽(あ)き飽(あ)きする道(みち)、それから山(やま)までは一町毎(ちやうこと)に町數(ちやうすう)が記(しる)して一里半(りはん)(?)と石杭(いしくひ)の立(た)つてゐたが、その間(あいた)は左右(さいう)いづれも木立(こたち)ばかり、山(やま)も見(み)えなければ雨(あめ)はびしよつく、道(みち)は漸(やうや)く一間位(けんくらい)、中(なか)に一筋(ひとすち)おのづから石段(いしたん)を刻(きさ)んだやうに牛(うし)の跡(あと)が蛇腹(しやはら)についてゐた石(いし)はなし、道(みち)は赤土(あかつち)、うつかりすれば辷(すへ)るあぶなさ、すでにわれ/\三人(さんにん)が實際(しつさい)之(これ)を經驗(けいけん)した、左右(さいう)の林(はやし)は何處(とこ)まで奥(おく)があるのか、大木(たいほく)に小木(せうほく)灌本(くわんほく)に下草(したくさ)土目(つちめ)になれて生(は)へ茂(しけ)つて蛇(へび)がゐるやら蝮(まむし)がゐるやら、ことに目(め)につくのは、樺(かは)の木(き)とまた雷火(らいくわ)に燃(も)えた大木(たいほく)であつた、伊香保(いかほ)【注13】から掛(か)けて上州(しやうしう)の山(やま)にも落雷(らくらい)した木(き)が多(おほ)いとほり、この邊(へん)にも落雪(らくらい)は凄(すさ)まじい事(こと)と見(み)えた、談笑(たんせう)の中(うち)に向(むか)ふにあたつて見(み)る一簇(ひとむら)の樅(もみ)の木立(こたち)、其横(そのよこ)にきらつくのは待(ま)ちに待(ま)つた戶隱(とかくし)の山里(やまさと)であつた、折(をり)から雨(あめ)も晴(は)れて雲(くも)も少(すく)なく、漏(も)れる戶隱山(とかくしやま)の絶頂(せつちやう)を仰(あふ)げば岩石(かんせき)の樣(さま)もや〻詳(つまひ)らか、谷間(たにま)に一點(いつてん)見(み)える白(しろ)いもの、瀧(たき)か河(かは)かと評(ひやう)したのも當推量(あてすいりやう)、よく見定(みさた)めれば矢張(やは)り雪(ゆき)であつた、いつか樅(もみ)の木立(こたち)に入(はい)ればもう何處(とこ)へ行(い)つたか分(わ)からず、日影(ひかけ)も洩(も)らぬ木下闇(このしたやみ)、まづ異常(いしやう)なのは身(み)に感(かん)ずる山氣(さんき)であつた樅(もみ)は木立(こたち)でこそあれ、猛然(まうせん)として雪(ゆき)を突(つ)くいかめしさ、山(やま)に入(はい)るに從(した)がつて山(やま)だけの形容(けいよう)が段(たん)々ついて來(き)た、時計(とけい)を見(み)ればや〻午前(こせん)十一時(し)、右(みき)の鳥居(とりゐ)は一の鳥居(とりゐ)とて長野(なかの)からの登路(のほりみち)はここに限ることで、それから力餅(ちからもち)を賣(う)つて居(ゐ)た處(ところ)は大久保(おほくほ)といふ村(むら)いざや山(やま)と言(い)ふ處(ところ)で追分路(おいわけみち)になり、其處(そこ)に石(いし)が建(た)つて居(ゐ)て「右(みき)、中社(ちやうしや)、左、寶光社(はうくわうしや)」と彫(ほ)つてあつた、中社(ちゆうしや)と言(い)ふのは中院(ちゆうゐん)で奥(おく)の院(ゐん)へ行(ゆ)くもの〻經(へ)る處(ところ)、寶光社(はうくわうしや)は一(ひと)つ山(やま)に別(へつ)に設(まう)けた一宇(いちう)の社(やしろ)でこ〻からも中院(ちゆうゐん)へ行(ゆ)けるが、初めて登山(とさん)するものはまづ中院(ちゆうゐん)へ行(ゆ)くのが順路(しゆんろ)である、はじめ携(たつ)さへた繪圖(ゑつ)によれば此追分(このおいわけ)から右(みぎ)の道(みち)を取(と)つて程(ほと)なく熊(くま)の塔(たう)といふ由緒(ゆゐしよ)の有(あ)るらしい物(もの)が有(あ)つた趣(おもむ)き、しかし殘念(さんねん)な事(こと)、見損(みそこ)なつて仕舞(しま)つた、右(みき)に富士見山(ふしみやま)といふのを眺(なか)めて登(のほ)る山路(やまみち)、さあ聞(き)いた通(とほ)り弱(よわ)り果(は)てた、何(なに)しろ途(みち)は柔(やわら)かい赤土(あかつち)、それで果(はて)
ない大(おほ)のぼり自然(しせん)と足(あし)に力(ちから)が入(はい)る、それ丈(たけ)に一足(ひとあし)下(くた)せばぐつと潜(もく)つた、會(かつ)て碓氷峠(うすひとうげ)【注14】を越(こ)した時(とき)、其道(そのみち)のわるさ馬(うま)さへ脛(すね)を沒(ほつ)する勢(いきほひ)には駭(おとろ)いたもの〻此處(ここ)は上信(しやうしん)の境(さかひ)で通行(つうこう)も有(あ)る所(ところ)ゆゑと諦(あきら)めたが、僻境(へききやう)の戶(と)がくしが斯(か)うあらうとは思(おも)ひも付(つ)かぬ話(はな)し草鞋(わらち)がけなら辷(すべ)らずには濟(す)まず下駄(けた)がけなら脱(ぬ)かずには終(おは)らず私(わたくし)も二三度(にさんと)下駄(けた)を吸(す)ひ取(と)られた唯(た〻)掛(か)け聲(こゑ)ばかり、其(その)くせ我慢(かまん)で成(な)るたけよささうな道(みち)と擇(えら)ぶだけ些(すこ)しも捗(はかと)らず、儲(まう)けものだか、損耗(そんまう)だか、泥染(とろそ)めの足袋(たひ)が出來(てき)た、やがて引(ひ)き續(つ〻)く山里(やまさと)、いづれも舊(もと)の許多(あまた)の神官(しんくわん)の住(すま)ひで、今(いま)は何(いつ)れも登山(とさん)の人(ひと)のための旅宿(りよしゆく)見(み)たのは其(その)くらゐ、下(した)を向(む)いて足(あし)をどられぬ用心(ようしん)するばかり中社(ちゆうしや)まで行(ゆ)き着(つ)いた時(とき)は重荷(おもに)を下(おろ)したやうな氣(き)がした、中社(ちゆうしや)と言(い)ふは思(おも)つたよりは大(おほ)きな規模(きも)、而(しか)も登山(とさん)の人が虛弱(きよしやく)でゞもあれば其上(そのうへ)奥社(おくしや)迄(まて)猶遙(なほはる)か有(あ)る事(こと)とて多(おほ)く此(この)中社(ちゆうしや)限(かき)りにして歸(かへ)る其爲(そのため)の拜殿(はいてん)ゆゑ其(その)立派(りつは)なのは山中第一(さんちやうたいいち)であつた、社(やしろ)は白木(しらき)づくりの宏壯(くわうそう)な殿堂(てんどう)、他國(たこく)にも中(なか)/\珍(めつら)しい普請別(ふしんへつ)に案內者(あないしや)も持(もた)ずに見(み)たのみか、而(しか)も寺(てら)と違(ちか)つて其處此處(そここ〻)に塗抹彫刻(とまつてうこく)の飾(かさ)りが無(な)いために深(ふか)く目(め)に留(とま)る物(もの)も無(な)く、只(た〻)宏壯(くわうそう)と感(かん)じたのみであつたが、獨(ひと)り二間四方餘(にけんしほうよ)ばかりの一枚板(いちまいいた)の天井(てんしやう)に描(ゑか)いてあつた墨繪(すみゑ)の龍(りやう)、筆者(ひつしや)は誰(たれ)か、兎(と)に角(かく)非凡(ひほん)な出來(てき)、只(た〻)夫(それ)が目(め)について後(あと)で歸京(ききやう)して圖(はか)らず思(おも)ひ出(た)したのは即(すなは)ち是(これ)が曉齋翁(けふさいをう)【注15】の筆(ふて)であつたので、曾(かつ)て香亭氏(かうていし)の雅談(かたん)で讀(よ)みまた同氏(とうし)からも其(その)由緒(ゆゐしよ)を直接(ちよくせつ)に聞(き)いた事(こと)も有(あ)つた、それをさつぱり忘(わす)れ果(は)て〻しまつた、早(はや)く氣(き)がついたらと後(あと)で悔いるといふぬかりの至(いた)り、中社(ちゆうしや)から直(す)ぐ左(ひたり)にあたつて有(あ)つた社務所(しやむしよ)は社司(しやし)久山義男氏(ひさやまよしをし)の住(すま)ひであつた、柴田氏(しはたし)は久山氏(ひさやまし)と懇意(こんい)な中(なか)、柴田氏(しはたし)の案內(あんない)によつて先此(まつこの)社務所(しやむしよ)に著(つ)き泥足(とろあし)の事(こと)とて裏(うら)へまはり其處(そこ)の下男(しもをとこ)と顔見合(かほみあ)はせて柴田氏(しはたし)が愛嬌(あいけう)のある久(ひさ)しぶりの挨拶(あいさつ)、洗足(せんそく)の水(みす)に足(あし)を清(きよ)めて上(あか)れば俄(には)かに出(て)るくたびれ廣間(ひろま)二(ふた)つばかりを過(す)ぎて見晴(みは)らしのい〻一間(ひとま)に案內(あんない)された、時計(とけい)を見(み)れば正(まさ)に十二時(し)食膳(しよくせん)と蕎麥(そは)と共(とも)に言(い)い附(つ)けると引(ひ)き違(ちか)へて出した菓子(くわし)は例(れい)の越後(ゑちこ)へ行(ゆ)けば必(かならす)ある翁飴(おきなあめ)であつた休息(きうそく)して煙草(たはこ)一服(いつふく)袴(はかま)を脱(ぬ)ぎ捨(す)て今(いま)までの道(みち)の事(こと)を話(はな)しながらつら/\家(いへ)の建築(けんちく)を見(みれ)ば何(なに)さま昔(むか)し慕(したは)れるやうな、一間(いつけん)の木(き)目立(めた)つた椽側(えんかは)がはるかに走(はし)つて、小壁(こかへ)の高(たか)さは四尺(ししやく)ばかり、摺金(すりきん)の六角形(ろくかくけい)臍附(へそつき)の釘(くき)かくしも處(ところ)々取(と)れては居(ゐ)たもの〻、こ〻に衣冠(いくわん)で坐(さ)を廣(ひろ)く潰(くつ)しても失策(しつさく)は無(な)ささうな體(たい)、見(み)るからか古代(こたい)に生(うは)れた心持(こ〻ろもち)が爲(し)た、戶隱山(とかくしやま)と言(い)へば歴史(れきし)に緣(えん)の深(ふか)い山神代記(やましんたいき)のそも/\始(はし)め、天照皇大神(てんせうくわうたいしん)が素盞命(すさのをのみこと)の暴(ほう)を憤(いか)つてこもられた岩窟(いはや)は即(すなは)ちこの戶隱山(とかくしやま)で、今(いま)でもそれゆゑ手力雄命(たちからをのみこと)を祀(まつ)つてあるとの口傳(くてん)もあり、維茂(これもち)が此山(このやま)に分(わけ)け登(のほつ)て鬼女(きちよ)を退治(たいち)
した紅葉狩(もみちかり)の故事(こし)もあり(今(いま)でも山中(さんちゆう)に紅葉狩(もみちかり)といふ所(ところ)が存在(そんさい)する)また近(ちか)くは武田信玄(たけたしんけん)か河中島(かはなかしま)の戰争(せんそう)とかで埒(らち)の明(あ)かぬため早(はや)く勝(か)たせてと此山(このやま)に祈(いの)つた事(こと)もあり、または佐久間象山翁(さくまさうさんをう)が軍旗(くんき)と兵書(へいしよ)とを携(たつさ)へて此山(このやま)に籠(こも)つた事(こと)もあるなど、それやこれやを思(おも)ひ出(た)せば日本建國(につほんけんこく)の昔(むか)しからの二千年間(にせんねんかん)を一時(いちし)に短(つ)め合(あは)せに其處(そこ)に生(うま)れた心持(こ〻ろも)ち、ことには身(み)の前後左右(せんこさいう)すべて、古風(こふう)な物(もの)で無(な)いものはないわが姿(すかた)をさへ顧(かへり)みなければ全(まる)で明治以前(めいちいせん)の世(よ)の中(なか)であつた、吾(われ)々の部屋(へや)は奥書院(おくしよゐん)で其(その)前(まへ)には庭(には)が廣(ひろ)く造(つく)つてあつた、左(ひたり)に當(あた)つて峙(そはた)つ山(やま)、其(その)切(き)り岸(きし)からした〻る瀧(たき)の點滴(てんてき)が常(つね)に雨(あめ)の音(おと)をなして雨(あめ)をうれへる吾(われ)々の耳(み〻)を幾度(いくと)か欺(あはむ)いた、瀧(たき)の下流(かりう)から右(みき)へ折(を)れて出來(てき)た池水(ちすゐ)は泥(とろ)にこりて魚(さかな)も見(み)えず、流(なか)れを受(う)ける事(こと)とて絶(た)えず水面(すゐめん)は動搖(とうえう)して雲紋(うんもん)を絞(しほ)つた、水(みす)々として居(ゐ)るのは岸(きし)の草木(さうもく)ばかり、名(な)の知(し)れぬ草(くさ)に名(な)の知(し)れぬ木(き)、山蕨(やまわらひ)、木賊(とくさ)、さま/"\な苔(こけ)などが愛(あい)らしく雜生(さつせい)して、ことに驚(おとろ)いたのは菖蒲(しやうふ)の莖(くき)は有(あつ)ても蕾(つはみ)がやうやく催(もよ)ほしたと云(い)ふ位(くらゐ)な體(てい)であつた事(こと)である、七月の中旬(ちゆうしゆん)に菖蒲(しやうふ)が咲(さか)かぬとは、彼是(かれこれ)する內持(うちも)ち運(はこ)ぶ杯盤(はいはん)、向(むか)つて箸(はし)を取(と)れは空腹(くうふく)か中(なか)々うまい理料魚(れうりな)は燒(や)く煮(に)るにも岩魚(いわな)ばかり、其他(そのた)は玉子(たまこ)ばかり、しかし岩魚(いわな)の煮(に)ひたしから塩燒(しほやき)、また茶碗蒸(ちやわんむ)しに至(いた)るまで中(なか)/\深山(しんさん)で得(えら)れる物(もの)とは思(おも)はれぬ計(はか)り、特(こと)には戸隱(とかくし)固有(こひう)といふ地瘤(ちこふ)とか言(い)ふ菌(きのこ)の一種(いつしゆ)、それが他國(たこく)で迚(とて)も得(え)られぬ物(もの)であつた、地瘤(ちこふ)とは形(かた)ち土筆(つくし)の大(おほ)きなやう、蛇(へひ)の脊(せ)に似(に)た班(ふ)があつて其色(そのいろ)は薄鼠(うすねすみ)、口(くち)へ入(い)れはぬらついて一寸(ちよつと)言(い)へば蒪菜(しんさい)のやう、しかし美味(ひみ)であつた、是(これ)は地(ち)から取(と)つて数時間(すうしかん)立(た)つと腐敗(ふはい)して虫(むし)になるとか、其(その)ために戸隠(とかくし)より外(ほか)へ持出(もちた)す事(こと)も出來(てき)ず、長野(なかの)にも亦無(またな)程(ほと)である地瘤(ちこふ)の名(な)は猶(なほ)人(ひと)が知(し)らぬもの〻、蕎麥(そは)に至(いた)つては信濃(しなの)の人(ひと)で戸隠(とかくし)の名(な)を知(し)らぬ者(もの)は無(な)いくらゐ、東京(とうきよう)で更科(さらしな)【注16】が其(その)名所(めいしよ)と聞(き)いて、さて其(その)土地(とち)へ行(い)つて見(み)れば更科(さらしな)などさしたる方(ほう)では無いとの事(こと)であつた、蕎麥(そは)は縱(たて)六寸横(よこ)四寸ばかりの楕圓形(えんけい)の竹笊(さる)に揃(そろ)へてならべてあつた、決(けつ)して東京(とうきよう)などのやうに紊(みた)れさせては盛(も)らず、奇麗(きれい)にそろへて、山家(やまか)の蕎麥(そは)には他(ほか)でも間(ま)々この類(るゐ)がある、元(もと)よりいづれも盛蕎麥(もりそは)で種物(たねもの)は無(な)く、下地汁(したちしる)の蕎麥(そは)に比(ひ)して劣等(れつとう)なのが殆(ほと)んど玉(たま)に瑕(きつ)の心持(こ〻ろも)ち、藥味(やくみ)は葱(ねき)に山葵(わさひ) 乾海苔(ほしのり)の揉(も)んだの、是等(これら)でした、福武氏(ふくたけし)は常(つね)からの蕎麥黨(そはたう)、柴田氏(しはたし)もゆづらぬ相手(あひて)、や〻冷淡(れいたん)なのが私(わたし)であつた、やがてそろ/\さら/\、餘所(よそ)目からは蕎麥(そは)の食(た)べ方(かた)が一番(いちはん)をかしいもの鼻息(はないきは)あらくなる、目はすわつて、そして山葵(わさひ)の涙(なみた)で一杯(いつはい)になる一杯(いつはい)二杯(にはい)と片付(かたつ)けて相手(あひて)の両雄(りやうゆう)も頻(しきり)にひしめいて居(ゐ)た、しかし何(いつ)れも言葉(ことは)ほどには行(ゆ)かず、强(し)ひる斷(こと)はるでしばらくは捫擇(もんちやく)やがて食事(しよくし)も果(は)て〻それから
一先(ひとまつ)休息(きうそく)とて給任(きうし)の女(をんな)が蒲團小夜着(ふとんこよき)など持(も)たらしたのを幸(さいは)ひしばらく横(よこ)になつた二時半(にしはん)といふ頃(ころ)起(おき)て顔(かほ)を洗(あら)ひ、いさ〻か養(やしな)つた勇氣(ゆうき)を力(ちかや)にいよ/\それから奥(おへ)の院(ゐん)まで登(のほ)らうと決(けつ)した社司(しやし)の久山義男氏(ひさやまよしをし)は旅行中(りよこうちゆう)で不在細君(ふさいさいくん)が見(みえ)たを幸(さいは)ひ其(その)趣(おもむ)きを話(はな)せば眉(まゆ)をひそめて今日(こんにち)の道(みち)は御(お)わるう厶(こさ)いましやうとの言葉(ことは)、しかし思(おも)ひ立(たつ)た矢竹心(やたけこ〻ろ)は中(なか)/\之(これ)でしづまらず、笑(わら)つて決心(けつしん)の趣(おもむき)を答(こた)へるとそんならと言(い)つて子息(しそく)に案內(あんない)させてくれた、また舊(もと)のとほりの打扮(いでたち)、裏山(うらやま)を傳(つた)はつて山路(やまみち)に就(つ)けば何(なに)さまこたへたと言(い)はうか、何(なに)と言(い)はうか、其路(そのみち)のわるさ、道(みち)といふよりは泥(とろ)であつた、それもい〻が山路(やまみち)の常(つね)とてすさまじい虻(あふ)の攻撃(こうげき)、すこしでも油斷(ゆたん)すれば震(ふ)るへるばかりに噛(か)まれて跡(あと)には殘(のこ)る疼痛(いたみ)と痒(かゆ)み、ぬかつて扇(あふき)も團扇(うちは)も忘(わす)れて詮無(せんな)く辛(から)くもはんけちを振(ふ)るばかり、襟(えり)をはらへば足(あし)につく足(あし)を逐(お)へば顔(かほ)に來(く)る折角(せつかく)少(すこ)しい〻道(みち)を見付(みつ)けても繰(あやつ)り人形(にんきやう)の眞似(まね)するやうに手足(てあし)ふればよろめいて深(ふか)みへ飛び込(こ)むやらまた/\雨(あめ)の無(ない)のかせめても是(これ)で雨(あめ)に降(ふら)れたらそれこそ大變(たいへん)降(ふ)らなくても虻(あふ)の用心(ようしん)に安心(あんしん)しては四方(しはう)を見(み)られず、なる程(ほと)厄介(やくかい)な山(やま)とつく/゛\思(おも)ひ知(し)つた山(やま)はます/\登(のほ)る斗(はか)りいよ/\深(ふか)く行(ゆ)けば行(き)くほど行處(とこ)が奥(おく)だかわからぬ程(ほと)、道(みち)は左右(さいう)に林(はやし)と松(まつ)ばかり、何(なん)のながめも無(な)く、やがて次第(したい)に行(ゆ)くに從(したが)つて山氣(さんき)が凛然(りんせん)と肌(はた)にしみて來(き)た、蓊欝(をううつ)【注17】と茂(け)つてほのぐらくなつたのはまた樅(もみ)と松(まつ)との森(もり)で、中(なか)を通(とほ)して一條(いちてう)の道(みち)が有(あ)るばかり、森(もり)の奥(おく)には雑草(さつそう)や灌木(くわんほく)が叢生(そうせい)して人跡(しんせき)は少(すこ)しも止(と〻)めず、處(ところ)々足(あし)を奪(うは)ふやうに狂(くる)ひ立(た)つて飛(と)び流(なか)れる渓流(けいりう)の清(きよ)さ、道(みち)の向(むか)ふに當(あた)つて見(み)える一構(ひとかよ)への門(もん)、近(ちか)よつて見(み)れば荒(あ)れさびた隨神門(すゐしんもん)で、見(み)るから胸(むね)にとほる石の榜示杭(はうしくひ)に「下馬(げば)」とばかりに唯(た〻)一句(いつく)、將軍(しやうくん)の肖像(せうさう)を雨露(うろ)と時代(したい)に剝落(はくらく)してゐたが却(かへつ)て物凄(ものすこ)くなつて居(ゐ)た、空氣(くうき)は最早(もはや)ひやついて來(き)て、汗(あせ)は出(て)ても氷(こほり)のやう、それに深山(しんさん)ほとんど晦冥(くわいめい)、口(くち)に言(い)へぬ一種(いつしゆ)の臭(にほい)がしてあはれその梢(こずゑ)の上(うへ)に大魔王(たいまわう)でもゐるかの心持(こ〻ろもち)、少(すこ)し咳(せき)でもすれば木靈(こたま)の誤(あやま)らず荅(こた)へる、いよ/\凄味(すごみ)は加(くわ)はつて正(まさ)にありあり神霊(しんれい)に撲(うた)れるかの迷(まよひ)も出(て)るばかりであつた、戸隠(とがくし)は海面(かいめん)から五千尺(こせんしやく)の山(やま)、旣(すて)に此下馬(このけは)から絶頂(せつてう)までは遠(とほ)くも無(な)い事(こと)とて肌(はた)には異常(いしやう)な冷氣(れいき)を覺(おほ)えて來た、道(みち)の困難(こんなん)に津(しん)々と湧汗(わくあせ)、それも出(て)るや否(いな)や冷汗(ひやあせ)と變(かは)つて、身(み)の內(うち)が熱(ねつ)して外(ほか)が冷(ひ)え言(い)ふに言(い)はれぬ心持(こ〻ろもち)、のみか山(やま)には天狗風(てんくかせ)が怒號(とかう)して林立(しんりつ)した梢(こずゑ)を揉(もみ)み立(た)てる椽(とち)などの枝葉(しえふ)は脆(もろ)くも吹(ふ)き折(を)られて鳥(とり)の樣(やう)に飛(と)ぶ勢(いきほ)ひ、その凄(すさ)まじさ、草(くさ)も次第(したい)に乏(とほ)しくなり、艶欵冬(えんくわえごう)【注18】、獨活(とくくわつ)【注19】など嚴寒(けんかん)を物(もの)ともせぬのか多(おほ)く生(しやう)じてやがて奥院(おくのゐん)に近(ちか)づくに從(したか)ひ數十段出來(すしうたんてき)てゐる石段(いしたん)の上(うへ)に我物(わかもの)顔(かほ)に生(しやう)じてゐるのは樣(さま)々な苔(こけ)であつた、たゞ
木(き)ばかりは密封(みつふう)して絶頂(ぜつてう)を示(しめ)さず、わづかに泄(も)れる所(ところ)から仰(あほ)ぎ眺(なが)むれば大磐石(たいはんしやく)の屏風(ひやうふ)を建(た)てたばかり石段(いしたん)の盡(つ)きた所(ところ)が即(すなは)ち奥院(おくのゐん)であつた、社殿(しやてん)物凄(ものすこ)く寂莫(しやくまく)として飾(かさ)つてある一面(いちめん)の鏡(か〻み)の薄曇(うすくも)りしてゐるのが何(なに)やら靈氣(れいき)を帶(おひ)たやう、魔風(まふう)が時(とき)を賺(すか)さず吹(ふ)き掛(か)けて注連繩(しまなは)の定(さた)まる折(おり)も無(な)いくらゐ、之(これ)に並(なら)んで左(ひたり)にある社(やしろ)は九頭龍(くつりやう)神社(しんしや)と呼(よ)ぶ建物(たてもの)、九頭(くとう)の蛇(へび)を祀(まつ)つたものとか、蛇(へび)は今(いま)でも生(い)きてゐて日(ひ)々供御(くこ)する趣(おもむ)きで、見(み)れば社殿(しやてん)は岩窟(いはあな)にさしかけて出來(てき)、其前(そのまへ)に九枚(くまい)の土器(とき)が有(あ)り、蛇(へひ)が通(かよ)ふといふ廻廊(くわいらう)が些(すこ)しばかり出來(てき)てゐた、素(もと)より人(ひと)を禁(きん)じて窟(あな)には近(ちか)づかせず人(ひと)も此方(こちら)から眺(なか)めるのみであるが、窟(あな)は三尺餘(さんしやくよ)、隱(いん)々として薄暗(うすくら)く爲(な)つてゐた、両神社(りやうしんしや)から左(ひたり)の手前(てまへ)、さし出(て)た岩角(いはかと)に設(まう)けた一搆(ひとかま)への家(いへ)は即(すなは)ち奥社(おくしや)を護(まも)る男(おとこ)のゐる處(ところ)で、すべて岩(いは)を土臺(とたい)としまた岩(いは)を楯(たて)にして、一方(いつはう)社(やしろ)に向(むか)つた方(はう)は壁(かへ)が岩(いに)、岩(いは)の窪(くほ)みが即(すなは)ち竈(かまと)、入口(いりくち)は天日(てんひ)も洩(も)れず殆(ほと)んど暗夜(あんや)、音なひの聲(こゑ)に立(た)ち出(て)て來(き)たのはくくり袴(はかま)をとつぷり穿(ま)いて惣髪(そうかみ)に結(ゆ)つた男(をとこ)であつた、やがて客座とも言(い)ふところに案內(はんない)されて今(いま)一人(ひとり)の主(しゆ)の山守(やまもり)に應接(おうせつ)された客座(きやくさ)は八疊(はちてう)ばかりの座敷(さしき)、岩角(いはかと)へさしぬけた一間(ひとま)で欄干(らんかん)が古風(こふう)についてゐた、岩角(いはかと)の事(こと)ゆゑ眺(なか)めもい〻事(こと)、其處(そこ)で休(やす)んで遠近(ゑんきん)を望(のそ)めば何(なに)かなし、たゞ千里兩眼(せんりりやうかん)の中(うち)、裏口(うらくち)から絶頂(せつちやう)を仰(あふ)げば、さてもよく峙(そはた)つた事(こと)只岩石(た〻いわいし)の塊(かたまり)であつた、岩(いは)は妙義(めうき)あたりの粘土(ねんと)の樣(やう)に凝(こ)つたやうな物(もの)とは違(ちか)つて全(まつた)くの石(いし)、それで一面用捨(いちめんようしや)なく屹立(きつりつ)してゐた、苔(こけ)が滿(み)ちて足(あし)はすべる、わづかにある岩間(いはま)のひ〻か足(あし)の掛(か)け所(ところ)手の入(い)れ塲所(はしよ)、道(みち)の無(な)い處(ところ)に道(みち)を認(みと)めるばかりの至(いた)り、絶頂(せつちやう)は充分(しゆうふん)に見(み)盡(つ)くすには一日(いちにち)か〻るといふ廣(ひろ)さ、而(しか)も我(われ)も/\と峙(そはた)つ岩石(かんせき)の種(しゆ)々さま/゛\蟻(あり)のとわたりといふ道(みち)は幅(は〻)僅(わつか)に只(た〻)の五寸(こすん)、五寸の處(ところ)が即(すなは)ち峯(みね)の上(うへ)、左右(さいう)は底(そこ)も知(し)れぬ千尋(ちひろ)の谷(たに)、一步足(いつほあし)をあやまてば身體(しんたい)は粉粉微塵(こなこなみしん)、わづかに有(あ)る鐵繩(てつつな)が命(いのち)の本(もと)、鐵繩(てつつな)が切(きれ)たら身(み)は忽(たちま)ち谷底(たにそこ)の蛇(へひ)の食(く)ひ物(もの)である、こ〻に至(いた)るまでは勇氣(ゆうき)も火(ひ)と燃(も)えて、こ〻で忽(たちま)ち水(みつ)と冷(さ)めるが常(つね)とは誰(たれ)の心(こ〻ろ)も同(おな)じもののいざや幅(は〻)五寸の苔(こけ)にぬらつく自然(しせん)の危橋(きけふ)を踏(ふ)まうという處(ところ)で誰(たれ)かふるへずに居(ゐ)られやう、顫(ふる)へを促(うなか)す、寒氣(かんき)の殘虐(さんきやく)、七月の夏(なつ)が猶(なほ)冬(ふゆ)であつた、見(み)なければい〻に其處(そこ)が人情(にんしやう)、つひ谷底(たにそこ)をすかし見(み)れば乱雲白雪千年(らんうんはくせつせつねん)のま〻に殘(のこ)つて珍(めつ)らしい人間(にんけん)の生物(いきもの)に腮(あこ)を張(は)つて待(ま)つてゐるやう、風(かせ)さへ烈(はけ)しく足(あし)をとられる、誰(たれ)か立(たつ)てあるかれやう、馬琴(はきん)が庚申山(かうしんやま)で現八(けんはち)が石橋(いしはし)をわたる處(ところ)を叙(しよ)し、やす/\それを渡(わたつ)て現八(けんはち)は全(まつた)く柔術(ちうしゆつ)に長(ちやう)じてゐたよしを書(か)いた、それも流石(さすが)に思(おも)ひ當(あた)ること、こ〻に至(いた)つて這(は)はずに居(ゐ)られず、更(さら)に安全(あんせん)を索(もと)めて道(みち)を馬乘り(うまの)に跨(またか)つて擦(す)り行(ゆ)かずに居(ゐ)られず、こ〻まで攀(よ)ぢて【注20】くる人(ひと)すら少(すく)ない處(ところ)更(さら)
にこ〻で勇氣(ゆうき)を挫(くち)かれて立歸(たちかへ)る人が過半(くわはん)とか、思へば役行者(えんのきやうしや)【注21】が此處(ここ)をも經(へ)て更(さら)に絶頂(せいちやう)の最絶頂(さいせつちやう)の劔(つるき)ヶ峯(みね)に高足駄(たかあした)の齒(は)を鳴(な)らした恐(おそろ)しさ、蟻(あり)のとわたりを渡(わた)つて氣(き)のむくま〻、嶮岨(けんそ)に打(う)ち勝(か)ち打(う)ち勝(か)つてかけ回(まは)れば越後(ゑちこ)の海(うみ)もはや目(め)に入(い)つて而(しか)も信州(しんしう)甲州(かふしう)二國(にこく)をつらぬいて富士(ふし)も珍(めつ)らしく見(み)えるとは近(ちか)く見(み)れば飯綱(い〻つな)、黑姫(くろひめ)、妙高(めうかう)の諸山(しよさん)、遠(とほ)く眺(なか)めれば越中(ゑつちゆう)飛驒(ひた)の連山(れんさん)木曾(きそ)の山(やま)々、われを見(み)ろと言(い)はぬばかり、一劍(いちけん)直(た〻)ちに天宮(てんきう)を衝(つ)くのは鋒先山(はうせんさん)、一脉急(いちみやくきう)に空(そら)を支(さ〻)へるのは御嶽山(おんたけさん)あちこちに間斷(かんたん)なく湧(わ)く亂雲(らんうん)の樣(さま)も種(しゆ)々さま/\、つかれて山(やま)の腰(こし)にもたれ掛(かか)るもあり、怒(いか)つて大獸(たいしう)の牙(きは)を張(は)つて走るのもあり、其間(そのあいた)、さても奇絶(きせつ)、塵(ちり)に染(そ)まず、白(しら)げた峯(みね)の岩角(いはかと)に肩(かた)を怒(いか)らせてゐた、鷲(わし)が獲物(えもの)を見(み)てか、こ〻との天地(てんち)を我物(わかもの)がほ、縱横無盡(しゆうわうむしん)に飛(と)びまはる造化(そうくわ)一個(いつこ)の大觀(たいくわん)、ひるがへつて山(やま)の岩(いは)を仔細(しさい)に尋(たつ)ねれば、白玉(はくきよく)の山(やま)をなした水晶窟(すゐしやうくつ)、形(かた)ち怒(いか)つた獸王(しゆうあう)に似(に)た獅子窟(ししくつ)、天帝窟大多利窟(てんていくつたいたりくつ)、仙人窟(せんにんくつ)、大岩殿(たいかんてん)、歡喜屈(くわんきくつ)、金剛窟(こんがうくつ)、三世窟(さんせくつ)猿女窟(ゑんによくつ)、威德窟(いとくくつ)、不動窟(ふとうくつ)、西窟(せいく)、長岩殿(ちやうかんてん)、三層窟(さんそうくつ)、虛空窟(こくうくつ)、象(そう)が窟(くづ)、五色窟(こしきくつ)大隈窟(たいわいくつ)、小隈窟(せうわいくつ)、鷲窟(しゆくつ)、中窟(ちゆうくつ)利軍窟(りくんくつ)、金窟(きんくつ)、藥師窟(やくしくつ)、日中窟(につちゆうくつ)、大盤窟(だいはんくつ)、智慧窟(ちゑくつ)、醍酬窟(たいこくつ)、梯漸窟(たいせんくつ)、そして醍酬窟(たいこくつ)と藥師窟(やくしくつ)との間(あいた)にあるのが天岩屋(あまのいはや)、すべて岩(いは)がすなはち窟外(いはやほか)には佛掌窟(ふつしよくつ)など〻言(い)ふのも有(あ)つて窟(いはや)の數(かす)が大抵(たいてい)三十ばかり、思(おも)へばよく斯(か)う揃(そろ)つた物(もの)、あ〻山(やま)の奇(き)といひ、海(うみ)の妙(めう)といひ、自然(しせん)は無心(むしん)で作(つく)つたものがよくもかうまで究全(くわんせん)なもの近(ちか)づいてつら/\見(みれ)ば岩(いは)の色(いろ)は矢張(やはり)鼠(ねづみ)、それながら夏(なつ)の三伏囚人(さんふくしうしん)【注22】の着(き)る肌着(はだき)の色(いろ)とは思(おも)はれぬ、さても天地秀靈(てんちしうれい)の氣(き)の凝(こ)つたもの岩角(いはかと)にた〻ずめば千里一瞬(せんりいつしゆん)の風(かせ)が耳(み〻)を擦(そ)つて天(てん)は何處(ここ)まで連(つらな)る事(こと)かまた何所(ここ)まで高(たか)いことか素晴(すば)らしく大(おほ)きな夕陽(せきやう)が天神(てんしん)の球(まり)を抛(なけう)つて餘所(よそ)に分(わ)かつ餘光(よくわう)は永久不變(えいきうふへん)の天火(てんくわ)の彩色(いろと)り、咽喉(のと)わづか三寸、つんざける斗(はか)り叫(さけ)んでも裳(すそ)を玩(もてあそ)ぶ風(かせ)の囁(うそふ)きには勝(か)てず、目(め)を閉(と)ぢてちつと観念(くわんねん)、金輪(きんりん)を暗黑(あんこく)の皮裏(かはうら)湧(わ)かせても終(つひ)に消(き)えか〻る横雲(よこくも)の鍍金(めつき)の色(いろ)にさへ及(およ)ばぬさても偉人(いしん)とは何(なん)のことか、曾(かつ)て大平洋(たいへいよう)に向(むか)つて立(た)つた時(とき)、成(な)る程(ほど)海(うみ)はこんな物(もの)かと坐(そ〻)ろに舌(した)を巻(ま)いた、それと同(おと)じ心持(こ〻ろも)ち、しかし今(いま)比較(ひかく)して考(かんか)へれば海(うみ)の大(たい)と山(やま)の大(たい)とは亦違(またちか)つた所(ところ)も有(あ)つた、おもふに日本(につほん)の山(やま)は富士(ふし)、富士(ふし)でもない所(ところ)で是程(これほど)に考(かんか)へるのはや〻量(りやう)の狭(せま)い至(いた)りながら思(おも)ひ切(き)つて切(き)り開(ひら)けた天(てん)に向(むか)つた心持(こ〻ろもち)は要(えう)するに推(お)せる事(こと)であらう、で、比較(ひかく)すれば海(うみ)の大(たい)は快活(くわいくわつ)に近(ちか)く山(やま)の大(たい)は威嚴(ゐけん)に傾(かたむ)いたやう、例(れい)すれば海(うみ)は希臘(きりしや)の神らしく、山(やま)は印度(いんと)の佛(ほとけ)めいたやう浪(なみ)怒(いか)つて天(てん)を呑(の)む所(ところ)は壯(さかん)なもの〻、一且(いつたん)怒(いか)りが風(かせ)と共(とも)に消(き)えれば嬌羞(けうち)をうつす鏡(か〻み)を拭(ぬ)つて平和優美(へいわいうひ)、また愉快(ゆくわい)、之(これ)を山(やま)の千本(せんほん)の劍(つるぎ)はげしく空(くう)を刺(さ)し、千秋(せんしう)の靈氣(れいき)を凝(こ)らして人(ひと)を睨(にら)め下(くた)す所(ところ)に比(くら)べて凄(すさ)ましいの
はそも/\どちら、かさして、深(ふか)い考(かんかへ)へ催(もよほ)さぬもの〻、立(た)ち去(さ)るのは殆(ほと)んど强面(つら)いやう、夕暮(ゆうくれ)に促(うな)がされて割愛(かつあい)する事(こと)となつた、山守(やまもり)は愛嬌(あいけやう)のある男(をとこ)、若(わか)い時(とき)には江戶(えと)にも居(ゐ)たとか、た〻吾(われ)々を駭(おと)ろかしたのは前(まへ)に記(しる)した飯綱原(いつなはら)の鳥居(とりゐ)、その建立(こんりつ)は殆(ほと)んど十年前(しふねんまへ)で、立(た)つた以來(いらい)また一度(いちと)も其山守(そのやまもり)は見(み)ぬとのこと、即(すなは)ち山(やま)に起臥(きくわ)して些(すこ)しも下界(けかい)を踏(ふ)まぬ譯(わけ)、質朴(しつほく)て金錢(きんせん)をむさほらず、敞衣一枚(へいいいちまへ)が千年(せんねん)の裘(きう)、床(とこ)の間(ま)に吊(つる)したものを何(なに)かと言(い)へば冬雪(ふゆゆき)に山(やま)が埋(うつも)つた時(とき)の用意(ようい)に取(と)つて置(お)く獨活(うと)との事(こと)であつた、早足(はやあし)は引(ひき)ずるやう、やかて打(う)ち連(つ)れて中社(ちゆうしや)へ立(た)ち歸(かへ)る道(みち)、いづれも骨(ほね)は中(なか)々折(お)れたが、道(みち)で梢(こすゑ)などから下(さか)る猿尾草(さるをくさ)など見(み)れば飛(と)び附(つ)いたり、下(ふらさか)つたり、いよ/\草臥(くたひれ)に掛(か)けをした中社(ちゆうしや)の久山氏方(ひさやましかた)へは轉(ころ)げ込(こ)む、直(た〻)ちに風呂(ふろ)にころげ込(こ)む、透(すき)とほる湯(ゆ)に心氣(しんき)全(まつた)く快復(くわいふく)して一同(いちとう)沐浴(もくよく)を終(をわ)つてやがて膳(せん)に向(むか)へば早(はや)燈火(とうくわ)が點(つ)いた、夜(よる)は晝(ひる)とかはつて料理(れうり)いづれも佳味(かみ)であつたが、外(ほか)に猶(なほ)一(ひと)つ珍(めつ)らしいものが有(あ)つた、即(すなは)ち給仕(きうし)に出(て)た處女(しよしよ)、年(とし)は十七八、口重(くちおも)で容易(ようい)に物(もの)を言(い)はず、かざりも無(な)く唐人髷(とうしんまけ)を結(むす)んで飛白(かすり)の單衣(ひとへ)赤勝(あかかち)の帯(おひ)、質朴(しつほく)な、世(よ)にすれぬ氣色(けしき)正(まさ)にたつぷり、他日(たしつ)淸潔(せいけつ)な鄙(ひな)の少女(をとめ)を詩(し)か小說(せうせつ)に使(つか)ふ時(とき)には之(これ)に因(よ)つても宜(よ)ささうな、笑顔(ゑかほ)を出すのは惜(を)しいと言(い)ふ體(てい)、一寸(ちよつと)洩(も)らしたと思(おも)ふ間(ま)にすら見直(みなほ)せば何處(とこ)へやら燃燒(ねんせう)の早(はや)い花火(はなひ)といふ風(ふう)で、ことに其名(そのな)は扨(さて)も/\何(なに)かと言(い)へば「紅葉(もみち)」と一言(いちごん)、要(えう)するに是(これ)は紅葉狩(もみちかり)の故事(こし)から緣(ゑん)で命(めい)した名(な)、御前(おまい)が鬼女(きしよ)かと言(い)つてさへ泣(な)き出(た)さうかと危(あやふ)まれる程(ほと)、
秋(あき)はまた知(し)らぬ深山(みやま)の若(わか)もみち
いかなる風(かせ)の色(いろ)に染(そ)むらん
夜(よ)の寒(さむ)さは骨(ほね)に透(とほ)つて中霄(ちゆうせう)目(め)が覺(さ)めて廓下(らうか)へ立(た)ち出(いつ)れば寢衣(ねまぎ)一枚(いちまへ)なか/\凌(しの)ぎ切(き)れず、溪流(けいりつ)の音(おと)は山風(やまかせ)に通(かよ)ひ分(わか)つてその筈(はつ)思(おも)へば身(ミ)は五千尺(せんしやく)も上(うへ)の事(こと)、朝景色(あさけしき)のうるはしきは言葉(ことは)に盡(つ)くされず久山氏(ひさやまし)が貸(か)してくれた羽織(はをり)を引掛(ひきか)けて、ふた〻び近所(きんしよ)を散歩(さんほ)して富士(ふし)などをさぐり眺(なか)めて立(た)ち歸(か)へつて食事(しよくし)につき、それからはトランプ又(また)花(はな)かるた、又(また)第一(だいいち)に志(こ〻ろさ)した所藏(しよさう)の寶物(はうもの)など見(み)た、寶物(はうもつ)は久山氏(ひさやまし)の家(いへ)に預(あつか)る分(ふん)が長持(なかもち)に三つばかり故(こと)さらに許(ゆる)されて吾(われ)/\の自由自在(しゆうしさい)見張(みは)りも何(なに)もせず勝手(かつて)に引(ひ)き出(た)して自由(しゆう)に見(み)せて來れた久山氏(ひさやまし)の親切(しんせつ)は深(ふか)く感謝(かんしや)する、實(しつ)は何處(とこ)の名所(めいしよ)舊跡(きうせき)でも案內(あんない)が錢(せに)を貪(むさほ)つて早口(はやくち)に由緒(ゆるしよ)を說(と)いて人(ひと)に隔靴(かくくわ)の感(かん)【注23】をいだかせるのは普通(ふつう)の事(こと)、此日(このひ)自由(しゆう)に品(しな)に近(ちか)づいて寫(うつ)すことの出來(てき)たのは何(なに)よりも仕合(しあは)せであつた、寶物(はうもつ)は多數(たすう)で數(かそ)へ切(き)れぬもの〻、其中(そのうち)での尤物(いふふつ)抜(ぬ)けば即(すなは)ち左(さ)の品(しな)々であつた、」
一 持統天皇(しとうてんわう)御所用(こしよよう)犀角御笏(さいかくおんしやく)(形(かた)は後世(こうぜい)の笏(しやく)より小形(こかた)で切落(きりおと)しも少(すく)ない方(かた))
二 後醍醐天皇(こたいこてんわう)宸翰(しんかん)
三 御陽成院(こやうせいゐん)懐紙(くわいし)(歌(うた)の題(たい)は重陽月詠菊有新花とあり歌は「うへかへてなをいくあきと契(ちき)らまし、けふをはしめの白(しら)きくの花(はな)」伹しこの假名は思ふ所あつて原文の儘にした)
四 正親町天皇和歌(あふきまちてんわうのわか)(「みよしのの山(やま)の白雪(しらゆき)つもるらし、ふる郷(さと)さむくなりまさるなり」例(れい)の有名(いうめい)の御歌(ぎよか)である)
五 御光嚴院歌切(まくわうけんゐんうたきれ)
五 定家鄉式紙(ていかきやうのしきし)(たのみてし常盤(ときは)の山(やま)も大空(おほそら)の霞(かすみ)にかすむ世(よ)にこそありけれ)
七 賴政和歌二首(よりまさのわかにしゆ)(是(これ)は取(と)り落(お)として忘(わす)れた)
八 武田信玄願狀(たけたしんけんくわんしやう)(上杉(うへすき)に對(たい)して勝軍(かちいくさ)を戶隱山(とかくしやま)に祈(いの)つた漢文(かんふん)の願狀(くわんしやう)、年付(としつけ)は永祿元年(えいろくくわんねん)戊午八月(ほこはちくわつ))
九 西山公書翰(せいさんこうのしよかん)
十 德川秀忠和歌(とくかはひてた〻わか)(題(たい)は蓬不蓬戀(あふてあはさるこゑ)「千鳥(ちとり)なく澤邊(さはへ)のちはら風絶(かせた)えて蓬(あ)はてそ歸(かへ)る有明(ありあけ)の月(つき))
十一 慈眼大師一行物(ぢかんたいしいちきやうもの)(長生殿裡富春秋(ちやうせいてんりしゆんしうにとむ))
十二 烏丸光廣卿百人一首
十三 兆典司羅漢圖二幅
十四 探幽雪中文珠圖
十五 同人丸像(題歌ほのほのは守澄親王)
十六 石川丈山賛堂堂武矦圖(畵は狩野安重)
十七 戶隱山紅葉狩繪卷物二卷(畵工筆者共に不分明)
其他には佐久間象山の旗、家綱將軍にはとりの畵など一寸珍らしい物が許多、外に刀劔類に至つては凄まじい物が無數であつた、
晝(ひる)すこし過ぎてから名殘をしい山を下りはじめ、寶光社に立寄つたそれからの歸り道はいづれも前日と同樣であつた、山には種ヶ池、涌池などいふ池もある趣であつたが吾々は見なかつた、何にしろ今思ひ出しても其凛然とした姿は目にも逼るああ秀靈の名山、
【注1】
山田武太郎。明治時代の小説家、詩人、劇作家、辞書編纂者で、美妙齋などと号す。尾崎紅葉らとともに「硯友社」を結成、機関誌『我楽多文庫』に小説『竪琴草紙』などを発表した。このころから言文一致運動に着手した。
【注2】
長野県長野市にある山で、信州百名山および北信五岳の一つとして知られている。古くから修験道の道場で、山の中腹には戸隠神社があり、古くから信仰の対象となっている。明治の廃仏毀釈が行われるまでは、戸隠神社に聖観音菩薩が祀られていた。
【注3】
大分県中津市にある山国川の上・中流域及びその支流域を中心とした渓谷で、日本三大奇勝として知られ、日本新三景として名勝に指定されている。耶馬日田英彦山国定公園に含まれる。
【注4】
妙義山(みょうぎさん)は、群馬県甘楽郡下仁田町・富岡市・安中市の境界に位置する日本三大奇景の一つとされる山である。この険しい岩峰の尖った荒々しい山容の奇観から日本三大奇景の一つに数えられており、また国の名勝に指定され、日本百景にも選ばれている。
【注5】
紅葉狩(もみじがり)は、能の一曲で平維茂が鬼退治をする物語を描いている。この能は、長野県の戸隠、鬼無里(きなさ)、別所温泉などに伝わる紅葉伝説に基づいており、紅葉という鬼女との戦いが中心となっている。
【注6】
長野県と新潟県を指す総称である。この名称は、かつての令制国名である信濃国と越後国に由来するが、佐渡国である佐渡島も信越に含めて扱われることが多い。
【注7】
綿入れのこと。昔、庶民が胴着にして着物の下に着たり、あるいは上着に用いたりした粗末な防寒衣で,とくに綿の厚く入ったもの指した。
【注8】
現在「旭山(あさひやま)」と表記されているこの山は、長野市のシンボル的存在となっている。旭山の中腹には朝日山観世音堂があり、合格祈願のご利益があると知られている。
【注9】
往生寺(おうじょうじ)は、長野県長野市にある浄土宗の寺院で、山号は安楽山、院号は菩提院。善光寺の奥の院にあたり、善光寺西側の高台にある。
【注10】
鎌倉時代前半から中期にかけて活躍した僧で、鎌倉仏教の一つ、浄土真宗の宗祖とされる。越後での流刑を終えた親鸞聖人は、関東に赴く前に戸隠を訪れたという伝承がある。
【注11】
飯縄山(いいづなやま)は、長野市、上水内郡信濃町、飯綱町にまたがる山で、北信五岳の一つとして知られている。古くから山岳信仰の霊山であり、飯縄権現を祀り修験道場が開かれ、上杉謙信など武将の尊崇を得ていた。
【注12】
巉崖(ざんがい)は険しい崖、絶壁(ぜっぺき)は切り立った崖をいう。
【注13】
群馬県中部、渋川市の旧町名。榛名山(はるなさん)東斜面の中腹にあり、古くからの温泉町である。
【注14】
群馬県安中市と長野県北佐久郡軽井沢町の境界にある峠で、千曲川水系と利根川水系とを分ける中央分水嶺である。古くから中山道の難所として知られ、安中市側の麓には碓氷関所があった。
【注15】
川鍋周三郎。幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師、日本画家で、曉齋と号した。筆禍事件で捕えられたこともあるほどの反骨精神の持ち主で、多くの戯画や風刺画を残した。
【注16】
現在の長野県千曲市および埴科郡戸倉町付近を指す。姥捨て山(うばすてやま)伝説や田毎(たごと)の月などで有名である。また、上質なそばの産地としても知られている。
【注17】
草木が盛んに茂るさま。
【注18】
欵冬は蕗(ふき)の別名なのでツワブキ(石蕗)のことか。
【注19】
山菜のウドのこと。
【注20】
あがろうとしてすがりつくこと。
【注21】
役小角(えんのおづね)。飛鳥時代に奈良を中心に活動していたと思われる、修験道の開祖とされている人物。
【注22】
初伏(しょふく)、中伏(ちゅうふく)、末伏(まっぷく)の総称で、7月中旬から8月上旬頃の、夏の最も暑い時期意味する。
【注23】
はがゆくもどかしい思いをすること。