東征軍を迎える過程で各藩は新政府への恭順をせまられていった。下野国で最も早く新政府側に態度をかえたのは外様藩の黒羽藩であった。特に三月一五日江戸城攻撃の段階で譜代大名たちはその態度決定をせまられた。宇都宮藩もこの宿命的決断にせまられ、藩内の勤王、佐幕両派の対立が激化し、三月一六日から一週間にわたって論議が続いた。勤王で藩論の統一をみたのは三月二三日であった。藩論をまとめた県六石は二九日板橋宿の東山道総督府に藩の態度を述べ、宇都宮周辺の実状を説明し援軍の派遣を願い出た。
この時期、東山道総督府は下野各藩に次のような達書をだしている。
上、武、野州徳川並ビ旗本ノ知行所ハ、総テ当国列藩ヘ鎮撫方仰セ付ラレ候間、各藩申シ合セ、持場ヲ定メ、諸方ヘ人数差シ出シ、賊徒ノ乱妨ヲ除クベシ、諸藩脱走人或ヒハ無宿ナドニ至リテハ、速ニ死刑ヲイタスベシ、尤モ百姓ト雖モ平日ノ所行ヲ糺シ、夫々所置ニ及ブベシ(『復古記』十一巻)。
東征軍はすでに板橋に到着していたが、江戸開城を目前にした関東各地は陣屋の役人たちは逃げ出してしまい「政令廃絶を幸にして無頼の悪徒どもが愚民を欺き、党を結び、富家に押入り金銀を奪い、民衆が塗炭の苦しみに陷ってた」として出されたものである。
高根沢地域は宇都宮藩、喜連川藩、一橋藩、真岡代官領その他旗本支配下にあった関係で幕領、藩領、旗本領に分かれ、新政府による支配への転換を前にして、その対応は微妙な対立地図を示し、悩める地域であった。
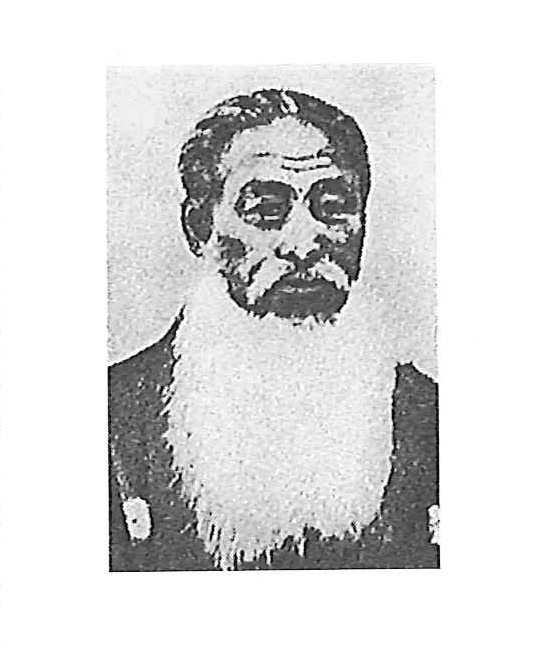
図2 県 六石(『栃木県史』通史編6近現代1より)