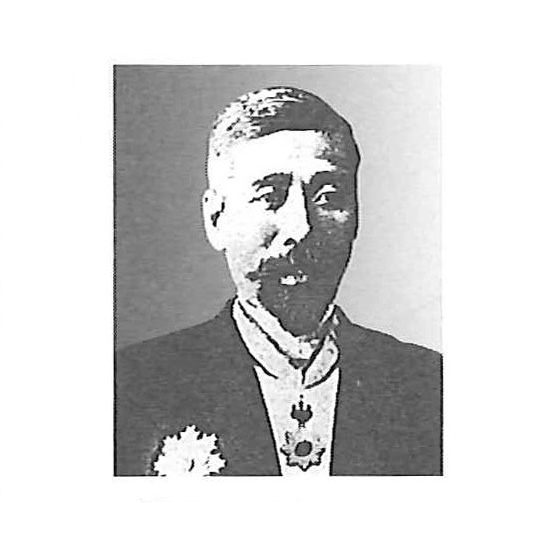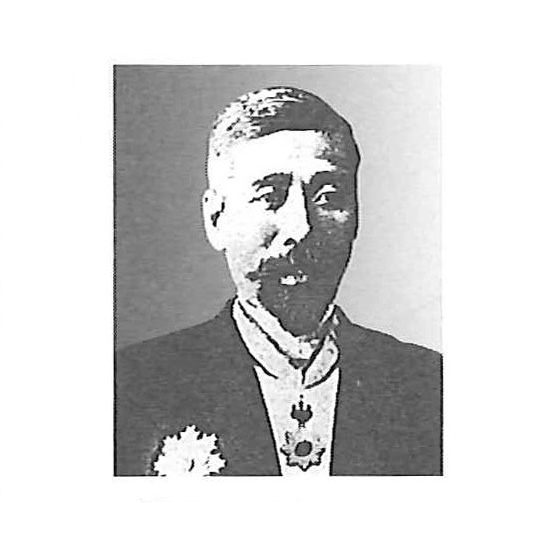明治二一年(一八八八)四月二五日、市制及び町村制が公布され(二二年四月一日より施行)、六月に山県有朋内務大臣は町村合併規準を地方長官に訓令した。規準内容は「町村ノ区域狭小若シクハ僅少ニシテ、独立自ニ耐ユルノ資力ナキモノハ、大凡三百戸乃至五百戸ヲ以テ標準ト為シ、猶ホ従来ノ習慣ニ隨ヒ、情願ヲ酌量シ民情ニ背カザルヲ要ス」と述べ、合併するときは交通の便など地理的条件を考慮するように指示した。これに基づいて、翌年にかけて町村合併が促進された。新町村の名称については、大町村が小町村を併合する場合は大町村の名称を、数町村合併の場合は「各町村ノ旧名称ヲ参互折衷スル等勉メテ民情ニ背馳セザルコト」が強調され、いずれの場合も旧名称を大字の名前として残すことが保証された。
栃木県では町村制実施によって村々は合併され、一〇九町一一四八か村が一七一か町村に集約された。そこには数個の町村を包括する戸長役場管轄の理念を継承しながら、さらにそれを発展させて、町村連合体から新しい町村への飛躍を強行した政策があった(大島美津子著『明治のむら』)。
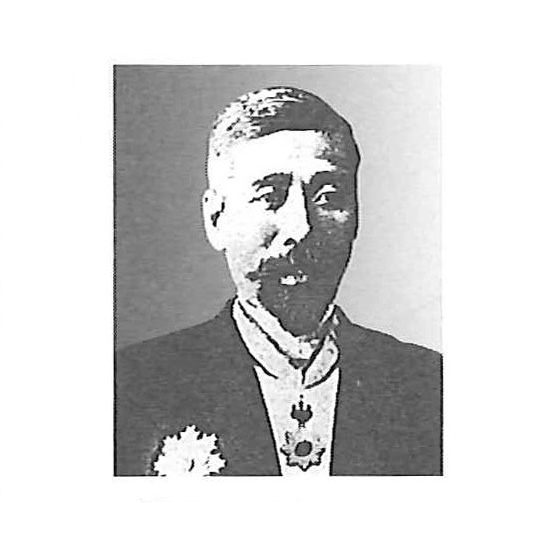
図38 山県有朋