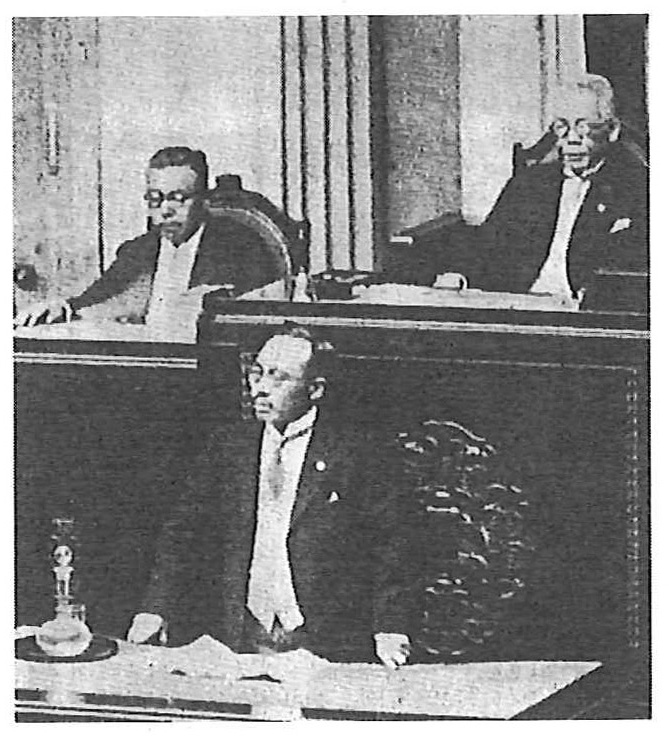麻生の立候補した一区には選挙区制は違っていたが、前回まで足利出身の政友会幹部の横田千之助がいて明治四五年の第一一回総選挙以来連続五回当選していた。この間、横田は政友会幹事長、原内閣の法制局長官などを歴任しており、大正一三年の第二次護憲運動では政友会側の中心になって活躍し、加藤護憲三派内閣に司法大臣として入閣した。しかし、残念なことに翌年二月病没した。そして、横田の補欠選挙の時、神奈川で落選していた森恪が招かれて栃木七区(那須・塩谷、定員二名、横田と高田耘平が当選、昭和三年からは中選挙区の一区に入る)から立候補、当選した。森が栃木県で立候補するようになったのは、県政界と縁が深く政友会院外団にもいた代議士志賀和多利が横田の葬儀で元県議小野崎甚吉(塩谷郡選出)に会い森の立候補を打診したところ、小野崎が「大横田の伝統を継げる人物」として賛成し、塩那地区の意向をまとめ、政友会支部長榊原經武の了解を得たという(森恪伝記編纂会『森恪』)。また、森の推薦者には大谷の石材業者で県政友会の実力者渡辺陳平がいたという(岩田豊秋著『栃木県政物語』)。渡辺は志賀と親しかったから、森の支援を頼まれたとも考えられる。森は最初の補選のときは精力的に矢板、大田原などで演説会を開いたが、その後は東京で政友会の選挙の采配をとることに忙しく、本籍は移したが、選挙区にはあまり来られず、地元の県議・町村会議員を督励して選挙をしていた。森は田中内閣で外務次官、昭和四年四月からは党幹事長という要職にあった。外務次官当時の昭和二年六月には「東方会議」を実質的に主宰し、軍部と外交官、政府による対中国強硬外交の方針(満蒙特殊権益の確保、満蒙の治安維持、満蒙分離、共産党の鎮圧と国民党支持、居留民の現地保護等)を決め、中国侵略の方向を決定づけるのに大きな役割を果たした。
足尾では麻生が落選すると、足尾鉱業所が銅山の鉱夫組合潰しにかかり、石山らの交渉も効なく組合幹部七五名が事実上解雇されて、鉱夫組合は力を失っていった。石山らは活動の場を鹿沼、宇都宮へと広げ、争議指導や労組結成に努めていた。
日本労農党は三・一五事件のあと政党合同をはかり右派の日本農民党と合同、三年一二月に日本大衆党を結成するが四年には党内で対立した左派・鈴木茂三郎ら、右派・平野力三らを除名、五年七月には全国民衆党、無産政党統一全国協議会と合同して全国大衆党(委員長麻生、書記長三輪寿壮)を結成した。大衆党は全国労働組合同盟会(全労、総同盟の後身)と全国農民組合(全農)をバックに満州事変直前の昭和六年七月、無産政党を統一する全国労農大衆党(書記長麻生、七年社会大衆党)を結成した。
昭和六年九月、満州事変が始まると、労農大衆党は対支出兵反対闘争委員会を設けて「帝国主義戦争反対」を強く主張したため、これまでより一層激しい弾圧を受けるようになった。六年一二月の大会では「最近、ストライキにおいて在郷軍人、青年会、消防隊までが暴力的鎮圧に参加し、暴力団が(日光鉱山、福岡県会、下関市会において)無産階級の戦士に白刃をもって切りつける等、これらはファッショ的傾向の社会的動向を如実に示すものである」とこれまでとは違う弾圧の変化が指摘されていた(麻生久伝刊行委員会『麻生久伝』)。
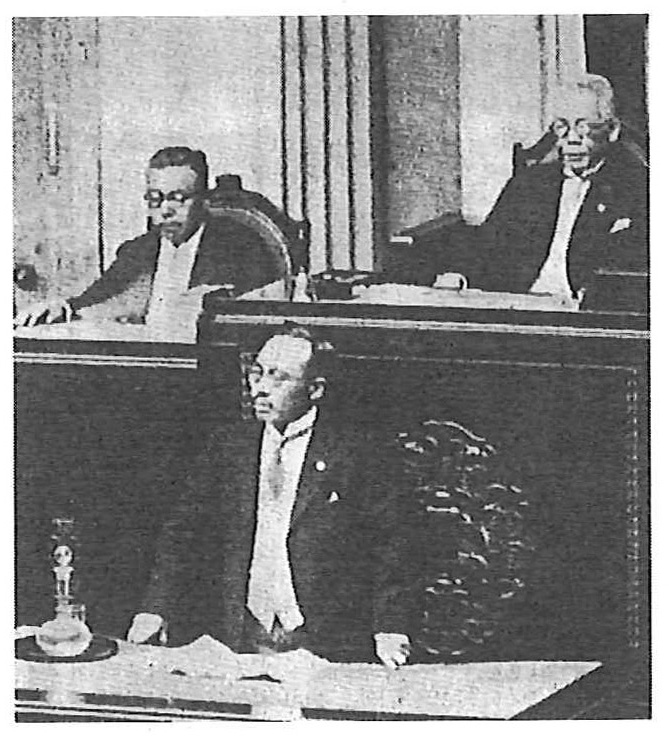
図9 昭和7年満州国承認演説をする森恪(『森恪』山浦貫一編著森恪伝記編纂会発行より)