阿久津村事件の後はじめての全農県連大会が昭和八年二月県公会堂で開催された。全農支部は六八に増え、組合員も二、六四八名と事件前を上回り、党・全農県連はかつての活力を取り戻したかにみえた。しかし、満州事変の拡大と戦争協力の大合唱のなかで全国労農大衆党は「帝国主義戦争絶対反対」のスローガンをいつの間にか下ろしていた。
昭和七年五月、赤松克麿、平野力三らが社会民衆党を脱して日本国家社会党という国家主義政党をつくり、満州事変支持を打ち出すと、無産政党指導者の間には動揺が広がった。五・一五事件や血盟団のテロに現われたファシズムの流れを断ち切るため、大衆党は社会民衆党と合同して七月に社会大衆党(社大党)を結成した。この政党により無産政党の戦線統一が初めて実現した。しかし、戦争とファシズムの重圧の中で活動の場は年々せばまっていった。そして、昭和九年のいわゆる「陸軍パンフレット」(国防の本義とその強化の提唱)以降、社大党は書記長麻生を中心に「軍隊と無産階級の合理的結合」による社会改革を唱え、急速に軍部革新派に接近していった。
県内では八年八月の社大党県連執行委員会で、幹部の黒沢、大貫、雨谷、田代らが脱党した。かれらは大貫を除き、栃木県経済同盟(中野正剛らの国民同盟の系統)という反共産主義、農本主義、軍国主義、統制経済を主張する団体をつくって(一二月三日創立)運動から離れていった。上野久内、螺良和男らも黒沢に同調した。彼らは阿久津事件の最終判決を前に転向したのである。これまでの労農大衆党県連には大屋を中心とする全農県連(左派)と黒沢・石山を中心とする全労県連(右派)の二つの系統があり、大衆動員による争議支援などは全農と大屋らが再建した大谷石材労組に頼って行われていた。大屋は社大党の右翼化に反対し、麻生に対しても批判的であった。黒沢らの脱党は大屋の社大党批判を強め、しだいに石山とも対立して運動は分裂し、農民運動に対する社大党の影響力はほとんど失われていった。
昭和一〇年四月、阿久津村石末の小作争議が再び報じられた。全農阿久津支部の組合員の小山栄太が地主野沢茂堯に対して九年度の不作を理由に小作地一町一反歩の小作料の五割減額を要求した。野沢はこれを認めず、四月一五日に内容証明郵便で土地返還要求書を送った。その夜、小山の小作田に積んであった藁が不審火で燃えた。一七日には野沢側が小山の小作田に栽培中のレンゲを掘り返して、対決姿勢を強めた。阿久津支部は全農の支援を得て組合員三〇余人が参加して、一八日午後一時を期して共同耕作を実施した。両者の対決状態はしだいに先鋭化してきた。前回の争議が流血の大事件になったことは人々の記憶に新しかったから、喜連川署と県特高課は緊密に連絡をとり争議の解決に介入してきた。五月二日、喜連川署長は調停に入り両者と協議の結果、次の条件で解決した。
一 小山は野沢所有の小作地全部を返還すること
一 レンゲ代金一五円を地主が支払うこと
一 小山が農民組合を脱退する条件で未納小作料を免除する
そして、組合長の斉藤寅松も野沢の小作地の小作料五割減額を条件に組合長を止めることになった。こうして、石末小作人組合以来の全農阿久津支部は昭和一〇年五月をもって解散となった。
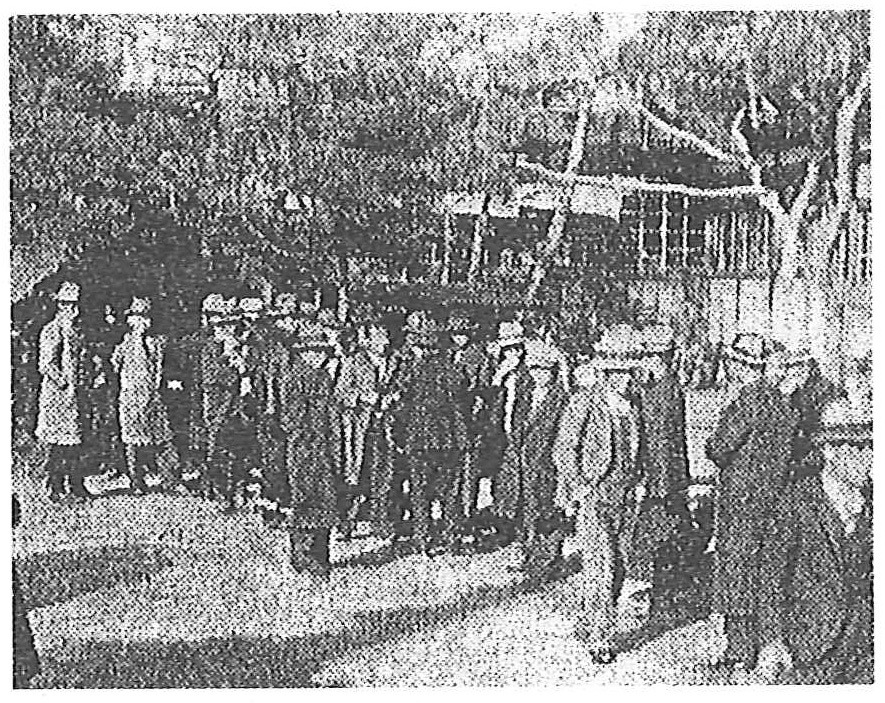
図17 監獄へ入るため裁判所へ集合した事件の被告たち(「東京日日新聞」昭和8年12月22日)