「ニュース」三号(九年三月一五日)で理事の横尾は「第一回大会を前にして特に組合理想を強調す!」と題した産青連の論説的論文で「産業組合運動は農民一般被搾取階級の協同的経済運動」だが、それのみを強調して「組合運動の社会的理想を忘却して営利主義産組と堕し、硬直し、老衰し、遂に全面的革新を要求せられるにいたった」そして、「明日を絶望せしむる資本主義社会の諸欠陥を修正しつつ協同組合による新社会建設の理想」を高く掲げて組合拡充計画に取り組むことを求めていた。
また同号で渡辺佳勇は「農村産組の自己批判と産青連」と題する論文で、産業組合の活動を販売・購買の価格上の問題でみれば、多くの保護と特典を与えられた営利会社と変わらないとし、「農村産組本来の性質は自主的農村経済の建設」で商行為はその一手段であるとし「農村産組の目的は農村の販売・購買物の価格の決定権の獲得」にあるとして、「産組の政治的活動こそ中間商人蟠居の隙を陥落せしめ、農民を資本への隷属から解放せしめ(中略)、結局に於いて自主的農村経済建設にまで導くであろう」と「政治的活動」の重要性を訴え、若人は「未来の統制された協同的な農村社会に就いて」語ろうと書いている。
第一回県産青連大会(三月一五日於県商工奨励館)では産業組合活動の促進策、女性の加盟促進策、産青連と各種青年団体との協調策、反産運動への対応策などが討議されたが、明治村産青連提出の「産青連として政治運動参加の可否いかん」については余り討論されず、うやむやに終わったという。「ニュース」第四号に塩谷郡泉村産青連はこの点を批判し、我々の全購連は肥料、飼料、ゴム靴工場を建設して配給統制の基礎をつくっているが「更に一歩進んで重要肥料、雑貨の全部的生産を敢行」すれば「資本主義的統制と対立し、両者の抗争は先鋭化するだろう」とし全購連がそこまで発展しないうちに「産業組合の使命を制約する強圧」がくるとして「やがて到来する危機の打開」のために政治的進出をしなければならないと、渡辺の意見を支持した。これらの意見は産青連内の左派的立場を代表するものであったが、全体的には少数派で、「既成政党に依存し」「政党・政派をこえて」産業組合支持勢力を増やせばよいという意見が多数派であった。
こうした内部対立はあったが、産青連は産業組合活動の手足として各地で活発に運動を展開し、組合員の獲得、米販売の増加、肥料、雑貨の共同購入、上都賀の医療組合上都賀病院建設、大麻県営検査問題などに取り組み、これまでの商人と手を組んで販売、購買の下請けをするような古い体質の産業組合から脱皮していった。
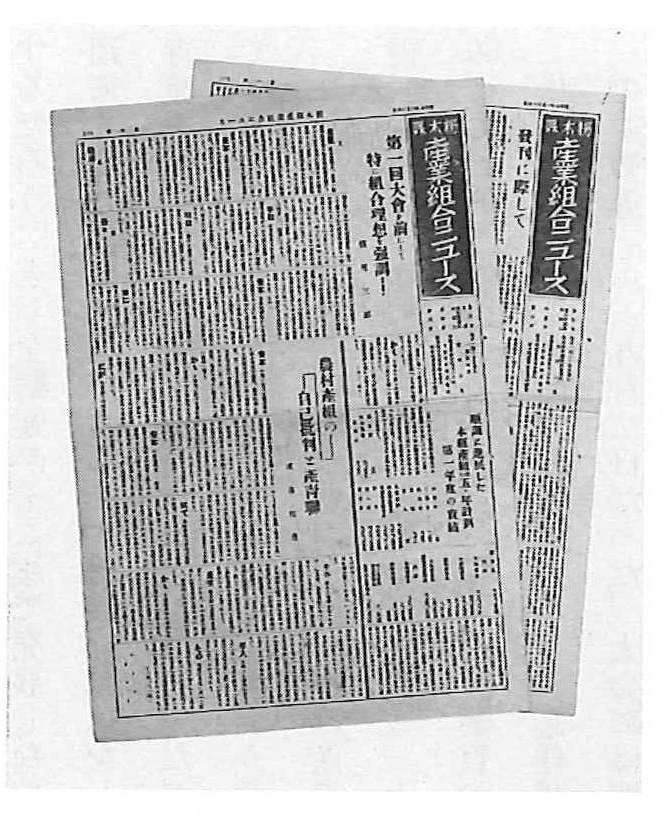
図21 「産業組合ニュース」創刊号と渡辺論文のある3号(栗ヶ島 渡辺章一家蔵)