この時期の政府は「経済自立」政策をたて、戦争中に壊滅した重化学工業を復興・発展させる産業基盤の強化を図っていた。それは、石炭、鉄鋼、造船、化学肥料、電力という基礎部門へ設備改善と新技術導入のための資金・資材を集中的に投入する政策であった。
この自立政策の中で農業と農村が担ったのは、米麦を主に食料を増産し、自給力を高めることだった。昭和二五から二七年の食糧自給率は穀物全体で八〇パーセント、大豆五〇パーセント、牛乳・乳製品八〇パーセントと現在とは比較にならない自給率の高さではあったが、それでも当時としてはかなりの部分を輸入に依存していると考えられ、貿易赤字の原因とされていた。だから、食糧増産政策の背景には次のような事情があった。
(イ)食糧危機は緩和されたとはいえ、輸入に占める農産物の割合は五〇~六〇パーセントであり、これが輸入超過の大きい原因となって日本経済に外貨不足をもたらしている。これを解決するには食糧増産が不可欠である
(ロ)国内農産物価格は占領期から輸入農産物価格より低く抑えられていたので、輸入農産物には価格差補給金をつけて安く販売していたが、これが財政を圧迫する要因となっている。そこで、国内農産物価格を輸入農産物価格並に引き上げて、農民の生産意欲を高めて増産させ、輸入を減らし、そこに生じる外貨と財政資金の余裕を重要産業基盤強化へ集中的に投下したいという強い要求があった。
(ハ)都市工業の復興が始まったとはいえ、農村には二、三男を中心に人口過剰の状態が続いていた。彼らの就業確保のためにも食糧増産政策は有効だとされていた。

図33 米づくりの実験深耕・直播(昭和29年)
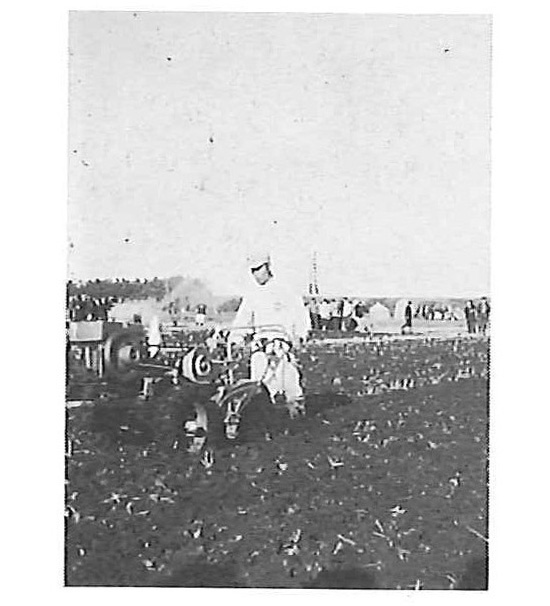
図34 動力耕耘機の競技会(昭和30年頃)

図35 稲刈り機の実演風景